
●大晦日(おおみそか)は12月31日を指す言葉であるが、晦日(みそか)から来ている言葉です。「晦」は月の満ち欠けが変化する様子を表わす言葉の1つで、月が隠れることを意味している。また、晦日は別名「つごもり」とも呼ばれ、同じく“月が隠れる”という意味の「月隠り(つきごもり)」が転じた読みである。旧暦は月の満ち欠けで暦が決まっていた。新月を1日とし、月が隠れる「晦」の頃がおおよそ30日であったことから、30日を晦日と呼ぶようになった。30歳を“みそじ“という。“みそ“がもともと30の読みであることをみるとわかりやすい。新暦に変わり、実際の日付が30日でなくとも毎月の末日を「晦日」と呼び、晦日の中でも1年を締めくくる12月には大をつけて「大晦日」と呼ぶようになった。
一年を締めくくる最後の「晦日」が「大晦日」である
●大晦日の歴史はかなり古く、平安時代まで遡る。昔、大晦日は正月に迎え入れる歳神様(としがみさま)をまつるための準備の日であった。歳神様とは、稲の豊作をもたらすとされている神様のことで、農作物が豊かに実り、食べるものに不自由することなく暮らせるようにと、昔から大切に扱われてきた神様である。また、歳神様は各家庭にやってくることから、家を守ってくれる祖先の霊とも考えられていたようだ。
◉除夜の鐘
大晦日は「除夜」とも呼ばれており、大晦日の夜から1月1日にかけて鳴らす除夜の鐘は今でもよく知られている。鐘を撞く回数は人の煩悩の数を示す108回で、寒空の下で響く鐘の音に誰しも一度は耳を傾けたことがあるように、煩悩を取り去り、正しく清らかな心で新年を迎えることができるようにするものである。
◉年の湯
大晦日の夜にお風呂に入ることを「年の湯」と言い、ここでしっかりと一年の垢を落とし、気持ち良く新年を迎える。今と違い、毎日入浴することが当たり前でなかった時代は、大晦日の入浴が特別なものであったに違いない。
◉年越し蕎麦
「年越し蕎麦」を食べる習慣は比較的新しく、江戸時代から始まったと言われている。別名「つごもりそば」、「三十日そば」とも呼ばれ、細く長い見た目から長寿や健康を願って食べられるようになった。また、蕎麦の麺は切れやすいことから「一年の災厄を断ち切る」という意味もある。

年の瀬に朝から晩までどの番組も大相撲の暴力問題。確かに暴力は許されるものではないがこの問題に端を発してダラダラとひと月にも及ぶほどこの問題にこだわることは無いようにも思う。もっと他に取り扱うべき大事なニュースはあるのにと思うのは私だけだろうか。
テレビのニュースの在り方に疑問を抱きます。
気分直しにこんな記事が目に留まりました。・・・少子化問題。
 二人家の中で大暴れ
二人家の中で大暴れ
 公園に連れて行きました
公園に連れて行きました
(おじいさんとおばあさんを作ったのは誰?〉。ポーランドのなぞなぞだという。のり・たまみ著『つい話したくなる 世界のなぞなぞ』(文春新書)におそわった◆答えは少し後で。同僚に試すと、わりと正解率が低かった。「ひいおじいさんとひいおばあさん」。ま、それも間違いではないものの、正解は「孫」とされる。なるほどオギャアと生まれる赤ちゃんが祖父母を作る。そんなわけらしい◆孫の誕生を待ち望む人でなくても、落胆を覚えた方は少なくないかもしれない。まもなく終わる2017年の人口動態調査である◆厚生労働省の発表によれば、今年国内で生まれた日本人の赤ちゃんは94万1000人(推計)で、100万人を2年連続で下回った。統計の残る1899年以降で最少を更新するという。出生が死亡を下回る自然減も拡大し、初めて40万人を超えた◆子育て支援の充実が一段と・・・と書こうとして、パソコンを打つ手が止まる。何度繰返したことだろう。国をあげて根気強く取り組むべき課題が来年も横たわる。少しでも多く、産声に目を細めるおじいさん、おばあさんに増えてもらおう。
読売新聞 【編集手帳】 2017・12・30
●のり・たまみ
世界中の「へんなもの」をこよなく愛する夫婦合体ライター。日本のみならず、世界中の政治の仕組みや法律などをこよなく偏愛している。主な著書に『へんなほうりつ』(扶桑社)、『日本一へんな地図帳』(白夜書房)、『へんな国会』(ポプラ社)、『へんな婚活』(北辰堂出版)などがある。
テレビのニュースの在り方に疑問を抱きます。
気分直しにこんな記事が目に留まりました。・・・少子化問題。
 二人家の中で大暴れ
二人家の中で大暴れ 公園に連れて行きました
公園に連れて行きました(おじいさんとおばあさんを作ったのは誰?〉。ポーランドのなぞなぞだという。のり・たまみ著『つい話したくなる 世界のなぞなぞ』(文春新書)におそわった◆答えは少し後で。同僚に試すと、わりと正解率が低かった。「ひいおじいさんとひいおばあさん」。ま、それも間違いではないものの、正解は「孫」とされる。なるほどオギャアと生まれる赤ちゃんが祖父母を作る。そんなわけらしい◆孫の誕生を待ち望む人でなくても、落胆を覚えた方は少なくないかもしれない。まもなく終わる2017年の人口動態調査である◆厚生労働省の発表によれば、今年国内で生まれた日本人の赤ちゃんは94万1000人(推計)で、100万人を2年連続で下回った。統計の残る1899年以降で最少を更新するという。出生が死亡を下回る自然減も拡大し、初めて40万人を超えた◆子育て支援の充実が一段と・・・と書こうとして、パソコンを打つ手が止まる。何度繰返したことだろう。国をあげて根気強く取り組むべき課題が来年も横たわる。少しでも多く、産声に目を細めるおじいさん、おばあさんに増えてもらおう。
読売新聞 【編集手帳】 2017・12・30
●のり・たまみ
世界中の「へんなもの」をこよなく愛する夫婦合体ライター。日本のみならず、世界中の政治の仕組みや法律などをこよなく偏愛している。主な著書に『へんなほうりつ』(扶桑社)、『日本一へんな地図帳』(白夜書房)、『へんな国会』(ポプラ社)、『へんな婚活』(北辰堂出版)などがある。
作日(12/28)は官庁御用納め、今年も残りわずかである。
新聞の記事もここにきて、今年の流行語や新語、造語などの言葉に関係するものが多くなっています。
今日も日本語のはなしですが一瞬ドキッとするような話です。
昨日の読売新聞【編集手帳】でパッと目に付いた新聞記事のこの文章「先生ちょっとマクっていいですか?」
ここで使われている言葉をそのまま理解できる人たちはごく一部の人達だとおもいます。
一般的には「まくる」とはおおっているものを、はいだり、上げたりして下の物をあらわすと云う意味で使われます。
先生がスカートを一瞬押さえるのも無理はありません。
説明を読み終わらないとスカートをマクる行為だけが頭に残って本来の意味は通じません。
若い人達だけに通じる日本語かも知れませんね。

大学教員の女性が朝の出勤時、駅であった男子学生と歩いていると、学生がふいに言った。「先生ちょっとマクっていいですか?」。教員はスカートを押さえた◆言語学者の窪園晴夫さんの近著『通じない日本語』(平凡社新書)に、実際にあった出来事として紹介されている。この場合の【まくる】はむろんスカートには関係なく、ハンバーガー店に立ち寄ることを言う◆「る」で終わる新語といえば、昨年の「神ってる」が浮かぶが、今年、女子中学生を中心に流行したのは【ストーリーってる】だという。インスタグラムに「ストーリー」と呼ばれる機能があり、動詞化したようである◆これを使うと、24時間過ぎればアップした画像が自動消去される。いわば「消える日記」だろうか。毎日の物語がすぐに消えて、すぐにまた始まる。刹那的だが、引きずるものがなくて、そこがいいのかもしれない◆じつは最近、若者言葉の変化を聞いてもあまり驚かない。というのも、江戸時代の流行語を知ったことがある。【茶づる】。お茶漬けを食べることで、広辞苑にも載っている。昔からの「る」だったんですね。
 窪園晴夫
窪園晴夫
●窪薗 晴夫(くぼぞの はるお、1957年3月17日~)は、日本の言語学者。専門は音声学・音韻論。国立国語研究所教授。 英語への興味から研究生活を始めたものの、イギリス留学時代の「母語である日本語のことをほとんど知らない」という体験によって、日本語への探求へと研究対象を変えてゆくこととなる。近年は母方言である鹿児島方言の調査や借用語の促音挿入問題を中心に、言語接触による言語変化についての研究を行っている。
●経歴
鹿児島県薩摩川内市出身。
1975年、鹿児島県立川内高等学校を卒業。
1979年、大阪外国語大学(現在の大阪大学外国語学部)英語学科を卒業。
1981年、名古屋大学大学院文学研究科博士前期課程を修了。
イギリスのエジンバラ大学大学院留学(1983年 - 1986年)の後、南山大学助教授、大阪外国語大学助教授、神戸大学大学院人文学研究科教授を経て、現在は国立国語研究所教授。
2015年4月、日本言語学会会長に就任。
日本学術会議連携会員。
●主な出版物
通じない日本語―世代差・地域差から見る言葉の不思議
窪薗晴夫
平凡社 2017年12月
オノマトペの謎ーピカチュウからモフモフまで
窪薗晴夫 (担当:編者)
岩波書店 2017年5月
The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants
窪薗晴夫 (担当:編者)
Oxford University Press 2017年4月
Mouton Handbook of Japanese Phonetics and Phonology
窪薗晴夫 (担当:編者)
Mouton de Gruyter 2015年2月
日英対照 英語学の基礎
窪薗晴夫 (担当:共著, 範囲:第1章 音韻論)
くろしお出版 2013年11月
新聞の記事もここにきて、今年の流行語や新語、造語などの言葉に関係するものが多くなっています。
今日も日本語のはなしですが一瞬ドキッとするような話です。
昨日の読売新聞【編集手帳】でパッと目に付いた新聞記事のこの文章「先生ちょっとマクっていいですか?」
ここで使われている言葉をそのまま理解できる人たちはごく一部の人達だとおもいます。
一般的には「まくる」とはおおっているものを、はいだり、上げたりして下の物をあらわすと云う意味で使われます。
先生がスカートを一瞬押さえるのも無理はありません。
説明を読み終わらないとスカートをマクる行為だけが頭に残って本来の意味は通じません。
若い人達だけに通じる日本語かも知れませんね。

大学教員の女性が朝の出勤時、駅であった男子学生と歩いていると、学生がふいに言った。「先生ちょっとマクっていいですか?」。教員はスカートを押さえた◆言語学者の窪園晴夫さんの近著『通じない日本語』(平凡社新書)に、実際にあった出来事として紹介されている。この場合の【まくる】はむろんスカートには関係なく、ハンバーガー店に立ち寄ることを言う◆「る」で終わる新語といえば、昨年の「神ってる」が浮かぶが、今年、女子中学生を中心に流行したのは【ストーリーってる】だという。インスタグラムに「ストーリー」と呼ばれる機能があり、動詞化したようである◆これを使うと、24時間過ぎればアップした画像が自動消去される。いわば「消える日記」だろうか。毎日の物語がすぐに消えて、すぐにまた始まる。刹那的だが、引きずるものがなくて、そこがいいのかもしれない◆じつは最近、若者言葉の変化を聞いてもあまり驚かない。というのも、江戸時代の流行語を知ったことがある。【茶づる】。お茶漬けを食べることで、広辞苑にも載っている。昔からの「る」だったんですね。
 窪園晴夫
窪園晴夫●窪薗 晴夫(くぼぞの はるお、1957年3月17日~)は、日本の言語学者。専門は音声学・音韻論。国立国語研究所教授。 英語への興味から研究生活を始めたものの、イギリス留学時代の「母語である日本語のことをほとんど知らない」という体験によって、日本語への探求へと研究対象を変えてゆくこととなる。近年は母方言である鹿児島方言の調査や借用語の促音挿入問題を中心に、言語接触による言語変化についての研究を行っている。
●経歴
鹿児島県薩摩川内市出身。
1975年、鹿児島県立川内高等学校を卒業。
1979年、大阪外国語大学(現在の大阪大学外国語学部)英語学科を卒業。
1981年、名古屋大学大学院文学研究科博士前期課程を修了。
イギリスのエジンバラ大学大学院留学(1983年 - 1986年)の後、南山大学助教授、大阪外国語大学助教授、神戸大学大学院人文学研究科教授を経て、現在は国立国語研究所教授。
2015年4月、日本言語学会会長に就任。
日本学術会議連携会員。
●主な出版物
通じない日本語―世代差・地域差から見る言葉の不思議
窪薗晴夫
平凡社 2017年12月
オノマトペの謎ーピカチュウからモフモフまで
窪薗晴夫 (担当:編者)
岩波書店 2017年5月
The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants
窪薗晴夫 (担当:編者)
Oxford University Press 2017年4月
Mouton Handbook of Japanese Phonetics and Phonology
窪薗晴夫 (担当:編者)
Mouton de Gruyter 2015年2月
日英対照 英語学の基礎
窪薗晴夫 (担当:共著, 範囲:第1章 音韻論)
くろしお出版 2013年11月
日本語って難しいなあとつくづく思い知らされる記事です。
考えて次の記事を読むと頭の中がこんがらかってしまいますがサラッと読み通すとなんでもない事柄です。
日本語を自由に使いこなしている私たちには理解していなくとも理解している様な振りが出来るのもおかしなことですね。


なぜなに日本語 381 読売新聞 12月27日 くらし教育面
奥にないけど奥の手
うまくいかないなあ、そろそろ奥の手を出すか---------めったには使わない。
とっておきの手段を「奥の手」と表します。
といっても、奥の方にもう一本、手が隠れているわけではありません。
もともとは左手のことを言いました。
吾妹子(わぎもこ)は釧(くしろ)にあらなむ左手のわが奥の手に纏(ま)きて去(い)なましを 万葉集に載っている歌で、「奥の手」は「大切な手」の意味で使われています。
「わぎもこ」は、奥さんや恋人を呼ぶ言い方で「くしろ」は腕輪です。
あなたが腕輪だったら、私の大切な左手に巻き付けて行くのになあ、と言った意味でしょうか。
古代日本では、右よりも左を尊んで、左手を神聖な手、大事な手として、「奥の手」と呼んだようです。
太陽の女神・アマテラスオオミカミはイザナギノミコトの左目から生まれていますし、左大臣は右大臣よりも位が上でした。
こんなところにも、右より左を上とする気持ちが表れています。
一方で、「右に出る者はいない」「あの人は社長の右腕だ」など右を上に見る考え方もあります。
低い地位に落とされる「左遷」、事業などがうまくいかなくなる「左前」などは、左がよくない意味で用いられている言葉です。
(関根健一)
考えて次の記事を読むと頭の中がこんがらかってしまいますがサラッと読み通すとなんでもない事柄です。
日本語を自由に使いこなしている私たちには理解していなくとも理解している様な振りが出来るのもおかしなことですね。


なぜなに日本語 381 読売新聞 12月27日 くらし教育面
奥にないけど奥の手
うまくいかないなあ、そろそろ奥の手を出すか---------めったには使わない。
とっておきの手段を「奥の手」と表します。
といっても、奥の方にもう一本、手が隠れているわけではありません。
もともとは左手のことを言いました。
吾妹子(わぎもこ)は釧(くしろ)にあらなむ左手のわが奥の手に纏(ま)きて去(い)なましを 万葉集に載っている歌で、「奥の手」は「大切な手」の意味で使われています。
「わぎもこ」は、奥さんや恋人を呼ぶ言い方で「くしろ」は腕輪です。
あなたが腕輪だったら、私の大切な左手に巻き付けて行くのになあ、と言った意味でしょうか。
古代日本では、右よりも左を尊んで、左手を神聖な手、大事な手として、「奥の手」と呼んだようです。
太陽の女神・アマテラスオオミカミはイザナギノミコトの左目から生まれていますし、左大臣は右大臣よりも位が上でした。
こんなところにも、右より左を上とする気持ちが表れています。
一方で、「右に出る者はいない」「あの人は社長の右腕だ」など右を上に見る考え方もあります。
低い地位に落とされる「左遷」、事業などがうまくいかなくなる「左前」などは、左がよくない意味で用いられている言葉です。
(関根健一)
朝起きしなに「夜間の走行照明はハイビームが基本」?・・とか何とかのニュースが飛び込んで来た。あと一つは「爆弾低気圧」。寝起きの頭の中に気になったのは「ハイビーム」のこと。
この歳になって夜間長く走ることはほとんどありませんが、対向車が上向きで走って来た時などは眩しくてまともに前を見ていられなくて恐ろしい思いをしたことがあります。八代ー人吉間の九州自動車道には距離38.5㎞の間にトンネルが23個もあります。以前はそのトンネルのほとんどが対面通行でライトを挙げて通行する車に出会うと嫌な思いをしたものです。
そんな事もあって今日のニュースの内容には少し首をかしげたくなる思いです。
詳しく調べてみますとライトを下げて走るのが基本と思っている我々が間違っているようです。
-----------------------------------------------------------------------------
道路交通法、第五十二条では、原則的にハイビームを使用し、対向車がいる場合や、前を走る車がいる場合には、運転の妨げにならないように減光するよう定められています。ヘッドライトは、ハイビームこそが通常モードで、ロービームは減光モードということになります。また、逆に減光を怠った場合も違反となります。
街灯がある比較的明るい道路でも、対向車や先行車がいなければ、基本はハイビームが正しいということになります。
・・・と解説されています。

●夜間の運転は、ハイ・ローのライト切り替えを積極的に活用する。
●雨天時は日中であっても点灯し、対向車に自車の存在を知らせる。
●ハイビームを自動的に調整する次世代型ヘッドライトも登場した。
------------------------------------------------------------------------------
■12月27日「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」です。■ 実は12月26日も一粒万倍日でした。
「一粒万倍日:いちりゅうまんばいび」または「いちりゅうまんばいにち」と読み、単に「万倍」ともいいます。
宣明暦時代には「万倍」と記載されていました。また、貞享改暦後は暦注から外されていましたが、新暦普及後には民間の暦に記載されるようになりました。
「一粒の籾(モミ)が、万倍にも実る稲穂になる」という目出度い日で、よろず事始めには良い日とされます。特に、仕事始め、開店、種まき、お金を出すことに良い日とされます。
但し、人に借金したり、物を借りたりすると、後々苦労の種が増えるとされています。借金が万倍では、返済しきれないと考えたのでしょう。

※季節のお便りより
この歳になって夜間長く走ることはほとんどありませんが、対向車が上向きで走って来た時などは眩しくてまともに前を見ていられなくて恐ろしい思いをしたことがあります。八代ー人吉間の九州自動車道には距離38.5㎞の間にトンネルが23個もあります。以前はそのトンネルのほとんどが対面通行でライトを挙げて通行する車に出会うと嫌な思いをしたものです。
そんな事もあって今日のニュースの内容には少し首をかしげたくなる思いです。
詳しく調べてみますとライトを下げて走るのが基本と思っている我々が間違っているようです。
-----------------------------------------------------------------------------
道路交通法、第五十二条では、原則的にハイビームを使用し、対向車がいる場合や、前を走る車がいる場合には、運転の妨げにならないように減光するよう定められています。ヘッドライトは、ハイビームこそが通常モードで、ロービームは減光モードということになります。また、逆に減光を怠った場合も違反となります。
街灯がある比較的明るい道路でも、対向車や先行車がいなければ、基本はハイビームが正しいということになります。
・・・と解説されています。

●夜間の運転は、ハイ・ローのライト切り替えを積極的に活用する。
●雨天時は日中であっても点灯し、対向車に自車の存在を知らせる。
●ハイビームを自動的に調整する次世代型ヘッドライトも登場した。
------------------------------------------------------------------------------
■12月27日「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」です。■ 実は12月26日も一粒万倍日でした。
「一粒万倍日:いちりゅうまんばいび」または「いちりゅうまんばいにち」と読み、単に「万倍」ともいいます。
宣明暦時代には「万倍」と記載されていました。また、貞享改暦後は暦注から外されていましたが、新暦普及後には民間の暦に記載されるようになりました。
「一粒の籾(モミ)が、万倍にも実る稲穂になる」という目出度い日で、よろず事始めには良い日とされます。特に、仕事始め、開店、種まき、お金を出すことに良い日とされます。
但し、人に借金したり、物を借りたりすると、後々苦労の種が増えるとされています。借金が万倍では、返済しきれないと考えたのでしょう。

※季節のお便りより
 花弁が落ちています(サザンカ)
花弁が落ちています(サザンカ) 花は平開しています(サザンカ)葉にギザギザもあります・葉脈の色が黒い
花は平開しています(サザンカ)葉にギザギザもあります・葉脈の色が黒い 花ごと落ちています(ツバキ)葉にギザギザがありません・葉脈の色が白い
花ごと落ちています(ツバキ)葉にギザギザがありません・葉脈の色が白い先日ゴルフに行ったときにゴルフ場に咲いている赤や白の花を見て椿云々の話が出ました。椿にしては時期が少し早いのではないか?今咲いているものは椿じゃなくて山茶花ではないだろうかと説明をしたものの後で自分の発言に確実な自信もなく調べてみることにしました。
サザンカはあちこちの庭に咲いていますがツバキはなかなか今の時期に咲いているものは見かけません。
近所の庭に咲いているサザンカと今の時期に珍しく咲いているツバキをやっと見つけました。
自分の家の椿や侘助はまだ咲きそうにはありません。
侘助もツバキの仲間らしいのですが全く違うものに見えるのでこれは次回の宿題にします。
 我が家のツバキ
我が家のツバキ 我が家の侘助
我が家の侘助山茶花と椿
◎山茶花・・ 秋の終わりから、初冬にかけての寒い時期に、5枚の花弁の花を咲かせる。
冬の季語にされるなど、サザンカには寒さに強いイメージがあるが、開花時期に寒気にさらされると花が落ちること、四国・九州といった暖かい地域が北限である事などから、原種のサザンカは特に寒さに強いわけでは無い。品種改良された園芸種には寒さに強く、真冬でも花を咲かせる品種も少なくない。
◎椿・・花期は冬から春にかけてまたがり、早咲きのものは冬さなかに咲く。
日本原産。日本では本州、四国、九州、南西諸島から、それに国外では朝鮮半島南部と台湾から知られる。本州中北部にはごく近縁のユキツバキがあるが、ツバキは海岸沿いに青森県まで分布し、ユキツバキはより内陸標高の高い位置にあって住み分ける。
椿とサザンカとの見分け方
●花の咲く時期
サザンカ→秋~冬に花を咲かせる。
ツバキ→初春に花を咲かせる
●花の開き方
サザンカ→完全に平開する
ツバキ→完全に平開しない
●花の散り方
サザンカ→ 花びらがバラバラに落ちる
ツバキ→花ごと落ちる
●葉脈の色
サザンカ→黒い
ツバキ→白い
●葉のギザギザ
サザンカ→ギザギザがある
ツバキ→ギザギザがない
●子房に毛があるかないか
サザンカ→毛がある
ツバキ→毛がない







産総研が調査した布田川断層帯北東部のトレンチの一般公開が昨日(12月24日)行われました。
トレンチの場所は県道299号線沿い南阿蘇村の沢津野地区という所でした。
この場所は熊本地震の本震を起こしたとされる布田川断層帯の北東方向にあり、阿蘇山カルデラ内側にあります。
今回のトレンチ調査により約3万年前までの地層を露出させ、地層のずれなどを確認したところ、約7300年前の地層が断層を境に上下に約2メートルずれているのを確認した。
熊本地震で地表面に表れたずれは50センチ程度だったため、約7300年前から、少なくとも今回の地震を含めて3回の地震が起きたと推測されると話されました。
そしてカルデラ内には活断層は無いと認識されていましたが今回のトレンチ調査により布田川断層帯が阿蘇のカルデラ内まで伸びていることが分かったと説明されました。
 中身は絵本にしました
中身は絵本にしました
こどもの詩
サンタさん
出立 みらい
この1年ずっとまっていました
会いたいけど会えません
プレゼント何かな?
クリスマスのよういたいへんだ
かぜひかないようにしてね
(和歌山県紀の川市・池田小2年)
12月24日 読売新聞 くらし面
毎年この日は子供たちが喜ぶ日です。
小さい頃、私たちもこの日を楽しみにしていました。
プレゼントの中身はお正月用の洋服がほとんどでした。
母親が子供たちに用意してくれたものでしたが貧しい生活の中、心身ともに暖かい贈り物でした。
思い出をよみがえらせてくれてありがとう。
縄文時代に三角形の石に描かれた「絵」が発見されました。今まで「絵」の発見というのは、長野県富士見町・唐渡野宮遺跡出土の土器(縄文中期)に描かれた女性像しかありません。
縄文時代の「絵」が珍しいことからいろんな先生方が縄文人の造形意識を知る手掛かりになるのではと思考をめぐらせます。12月20日の読売新聞に関連記事が有りましたので一部紹介します。
---------------------------------------------------------------------------------
小杉康・北海道大教授(考古学)は「置き仮面(マスコイド)のようなもので、祭祀に用いられたのではないか」とする。一方、「縄文人は絵が苦手だった」と考える文化庁美術学芸課の原田昌幸・主任文化財調査官は、この発見に驚きを隠さない。縄文人がほとんど絵を残していないのは、「立体を平面に変換して表現するという発想を持たなかったからでは」と想像するが、だとすれば、存在すること自体がまた不思議だ。
原田氏は、北海道八雲町・栄浜1遺跡で出土した家形石製品や、千葉県成田市・南羽鳥中岫(みなみはとりなかのこぎ)1遺跡出土の写実的な人頭形土製品などを挙げ、「縄文時代にはオーパーツ(場違いな工芸品)とも言うべき、他には例のない奇妙な造形が所々で見つかっている」と指摘。「それが縄文文化の魅力でもある」と語る。果たして、縄文の「人面画」は突然変異なのか、それとも、これを契機に「発見」が相次ぐか。三角形の岩板や土版に注目である。
----------------------------------------------------------------------------------
去年生まれた双子の孫はまだお絵かきは出来ません。
この子達が絵を書き出すのはいつ頃だろう?
上手、下手は別にして絵を描くという行為は普通に考えれば誰でも生まれながらに持っている能力だとだと思っていました。
縄文人にはその能力は持ち合わせていなかったと考えると、絵を描くという能力はいつの時代からか長い年月をかけて先祖から引き継いできた能力なのでしょうか?
【2017年の主な文化財関連ニュース】
1月
● 坂本龍馬が「新国家」という言葉を使って暗殺5日前に書いた手紙発見
2月
●初期の江戸城を描いた最古級の平面図「江戸始図」発見
●東弓削遺跡(大阪府八尾市)道鏡ゆかりの「弓義寺・ゆげでら」の塔跡(8世紀後半)発見
3月
●奈良県明日香村の小山田遺跡(7世紀中頃)、全国最大規模の方墳(1辺約70m)と判明
5月
●沖縄県石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡(しらほさおねたばるどうけついせき)で、国内最古の約2万7千年前の全身骨格を含む、少なくとも19体分の旧石器人骨出土
7月
●「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」(福岡県)が世界遺産登録された。
●八日市地方遺跡(石川県小松市)で、弥生時代中期(約2300年前)の木製の柄が残る最古の槍鉋が出土
8月
●ケカチ遺跡(山梨県甲州市)で平仮名の和歌を刻んだ10世紀中頃の土器
●東弓削遺跡(大阪府八尾市)道鏡が重用した称徳天皇造営の「由義宮」の一部とみられる遺構発見
9月
●戦国城下町の一乗谷朝倉氏遺跡(福井市、15~16世紀)近くで船着き場の遺構
10月
●「上野三碑・こうずけさんぴ」と「朝鮮通信使に関する記録」がユネスコ「世界の記憶」登録。「杉原リスト」は登録されず
11月
●薬師ノ上遺跡(福岡県筑前町)で、1~2世紀頃の、弥生時代初の完全な形の硯(すずり)
●富雄丸山古墳(奈良市、4世紀後半)が国内最大の円墳と判明
●木古内幸連5遺跡(北海道木河内町) 縄文の石、顔料で人の顔 4300年前
●東弓削遺跡(大阪府八尾市)「「由義寺跡」として国史跡指定に
以下、北海道新聞より 11/30
縄文期石製品に「人の顔」 木古内・幸連5遺跡で国内初出土
【木古内】道埋蔵文化財センターは29日、渡島管内木古内町の幸連(こうれん)5遺跡で、人の顔が描かれた縄文時代中期後半(約4300年前)の石製品が出土したと発表した。三角形の板状の石に目や眉などが黒色の顔料で描かれている。縄文時代の顔の絵は極めて珍しく、顔料で描かれ、また石製品に描かれている絵が見つかったのは全国で初めて。同センターは「縄文人の精神文化を探る貴重な資料」としている。
石製品は砂岩で、縄文時代の竪穴住居跡を覆っていた土から10月19日に出土した。一辺約12センチ、厚さ1・4センチ。砥石(といし)で整えたような跡があり、片面に石の形を顔の輪郭に見立てて眉や鼻、右目などが描かれている。顔料の成分は不明。眉と鼻はつながり、目には瞳がある。口の辺りにはひげ、または入れ墨のような表現が見られる。用途は不明だが、縄文人の精神文化に関わる物と考えられている。
有史以前の絵画は原始絵画と呼ばれ、顔料を塗ったもののほか、刻んだ線で粘土などに描く「線刻」などがあるが、縄文時代は原始絵画自体の資料が少ない。
縄文文化に詳しい小林達雄・国学院大名誉教授(考古学)は「写実的な絵は非常に珍しい。顔は命の象徴で、石製品は重要な祭祀(さいし)道具だったのでは」と話す。
幸連5遺跡は、縄文時代前期~後期(5500年前~4千年前)の遺跡。函館江差自動車道の建設に伴って昨年春から発掘が行われ、住居跡や土器などが多数発見されている。



縄文時代の「絵」が珍しいことからいろんな先生方が縄文人の造形意識を知る手掛かりになるのではと思考をめぐらせます。12月20日の読売新聞に関連記事が有りましたので一部紹介します。
---------------------------------------------------------------------------------
小杉康・北海道大教授(考古学)は「置き仮面(マスコイド)のようなもので、祭祀に用いられたのではないか」とする。一方、「縄文人は絵が苦手だった」と考える文化庁美術学芸課の原田昌幸・主任文化財調査官は、この発見に驚きを隠さない。縄文人がほとんど絵を残していないのは、「立体を平面に変換して表現するという発想を持たなかったからでは」と想像するが、だとすれば、存在すること自体がまた不思議だ。
原田氏は、北海道八雲町・栄浜1遺跡で出土した家形石製品や、千葉県成田市・南羽鳥中岫(みなみはとりなかのこぎ)1遺跡出土の写実的な人頭形土製品などを挙げ、「縄文時代にはオーパーツ(場違いな工芸品)とも言うべき、他には例のない奇妙な造形が所々で見つかっている」と指摘。「それが縄文文化の魅力でもある」と語る。果たして、縄文の「人面画」は突然変異なのか、それとも、これを契機に「発見」が相次ぐか。三角形の岩板や土版に注目である。
----------------------------------------------------------------------------------
去年生まれた双子の孫はまだお絵かきは出来ません。
この子達が絵を書き出すのはいつ頃だろう?
上手、下手は別にして絵を描くという行為は普通に考えれば誰でも生まれながらに持っている能力だとだと思っていました。
縄文人にはその能力は持ち合わせていなかったと考えると、絵を描くという能力はいつの時代からか長い年月をかけて先祖から引き継いできた能力なのでしょうか?
【2017年の主な文化財関連ニュース】
1月
● 坂本龍馬が「新国家」という言葉を使って暗殺5日前に書いた手紙発見
2月
●初期の江戸城を描いた最古級の平面図「江戸始図」発見
●東弓削遺跡(大阪府八尾市)道鏡ゆかりの「弓義寺・ゆげでら」の塔跡(8世紀後半)発見
3月
●奈良県明日香村の小山田遺跡(7世紀中頃)、全国最大規模の方墳(1辺約70m)と判明
5月
●沖縄県石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡(しらほさおねたばるどうけついせき)で、国内最古の約2万7千年前の全身骨格を含む、少なくとも19体分の旧石器人骨出土
7月
●「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」(福岡県)が世界遺産登録された。
●八日市地方遺跡(石川県小松市)で、弥生時代中期(約2300年前)の木製の柄が残る最古の槍鉋が出土
8月
●ケカチ遺跡(山梨県甲州市)で平仮名の和歌を刻んだ10世紀中頃の土器
●東弓削遺跡(大阪府八尾市)道鏡が重用した称徳天皇造営の「由義宮」の一部とみられる遺構発見
9月
●戦国城下町の一乗谷朝倉氏遺跡(福井市、15~16世紀)近くで船着き場の遺構
10月
●「上野三碑・こうずけさんぴ」と「朝鮮通信使に関する記録」がユネスコ「世界の記憶」登録。「杉原リスト」は登録されず
11月
●薬師ノ上遺跡(福岡県筑前町)で、1~2世紀頃の、弥生時代初の完全な形の硯(すずり)
●富雄丸山古墳(奈良市、4世紀後半)が国内最大の円墳と判明
●木古内幸連5遺跡(北海道木河内町) 縄文の石、顔料で人の顔 4300年前
●東弓削遺跡(大阪府八尾市)「「由義寺跡」として国史跡指定に
以下、北海道新聞より 11/30
縄文期石製品に「人の顔」 木古内・幸連5遺跡で国内初出土
【木古内】道埋蔵文化財センターは29日、渡島管内木古内町の幸連(こうれん)5遺跡で、人の顔が描かれた縄文時代中期後半(約4300年前)の石製品が出土したと発表した。三角形の板状の石に目や眉などが黒色の顔料で描かれている。縄文時代の顔の絵は極めて珍しく、顔料で描かれ、また石製品に描かれている絵が見つかったのは全国で初めて。同センターは「縄文人の精神文化を探る貴重な資料」としている。
石製品は砂岩で、縄文時代の竪穴住居跡を覆っていた土から10月19日に出土した。一辺約12センチ、厚さ1・4センチ。砥石(といし)で整えたような跡があり、片面に石の形を顔の輪郭に見立てて眉や鼻、右目などが描かれている。顔料の成分は不明。眉と鼻はつながり、目には瞳がある。口の辺りにはひげ、または入れ墨のような表現が見られる。用途は不明だが、縄文人の精神文化に関わる物と考えられている。
有史以前の絵画は原始絵画と呼ばれ、顔料を塗ったもののほか、刻んだ線で粘土などに描く「線刻」などがあるが、縄文時代は原始絵画自体の資料が少ない。
縄文文化に詳しい小林達雄・国学院大名誉教授(考古学)は「写実的な絵は非常に珍しい。顔は命の象徴で、石製品は重要な祭祀(さいし)道具だったのでは」と話す。
幸連5遺跡は、縄文時代前期~後期(5500年前~4千年前)の遺跡。函館江差自動車道の建設に伴って昨年春から発掘が行われ、住居跡や土器などが多数発見されている。



今日(12月22日)は冬至です。
二十四節気のひとつで、北半球では太陽が1年で最も低い位置にきて、夜が一番長くなる日です。
夏至の日と比べると、北海道の根室で約6時間半、東京で約4時間40分もの差があるのです。
また、冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力が甦ってくることから、太陽が生まれ変わる日ととらえ、古くから世界各地で冬至の祝祭が盛大に行われていました。太陰太陽暦(いわゆる旧暦)では冬至が暦を計算する上での起点となります。

一陽来復
冬至の翌日から日が延びるため、中国や日本では、この日は陰の極みで、翌日から再び陽にかえると考えられてきました。それを「一陽来復」といい、この日を境に運が向くとされています。つまり、みんなが上昇運に転じる日なのです!
冬至がゆとかぼちゃ
冬至に食べるものとして親しまれているのが、冬至がゆとかぼちゃです。冬至がゆは小豆を入れたおかゆのことで、小豆の赤が太陽を意味する魔除けの色で、冬至に食べて厄祓いをします。かぼちゃは栄養豊富で長期保存がきくことから、冬の栄養補給になり、冬至に食べると風邪や中風(脳血管疾患)にならないといわれています。

小豆粥
小正月や冬至に小豆粥を食べ、無病息災を祈る風習があります。小豆のように赤い色の食べものは邪気を払うと考えられていますから、小豆粥を食べて厄払いしてはいかがでしょう。
市販のゆで小豆缶を使うと簡単に作れます。
運盛り
冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめるといわれています。にんじん、だいこん、れんこん、うどん、ぎんなん、きんかん......など。「ん」のつくものを運盛り といって縁起をかついでいたのです。かぼちゃは、なんきん! 運盛りは縁起かつぎだけでなく、栄養をつけて寒い冬を乗りきるための知恵でもあり、土用の丑の日に「う」のつくものを食べて夏を乗りきるのに似ていますね。
また、「いろはにほへと」が「ん」で終わることから、「ん」には一陽来復の願いが込められているのです。
柚子湯
「一陽来復」の運を呼びこむ前に、厄払いするための禊(みそぎ)として身を清めました。冬が旬の柚子は香りも強く、強い香りのもとには邪気がおこらないという考えもありました。端午の節供の菖蒲湯も同じです。
また、柚子(ゆず)=「融通」がきく、冬至=「湯治」に通じて縁起もよいため、冬至には柚子となりました。
もちろん、柚子湯には血行を促進して冷え性を緩和したり、体を温めて風邪を予防したり、果皮に含まれるクエン酸やビタミンCによる美肌効果があります。
さらに、芳香によるリラックス効果もありますから、元気に冬を越すためにも大いに役立ちます。

くらし歳時記より
二十四節気のひとつで、北半球では太陽が1年で最も低い位置にきて、夜が一番長くなる日です。
夏至の日と比べると、北海道の根室で約6時間半、東京で約4時間40分もの差があるのです。
また、冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力が甦ってくることから、太陽が生まれ変わる日ととらえ、古くから世界各地で冬至の祝祭が盛大に行われていました。太陰太陽暦(いわゆる旧暦)では冬至が暦を計算する上での起点となります。

一陽来復
冬至の翌日から日が延びるため、中国や日本では、この日は陰の極みで、翌日から再び陽にかえると考えられてきました。それを「一陽来復」といい、この日を境に運が向くとされています。つまり、みんなが上昇運に転じる日なのです!
冬至がゆとかぼちゃ
冬至に食べるものとして親しまれているのが、冬至がゆとかぼちゃです。冬至がゆは小豆を入れたおかゆのことで、小豆の赤が太陽を意味する魔除けの色で、冬至に食べて厄祓いをします。かぼちゃは栄養豊富で長期保存がきくことから、冬の栄養補給になり、冬至に食べると風邪や中風(脳血管疾患)にならないといわれています。

小豆粥
小正月や冬至に小豆粥を食べ、無病息災を祈る風習があります。小豆のように赤い色の食べものは邪気を払うと考えられていますから、小豆粥を食べて厄払いしてはいかがでしょう。
市販のゆで小豆缶を使うと簡単に作れます。
運盛り
冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめるといわれています。にんじん、だいこん、れんこん、うどん、ぎんなん、きんかん......など。「ん」のつくものを運盛り といって縁起をかついでいたのです。かぼちゃは、なんきん! 運盛りは縁起かつぎだけでなく、栄養をつけて寒い冬を乗りきるための知恵でもあり、土用の丑の日に「う」のつくものを食べて夏を乗りきるのに似ていますね。
また、「いろはにほへと」が「ん」で終わることから、「ん」には一陽来復の願いが込められているのです。
柚子湯
「一陽来復」の運を呼びこむ前に、厄払いするための禊(みそぎ)として身を清めました。冬が旬の柚子は香りも強く、強い香りのもとには邪気がおこらないという考えもありました。端午の節供の菖蒲湯も同じです。
また、柚子(ゆず)=「融通」がきく、冬至=「湯治」に通じて縁起もよいため、冬至には柚子となりました。
もちろん、柚子湯には血行を促進して冷え性を緩和したり、体を温めて風邪を予防したり、果皮に含まれるクエン酸やビタミンCによる美肌効果があります。
さらに、芳香によるリラックス効果もありますから、元気に冬を越すためにも大いに役立ちます。

くらし歳時記より
12月21日「納めの大師」です。季節のお便りで知りました。恥ずかしい話ですが宗教にはとんと縁がなく自分の親父が浄土宗から天台宗、、真言宗、最後は曹洞宗といろいろ宗派替えを行ったものですから幼い頃には何も分からないまま比叡山や高野山へ親父についてお参りに付いて行ったものです。その頃は大阪に住んでいたものですから近くの有名なお寺さんには学校からも行きましたし回数が一番多かったのは高野山が多かったような気がします。そんな事もあり、弘法大師、空海、真言宗、密教という言葉だけは頭に残っていますが「納めの大師」というのは記憶にはありません。今日がその日ということで弘法大師さんの事を少し調べてみました。
■12月21日「納めの大師」です。■
空海を信仰する大師信仰は、高野山や四国八十八か所札所巡り、各地にある厄除け大師など、現代でも社会に広まっています。
「納めの大師」とは、その年の最後の弘法大師空海の縁日を指します。終い弘法・果の大師などともいいます。
弘法大師は、承和2年(835)3月21日に入寂したので、真言宗の各寺院では3月21日に御影供養を行い、毎月21日を縁日としています。その年の最後の縁日が12月21日であるところから「終い大師」「納めの大師」と呼ばれて参拝者で賑わいます。
京都「東寺」の終い弘法は、北野天満宮の終い天神(12月25日)と並び称され、大変賑わいます。関東では「西新井大師」や「厄除け川崎大師」が有名で、前夜からたくさんの参拝者で賑わいます。
 空海の肖像
空海の肖像
空海
空海(くうかい、宝亀5年(774年) - 承和2年3月21日(835年4月22日))は、平安時代初期の僧。弘法大師(こうぼうだいし)の諡号(921年、醍醐天皇による)で知られる真言宗の開祖である。俗名(幼名)は佐伯 眞魚(さえき の まお)。日本天台宗の開祖最澄(伝教大師)と共に、日本仏教の大勢が、今日称される奈良仏教から平安仏教へと、転換していく流れの劈頭(へきとう)に位置し、中国より真言密教をもたらした。能書家としても知られ、嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆のひとりに数えられている。
※劈頭 三省堂 大辞林 難読語 読みは・へきとう
〔「劈」はひきさく意〕
物事の一番はじめ。まっさき。冒頭。 「会議の-から意見が割れる」
※諡号 読み しごう
貴人・僧侶などに、その死後、生前の行いを尊んで贈る名。贈り名。
■12月21日「納めの大師」です。■
空海を信仰する大師信仰は、高野山や四国八十八か所札所巡り、各地にある厄除け大師など、現代でも社会に広まっています。
「納めの大師」とは、その年の最後の弘法大師空海の縁日を指します。終い弘法・果の大師などともいいます。
弘法大師は、承和2年(835)3月21日に入寂したので、真言宗の各寺院では3月21日に御影供養を行い、毎月21日を縁日としています。その年の最後の縁日が12月21日であるところから「終い大師」「納めの大師」と呼ばれて参拝者で賑わいます。
京都「東寺」の終い弘法は、北野天満宮の終い天神(12月25日)と並び称され、大変賑わいます。関東では「西新井大師」や「厄除け川崎大師」が有名で、前夜からたくさんの参拝者で賑わいます。
 空海の肖像
空海の肖像空海
空海(くうかい、宝亀5年(774年) - 承和2年3月21日(835年4月22日))は、平安時代初期の僧。弘法大師(こうぼうだいし)の諡号(921年、醍醐天皇による)で知られる真言宗の開祖である。俗名(幼名)は佐伯 眞魚(さえき の まお)。日本天台宗の開祖最澄(伝教大師)と共に、日本仏教の大勢が、今日称される奈良仏教から平安仏教へと、転換していく流れの劈頭(へきとう)に位置し、中国より真言密教をもたらした。能書家としても知られ、嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆のひとりに数えられている。
※劈頭 三省堂 大辞林 難読語 読みは・へきとう
〔「劈」はひきさく意〕
物事の一番はじめ。まっさき。冒頭。 「会議の-から意見が割れる」
※諡号 読み しごう
貴人・僧侶などに、その死後、生前の行いを尊んで贈る名。贈り名。
1925年の今日(12月20日)は大森貝塚を最初に発見したアメリカ人のモースが87歳で亡くなった日であることを今日は何の日カレンダーで知りました。
そして大森貝塚が日本の考古学を芽生えさせるきっかけになった事を大田区のブログから初めて知りました。
考古学には興味はあっても考古学そのものの歴史も知らないなんて自分のことながら恥ずかしい思いがします。
大田区のブログ「大田区の史跡と歴史」を紹介します。
ー日本考古学の夜明け、モースが発見した大森貝塚ー
●大森貝塚の発見…明治10年(1877)
アメリカ人、エドワード・シルベスター・モースが貝塚を発見したのは、明治10年(1877)、品川から横浜までの鉄道開通5年後のことでした。横浜から新橋に向かう途中の大森駅付近で、写真のように鉄道建設のため削られた斜面に、貝が大量に露出しているのを見ました。モースは、それが貝塚であることを直感しました。多くの日本人が同じ風景を見ていましたが、誰も古代人が捨てた貝の堆積した跡だとは知りませんでした。
●モースが行った最初の発掘の様子
明治10年10月の記述から、『 今日、ドクターマレー、彼の通訳及び私は人夫2人をつれて大森の貝塚へ行った。人夫は採取した物を何でも持って帰らせる為に連れて行ったのである。人夫達はつるはし耨(くさぎ 鍬のようなものか)で、我々は移植で掘り始めた。(中略)我々がそこを堀回した形跡は何ひとつ無くなった。大雨が一雨降った後では、ここがどんな風になったかは知る由もない。私は幸運にも堆積の上部で完全な甕(かめ)二つと、粗末な骨の道具一つとを発見し、また角製の道具三つと骨製のもの一つを見つけた』。(モース「日本その日その日」東洋文庫 平凡社刊から)
● モースが最初に掘った場所がどこか明らかでない、大田区と品川区が競って記念碑を建てており、どちらも国指定史跡となっている。また国指定の史跡は記念碑の建っているわずか28.57・と言う狭さである、これは発掘場所が不明なためである。品川区では区立歴史館建設の時に、現在記念碑の建っているを場所を国鉄より買い取り調査を行った。
●大森貝塚の発掘品について……明治12年(1879)本格的発掘調査始まる
発掘された遺物は、縄文式後期の土器や土偶、石斧、石鏃、骨角器など、動物の骨はサル、シカ、犬、鯨を含む大量の貝殻でした。モースは発見された土器に「コード・マーク」と名づけました。土器の表面にナワ目模様が付いていたのです。驚くことに人骨も発見され、その骨が削られたりしていたことから、「食人」の風習があったのではないかと推測されました、未だ結論は出ていません。
●大森貝塚の発掘場所は「品川区大井」であった。本当は大井貝塚となるはずだったが、モース達が大森駅に降りて発掘に向かったため、駅名をとって「大森貝塚」となった。貝塚公園は正確に言うならば品川区に属すようです。大田区の石碑(昭和5年4月)はNTTデータービルの間を入った線路ぎわにあります。昭和29年国指定の遺跡に認定された。参考・『東京都品川区 大森貝塚』編集・発行 品川区教育委員会 昭和60年発行
●貝塚公園(品川区)から東海道線を見る、発掘当時の海側は平坦で、東京湾の海岸線まで見えた。貝塚を作った人たちは、縄文時代後期、紀元前650年頃と推定されています。
■埴輪形の公園トイレ(品川区の公園)
埴輪の形の公園トイレ、工夫があっておもしろい。公園はやや小高い丘にあり、東海道線越しに見える蒲田方向は低い平らな土地である。汽車の開通当時は東京湾の海が広がっていた。→
■大田区の遺跡・貝塚
大田区は武蔵野台地の東端にあたり、縄文時代の大森貝塚は海に面したはずれにあたります。台地の湧水が豊富で、関東ローム層の軟らかい土のため洞窟や集落を作りやすかった、そのために縄文弥生時代から人が住んでいました。区全体に遺跡が数多くあります。しかし鉄道が開通すると同時に、今と同じように宅地開発が行われ、遺跡が充分な調査を行われないまま工事され、古代の遺跡は破壊されました。特に明治の文学者「江見水蔭」が実名で貝塚の場所を紹介したため、中馬込の遺跡(馬籠貝塚)は調査がされないまま、素人の発掘者のため荒れ果ててしまいました。畑の表面近くに土器などが埋まっていたため、手軽に掘ることが出来た事が要因でした。

エドワード・シルヴェスター・モース(Edward Sylvester Morse、1838年6月18日 - 1925年12月20日)は、アメリカの動物学者。標本採集に来日し、請われて東京大学のお雇い教授を2年務め、大学の社会的・国際的姿勢の確立に尽力した。大森貝塚を発掘し、日本の人類学、考古学の基礎をつくった[1]。日本に初めて、ダーウィンの進化論を体系的に紹介した。名字の「モース」は「モールス」とも書かれる。
●生誕
1838年6月18日
アメリカ合衆国 メイン州 ポートランド
●死没
1925年12月20日
アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 セイラム
死因・脳溢血
●研究分野
動物学、オリエンタリズム
●研究機関
ハーバード大学
ピーボディー科学アカデミー
ボウディン大学
東京帝国大学
●主な業績
大森貝塚を発掘
日本で初めて進化論を体系的に紹介
●影響を受けた人物
ルイ・アガシー ダーウィン
-----------------------------------------------------------------------------
大森貝塚
東京都大田区山王・品川区大井にある貝塚遺跡。JR京浜東北線大森駅から大井町駅にいたる線路に面する地域に所在する。1877年(明治10)、アメリカの碩学(せきがく)、エドワード・モースが日本を訪れた際、横浜から新橋へ向かう途中の車窓から発見した。同年、わが国における最初の学術的な発掘が行われ、その後、英文と邦文でその結果が発表された。1955年(昭和30)に国の史跡に指定され、1986年(昭和61)には追加指定を受けているが、出土品は多種類の貝殻をはじめ、土器、土偶、石斧(せきふ)、石鏃(せきぞく)、人骨片、鹿やクジラの骨など多岐にわたり、これらは東京大学に保存され、国の重要文化財の指定を受けた。それまでの日本には考古学が存在せず、この発掘調査は日本の近代的考古学の出発点となる記念すべき出来事であり、大森駅のホームにある碑には「日本考古学発祥の地」と刻まれている。品川区立品川歴史館に関係資料を展示。JR京浜東北線大森駅から徒歩すぐ。

考古学発祥の地大森貝塚。場所は品川区太井町
大森貝塚の発見された場所は現在、遺跡庭園として整備されています。しかし縄文遺跡のモニュメントらしいものが少しあるだけで、遺跡が見れるわけではありませんでした。

歴史の教科書に出てくる有名な碑
JR京浜東北線が迫っています。モース博士達が発掘した場所は太井町でしたが、モース博士の論文には発見した正確な場所には触れておらず、たぶん博士達が発掘作業で乗り降りした駅が大森駅だったので「大森貝塚」と命名したものだと思います。

日本考古学の祖モース博士の像
モース博士は東京大学の教員に雇われ来日しました。横浜から東京へ向かう列車の窓から貝塚を発見したのは有名な話ですね。
彼は東京大学に赴任後、学生を引き連れ貝塚の発掘を行いました。このとき貝塚だけではなく人や動物の骨、縄文土器を発見したのです。日本の考古学の夜明けです。モース博士が「大森貝塚」を発見した当時の年齢は30代ですが、モース博士の晩年のイメージで作られたブロンズ像は見る人に間違った印象を与えるなと感じました。
東京写真紀行より一部転載
そして大森貝塚が日本の考古学を芽生えさせるきっかけになった事を大田区のブログから初めて知りました。
考古学には興味はあっても考古学そのものの歴史も知らないなんて自分のことながら恥ずかしい思いがします。
大田区のブログ「大田区の史跡と歴史」を紹介します。
ー日本考古学の夜明け、モースが発見した大森貝塚ー
●大森貝塚の発見…明治10年(1877)
アメリカ人、エドワード・シルベスター・モースが貝塚を発見したのは、明治10年(1877)、品川から横浜までの鉄道開通5年後のことでした。横浜から新橋に向かう途中の大森駅付近で、写真のように鉄道建設のため削られた斜面に、貝が大量に露出しているのを見ました。モースは、それが貝塚であることを直感しました。多くの日本人が同じ風景を見ていましたが、誰も古代人が捨てた貝の堆積した跡だとは知りませんでした。
●モースが行った最初の発掘の様子
明治10年10月の記述から、『 今日、ドクターマレー、彼の通訳及び私は人夫2人をつれて大森の貝塚へ行った。人夫は採取した物を何でも持って帰らせる為に連れて行ったのである。人夫達はつるはし耨(くさぎ 鍬のようなものか)で、我々は移植で掘り始めた。(中略)我々がそこを堀回した形跡は何ひとつ無くなった。大雨が一雨降った後では、ここがどんな風になったかは知る由もない。私は幸運にも堆積の上部で完全な甕(かめ)二つと、粗末な骨の道具一つとを発見し、また角製の道具三つと骨製のもの一つを見つけた』。(モース「日本その日その日」東洋文庫 平凡社刊から)
● モースが最初に掘った場所がどこか明らかでない、大田区と品川区が競って記念碑を建てており、どちらも国指定史跡となっている。また国指定の史跡は記念碑の建っているわずか28.57・と言う狭さである、これは発掘場所が不明なためである。品川区では区立歴史館建設の時に、現在記念碑の建っているを場所を国鉄より買い取り調査を行った。
●大森貝塚の発掘品について……明治12年(1879)本格的発掘調査始まる
発掘された遺物は、縄文式後期の土器や土偶、石斧、石鏃、骨角器など、動物の骨はサル、シカ、犬、鯨を含む大量の貝殻でした。モースは発見された土器に「コード・マーク」と名づけました。土器の表面にナワ目模様が付いていたのです。驚くことに人骨も発見され、その骨が削られたりしていたことから、「食人」の風習があったのではないかと推測されました、未だ結論は出ていません。
●大森貝塚の発掘場所は「品川区大井」であった。本当は大井貝塚となるはずだったが、モース達が大森駅に降りて発掘に向かったため、駅名をとって「大森貝塚」となった。貝塚公園は正確に言うならば品川区に属すようです。大田区の石碑(昭和5年4月)はNTTデータービルの間を入った線路ぎわにあります。昭和29年国指定の遺跡に認定された。参考・『東京都品川区 大森貝塚』編集・発行 品川区教育委員会 昭和60年発行
●貝塚公園(品川区)から東海道線を見る、発掘当時の海側は平坦で、東京湾の海岸線まで見えた。貝塚を作った人たちは、縄文時代後期、紀元前650年頃と推定されています。
■埴輪形の公園トイレ(品川区の公園)
埴輪の形の公園トイレ、工夫があっておもしろい。公園はやや小高い丘にあり、東海道線越しに見える蒲田方向は低い平らな土地である。汽車の開通当時は東京湾の海が広がっていた。→
■大田区の遺跡・貝塚
大田区は武蔵野台地の東端にあたり、縄文時代の大森貝塚は海に面したはずれにあたります。台地の湧水が豊富で、関東ローム層の軟らかい土のため洞窟や集落を作りやすかった、そのために縄文弥生時代から人が住んでいました。区全体に遺跡が数多くあります。しかし鉄道が開通すると同時に、今と同じように宅地開発が行われ、遺跡が充分な調査を行われないまま工事され、古代の遺跡は破壊されました。特に明治の文学者「江見水蔭」が実名で貝塚の場所を紹介したため、中馬込の遺跡(馬籠貝塚)は調査がされないまま、素人の発掘者のため荒れ果ててしまいました。畑の表面近くに土器などが埋まっていたため、手軽に掘ることが出来た事が要因でした。

エドワード・シルヴェスター・モース(Edward Sylvester Morse、1838年6月18日 - 1925年12月20日)は、アメリカの動物学者。標本採集に来日し、請われて東京大学のお雇い教授を2年務め、大学の社会的・国際的姿勢の確立に尽力した。大森貝塚を発掘し、日本の人類学、考古学の基礎をつくった[1]。日本に初めて、ダーウィンの進化論を体系的に紹介した。名字の「モース」は「モールス」とも書かれる。
●生誕
1838年6月18日
アメリカ合衆国 メイン州 ポートランド
●死没
1925年12月20日
アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 セイラム
死因・脳溢血
●研究分野
動物学、オリエンタリズム
●研究機関
ハーバード大学
ピーボディー科学アカデミー
ボウディン大学
東京帝国大学
●主な業績
大森貝塚を発掘
日本で初めて進化論を体系的に紹介
●影響を受けた人物
ルイ・アガシー ダーウィン
-----------------------------------------------------------------------------
大森貝塚
東京都大田区山王・品川区大井にある貝塚遺跡。JR京浜東北線大森駅から大井町駅にいたる線路に面する地域に所在する。1877年(明治10)、アメリカの碩学(せきがく)、エドワード・モースが日本を訪れた際、横浜から新橋へ向かう途中の車窓から発見した。同年、わが国における最初の学術的な発掘が行われ、その後、英文と邦文でその結果が発表された。1955年(昭和30)に国の史跡に指定され、1986年(昭和61)には追加指定を受けているが、出土品は多種類の貝殻をはじめ、土器、土偶、石斧(せきふ)、石鏃(せきぞく)、人骨片、鹿やクジラの骨など多岐にわたり、これらは東京大学に保存され、国の重要文化財の指定を受けた。それまでの日本には考古学が存在せず、この発掘調査は日本の近代的考古学の出発点となる記念すべき出来事であり、大森駅のホームにある碑には「日本考古学発祥の地」と刻まれている。品川区立品川歴史館に関係資料を展示。JR京浜東北線大森駅から徒歩すぐ。

考古学発祥の地大森貝塚。場所は品川区太井町
大森貝塚の発見された場所は現在、遺跡庭園として整備されています。しかし縄文遺跡のモニュメントらしいものが少しあるだけで、遺跡が見れるわけではありませんでした。

歴史の教科書に出てくる有名な碑
JR京浜東北線が迫っています。モース博士達が発掘した場所は太井町でしたが、モース博士の論文には発見した正確な場所には触れておらず、たぶん博士達が発掘作業で乗り降りした駅が大森駅だったので「大森貝塚」と命名したものだと思います。

日本考古学の祖モース博士の像
モース博士は東京大学の教員に雇われ来日しました。横浜から東京へ向かう列車の窓から貝塚を発見したのは有名な話ですね。
彼は東京大学に赴任後、学生を引き連れ貝塚の発掘を行いました。このとき貝塚だけではなく人や動物の骨、縄文土器を発見したのです。日本の考古学の夜明けです。モース博士が「大森貝塚」を発見した当時の年齢は30代ですが、モース博士の晩年のイメージで作られたブロンズ像は見る人に間違った印象を与えるなと感じました。
東京写真紀行より一部転載
Posted by マー君 at
10:27
│Comments(0)
今日の予定は午前中、成人病(糖尿病・高血圧)治療のため病院通い、午後からは熊本に災害対策についての講演を聞きに行く予定だったのだが、医者に行くために医療手帳を準備していると眼科の手帳が目につき中を調べてみると12月5日に診療を受ける予定になっていたのに気がつき午後の予定を変更、午前も午後も病院につかることになりました。
いつもの光景だがどこの病院も何と年寄りの多いこと。
血糖値のコントロールがこの時期になるとどうしても思うようにはいきません。糖尿病治療は食事と運動が基本と言われていますが食後の血糖コントロールがこう寒くては散歩に行くのもおっくうになって、今日もお医者さんからは「食べちゃー寝、食べちゃー寝の生活は駄目ですよ。」て駄目押しを頂いた。数値が改善しているかそれとも悪くなっているか、病院に行かないと分からない。
とんでもない病気になったものだと今になってつくづく思う。
糖尿病と言う病気は一度なってしまえば治らない病気だそうです。
今以上に悪くならないように維持し続けるための治療だそうです。
医者は治療の手伝いをするだけ治療をするのは患者本人。
眼科も糖尿病関連で行っています。
人間って妙なもので苦しい目に遭って初めて過去の自分を反省します。人並か人並以下か・・何十人ものお客様待ちの間、頭に浮かぶのは反省ばかり「馬鹿だなー」と自責の念に押しつぶされそうになります。

縄文時代の人達にはなかった病気でしょうか?・・・現代病とも言われるので。
いつもの光景だがどこの病院も何と年寄りの多いこと。
血糖値のコントロールがこの時期になるとどうしても思うようにはいきません。糖尿病治療は食事と運動が基本と言われていますが食後の血糖コントロールがこう寒くては散歩に行くのもおっくうになって、今日もお医者さんからは「食べちゃー寝、食べちゃー寝の生活は駄目ですよ。」て駄目押しを頂いた。数値が改善しているかそれとも悪くなっているか、病院に行かないと分からない。
とんでもない病気になったものだと今になってつくづく思う。
糖尿病と言う病気は一度なってしまえば治らない病気だそうです。
今以上に悪くならないように維持し続けるための治療だそうです。
医者は治療の手伝いをするだけ治療をするのは患者本人。
眼科も糖尿病関連で行っています。
人間って妙なもので苦しい目に遭って初めて過去の自分を反省します。人並か人並以下か・・何十人ものお客様待ちの間、頭に浮かぶのは反省ばかり「馬鹿だなー」と自責の念に押しつぶされそうになります。


縄文時代の人達にはなかった病気でしょうか?・・・現代病とも言われるので。


2人いれば喧嘩ばかりしていますが、時々一人だけお守をしてほしいと連れてくるときがあります。もう一人が病気で医者がよいする時とか、母親の方に用事がある時など、・・こればかりは致し方ありません。そして気がついた事は一人の方が人の言うことはよく聞き分けます。まだ1歳半ですが、人の言うことは理解しているようです。話す方はまだ片言のようです。孫の守って疲れるけど色々成長について気づかされる事もあり私達の励みにもなります。ありがとう。また来てください。

 八代の「年の瀬」2景
八代の「年の瀬」2景今年も残すところあと半月、この歳になると年末の慌ただしさや忙しさなどよりも、急に寒くなった日々をどう過ごそうかとの心配の方が先に立ちます。
「年の瀬」の意味を調べてみると年の暮れ。年末。歳末。「 -も押し詰まった」。「瀬」とは、川の流れが速くなっている所を指し、歳末の慌しさや年越しの大変さを喩えた表現とされる。 一年の終わりの頃。などが出てきます。このことから年の暮れを表す意味であることは分かりますが、実際にいつ頃から何時までを表す言葉なのかと問われるとなかなかいい答えが浮かびません。
色々調べてみますと明確には決まっていなくて12月中旬以降を指す言葉という回答が有りましたが、使い方として12月に入った頃から「年の瀬に入り・・」「年の瀬の時期に・・」などと使われ、12月15日頃からは「年の瀬も押し迫って・・」「年の瀬も押し詰まって・・」という風に使われるので「年の瀬」という言葉だけでは正確に時期を表す言葉ではないようですね。もともとこの言葉の語源には慌ただしく押し詰まっているとか鬼気迫る様子を現す意味が込められていることから後につく言葉によって時期的な意味は異なってくるようです。
この時期になると毎年、その年の世相を反映した言葉として住友生命保険が師走恒例「創作四字熟語」の入選作を発表します。
今年で28回目になるそうです。
審査員コメントとして歌人の俵万智さんが次のように述べられています。
まさに青天霹靂だった政界の動き。疲労困憊の宅配便のドライバーさん。「政変霹靂(せいへんへきれき)」と「荷労困配(にろうこんぱい)」は、音の重なりを最大限に生かして、元の四字熟語の意味を効果的に響かせました。創作四字熟語の原点ともいうべきオーソドックスな作品です。「蟻来迷惑(ありきためいわく)」は、訓読みを取り入れた珍しい手法。「世代皇代(せだいこうたい)」と「中央習権(ちゅうおうしゅうけん)」は、漢字一字を変えただけで、まさに今年の四字熟語に。シンプルにしてインパクトのある出来栄えです。ローマ字を活用した作品も近年増えてきましたが「J音無事(じぇいおんぶじ)」は、アラートを「音」一字で表現したところがミソですね。同じテーマで競う優秀作品が、今年は例年になく多くて、選ぶのに苦労しました。「棋聡天才(きそうてんさい)」と「連聡棋録(れんそうきろく)」、「桐走十内(きそうてんない)」と「九九八新(きゅうきゅうはっしん)」など、それぞれに魅力のあるペアです。みなさんなら、どちらに軍配をあげるでしょうか。最後に、大いに笑わせてもらったのが「盆裸万笑(ぼんらばんしょう)」と「珍文漢糞(ちんぶんかんぷん)」。意味を凝縮させる漢字ならではの力が、遺憾なく発揮されています。
俵 万智(歌人)
-----------------------------------------------------------------------------------
俵 万智
(たわら まち)
誕生
1962年12月31日(54歳)
日本 大阪府北河内郡門真町(現・門真市)
職業
歌人
言語
日本語
国籍
日本
教育
学士(文学)
最終学歴
早稲田大学第一文学部日本文学専修
活動期間
1986年 -
代表作
『サラダ記念日』(1987年)
『チョコレート革命』(1997年)
主な受賞歴
角川短歌賞(1986年)
現代歌人協会賞(1988年)
紫式部文学賞(2003年)
若山牧水賞(2006年)
---------------------------------------------------------------------------------------
優秀作品10編は
 (きそうてんさい)
(きそうてんさい)
将棋の天才、藤井聡太棋士。
 (きゅうきゅうはっしん)
(きゅうきゅうはっしん)
桐生祥秀選手、100メートルで日本人初の9秒98。
 (せいへんへきれき)
(せいへんへきれき)
衆議院解散、希望の党結党、民進党合流・・・。目まぐるしい政界の動き。
 (にろうこんぱい)
(にろうこんぱい)
宅配業界の人手不足が深刻。
 (ありきためいわく)
(ありきためいわく)
コンテナにくっついて猛毒を持つヒアリがやってきた。
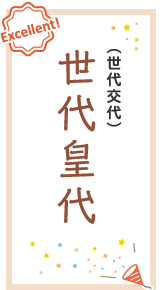 (せだいこうたい)
(せだいこうたい)
「退位特例法」成立。
 (じぇいおんぶじ)
(じぇいおんぶじ)
国民に緊急避難を呼び掛けるJアラートが発動したが、事無きを得た。
 (ちゅうおうしゅうけん)
(ちゅうおうしゅうけん)
中国は習近平体制で権力集中。
 (ぼんらばんしょう)
(ぼんらばんしょう)
アキラ100%さん、お盆ひとつの裸芸でブレーク。
 (ちんぶんかんぷん)
(ちんぶんかんぷん)
うんこが入った例文で、子どもが楽しく漢字を覚えられる。
私が面白いと思ったのはこんなものもあります・・
 (じゅうえんはって)
(じゅうえんはって)
郵便料金改定、ハガキが52円から62円に。
 (せんせんきょうきょう)
(せんせんきょうきょう)
割り込み・幅寄せなどの煽り運転による交通事故が発生し、社会問題となった。
今年で28回目になるそうです。
審査員コメントとして歌人の俵万智さんが次のように述べられています。
まさに青天霹靂だった政界の動き。疲労困憊の宅配便のドライバーさん。「政変霹靂(せいへんへきれき)」と「荷労困配(にろうこんぱい)」は、音の重なりを最大限に生かして、元の四字熟語の意味を効果的に響かせました。創作四字熟語の原点ともいうべきオーソドックスな作品です。「蟻来迷惑(ありきためいわく)」は、訓読みを取り入れた珍しい手法。「世代皇代(せだいこうたい)」と「中央習権(ちゅうおうしゅうけん)」は、漢字一字を変えただけで、まさに今年の四字熟語に。シンプルにしてインパクトのある出来栄えです。ローマ字を活用した作品も近年増えてきましたが「J音無事(じぇいおんぶじ)」は、アラートを「音」一字で表現したところがミソですね。同じテーマで競う優秀作品が、今年は例年になく多くて、選ぶのに苦労しました。「棋聡天才(きそうてんさい)」と「連聡棋録(れんそうきろく)」、「桐走十内(きそうてんない)」と「九九八新(きゅうきゅうはっしん)」など、それぞれに魅力のあるペアです。みなさんなら、どちらに軍配をあげるでしょうか。最後に、大いに笑わせてもらったのが「盆裸万笑(ぼんらばんしょう)」と「珍文漢糞(ちんぶんかんぷん)」。意味を凝縮させる漢字ならではの力が、遺憾なく発揮されています。
俵 万智(歌人)
-----------------------------------------------------------------------------------
俵 万智
(たわら まち)
誕生
1962年12月31日(54歳)
日本 大阪府北河内郡門真町(現・門真市)
職業
歌人
言語
日本語
国籍
日本
教育
学士(文学)
最終学歴
早稲田大学第一文学部日本文学専修
活動期間
1986年 -
代表作
『サラダ記念日』(1987年)
『チョコレート革命』(1997年)
主な受賞歴
角川短歌賞(1986年)
現代歌人協会賞(1988年)
紫式部文学賞(2003年)
若山牧水賞(2006年)
---------------------------------------------------------------------------------------
優秀作品10編は
 (きそうてんさい)
(きそうてんさい)将棋の天才、藤井聡太棋士。
 (きゅうきゅうはっしん)
(きゅうきゅうはっしん)桐生祥秀選手、100メートルで日本人初の9秒98。
 (せいへんへきれき)
(せいへんへきれき)衆議院解散、希望の党結党、民進党合流・・・。目まぐるしい政界の動き。
 (にろうこんぱい)
(にろうこんぱい)宅配業界の人手不足が深刻。
 (ありきためいわく)
(ありきためいわく)コンテナにくっついて猛毒を持つヒアリがやってきた。
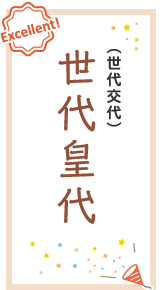 (せだいこうたい)
(せだいこうたい)「退位特例法」成立。
 (じぇいおんぶじ)
(じぇいおんぶじ)国民に緊急避難を呼び掛けるJアラートが発動したが、事無きを得た。
 (ちゅうおうしゅうけん)
(ちゅうおうしゅうけん)中国は習近平体制で権力集中。
 (ぼんらばんしょう)
(ぼんらばんしょう)アキラ100%さん、お盆ひとつの裸芸でブレーク。
 (ちんぶんかんぷん)
(ちんぶんかんぷん)うんこが入った例文で、子どもが楽しく漢字を覚えられる。
私が面白いと思ったのはこんなものもあります・・
 (じゅうえんはって)
(じゅうえんはって)郵便料金改定、ハガキが52円から62円に。
 (せんせんきょうきょう)
(せんせんきょうきょう)割り込み・幅寄せなどの煽り運転による交通事故が発生し、社会問題となった。
今日は年賀状特別扱い開始の日です、詳しく知りたいので調べてみますと郵便局関係での解説は見つかりません。
八木浩之さんのブログに「季節のお便り」というのがあります。
ブログは二十四節気や雑節や記念日など項目ごとに分けてありどれも分かりやすく書かれています。
「十二月のお便り」の中に年賀状の意味や歴史が詳しく書かれているので紹介します。

■12月15日「年賀状特別扱い開始の日」です。■
全国の郵便局では、この日から年賀はがきの特別扱いを開始しています。
25日までに投函された分についての年賀はがきは、翌年1月1日(元旦)に必ず配達されるという特別な制度です。
年賀状とは新年に送られる郵便葉書やカードを用いた挨拶状のことです。日本では、古く奈良時代より新年の年始回りという年始の挨拶をする行事があり、平安時代には貴族や公家にも風習が広まり、挨拶が行えないような遠方などへの年始回りに変わるものとして書状でも交わされるようになりました。
江戸時代になると新年の挨拶は社会全般に広まり、飛脚が新年挨拶書状を運ぶようになって来ました。明治維新後の明治4年(1871)、郵便制度が確立しましたが、年賀状は書状で送る習慣が定着していました。
明治6年(1873)に「郵便はがき」を発行するようになると、年始の挨拶も葉書で年賀状を送る習慣が急速に広まったのです。 明治20年頃になると年賀状を出すことが国民の間に年末年始の行事の1つとして定着したのです。
その結果、年末年始にかけて年賀状が集中し、郵便取扱量が何十倍にも膨れ上がり、通常郵便に加えて膨大な年賀状のため郵便物全体の処理が遅れ、年賀状以外の郵便物にも影響し通常より到着が遅れることがしばしば発生するようになりまた。
これを解決する対策として明治32年(1899)12月に指定された郵便局での年賀郵便の特別取扱が始まり、明治38年(1905)完全に全国の郵便局で実施されるようになりました。
なお年賀状は本来、元日に書いて投函していましたが、この特別取扱をきっかけに年末までに投函し元日に配達するようになったのです。
明治40年(1907)から葉書の表に「年賀」であることを表記すれば枚数にかかわらず郵便ポストに投函できるようになったのです。

年賀状作成で毎年失敗作が出ます。新しいものと交換してもらうため郵便局に行くとはがき大のメモを頂きました。内容は年賀はがきの郵便料金について、「差出期間」、「対象となるはがき」、「注意事項」となっています。
要約すれば2017年12月15日(金)~2018年1月7日(日)までは52円で扱いますが8日以降は10円追加の通常はがき扱いになります。
八木浩之さんのブログに「季節のお便り」というのがあります。
ブログは二十四節気や雑節や記念日など項目ごとに分けてありどれも分かりやすく書かれています。
「十二月のお便り」の中に年賀状の意味や歴史が詳しく書かれているので紹介します。

■12月15日「年賀状特別扱い開始の日」です。■
全国の郵便局では、この日から年賀はがきの特別扱いを開始しています。
25日までに投函された分についての年賀はがきは、翌年1月1日(元旦)に必ず配達されるという特別な制度です。
年賀状とは新年に送られる郵便葉書やカードを用いた挨拶状のことです。日本では、古く奈良時代より新年の年始回りという年始の挨拶をする行事があり、平安時代には貴族や公家にも風習が広まり、挨拶が行えないような遠方などへの年始回りに変わるものとして書状でも交わされるようになりました。
江戸時代になると新年の挨拶は社会全般に広まり、飛脚が新年挨拶書状を運ぶようになって来ました。明治維新後の明治4年(1871)、郵便制度が確立しましたが、年賀状は書状で送る習慣が定着していました。
明治6年(1873)に「郵便はがき」を発行するようになると、年始の挨拶も葉書で年賀状を送る習慣が急速に広まったのです。 明治20年頃になると年賀状を出すことが国民の間に年末年始の行事の1つとして定着したのです。
その結果、年末年始にかけて年賀状が集中し、郵便取扱量が何十倍にも膨れ上がり、通常郵便に加えて膨大な年賀状のため郵便物全体の処理が遅れ、年賀状以外の郵便物にも影響し通常より到着が遅れることがしばしば発生するようになりまた。
これを解決する対策として明治32年(1899)12月に指定された郵便局での年賀郵便の特別取扱が始まり、明治38年(1905)完全に全国の郵便局で実施されるようになりました。
なお年賀状は本来、元日に書いて投函していましたが、この特別取扱をきっかけに年末までに投函し元日に配達するようになったのです。
明治40年(1907)から葉書の表に「年賀」であることを表記すれば枚数にかかわらず郵便ポストに投函できるようになったのです。

年賀状作成で毎年失敗作が出ます。新しいものと交換してもらうため郵便局に行くとはがき大のメモを頂きました。内容は年賀はがきの郵便料金について、「差出期間」、「対象となるはがき」、「注意事項」となっています。
要約すれば2017年12月15日(金)~2018年1月7日(日)までは52円で扱いますが8日以降は10円追加の通常はがき扱いになります。
原発の再稼働について私は再稼働について反対の意見を持っています。理由は安全性にあります。福島の原発事故はその後色々な報道で知る限り事故処理についてはほとんど進展していないこと。廃炉作業についてもいまだこれと言った最良の方法が見つかっていないこと。原子力委員会が再稼働について厳しい条件を出して再稼働を認めても事故が起きればだれも責任は取りません。地震に津波、火山噴火、などの自然災害のほか、最近の世界情勢を考えるとテロや北朝鮮の核ミサイル問題など年々危険因子が増えている。条件の異なる原発に対しての安全対策に今のところ何一つ効果的な対策は打たれてはおりません。何かが起れば「想定外」で済ませるのはもうまっぴらである。
新聞社の世論調査でも原発再稼働の賛否については各社多少の差はあるものの反対55%、賛成26%と反対が大きく上回っています。
今回の広島高裁の判断、これまでにない火山噴火というそれも9万年前の事例を引き出して「立地として不適」としたのは、原発についてそこまで安全性を考えなければならないという慎重論だと思います。


伊方運転差し止め、阿蘇噴火で「火砕流到達も」
四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)について、広島、松山両市の住民が運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、広島高裁は13日、差し止めを命じる決定をした。
野々上裁判長は「阿蘇山(熊本県)の火砕流が敷地に到達する可能性が十分小さいとはいえない。立地として不適」と断じ、重大事故で「住民の生命・身体への具体的危険がある」と認めた。差し止め期限は来年9月末とした。高裁段階の差し止め判断は初めて。・・・
・・・ 決定で野々上裁判長は、規制委の内規「火山影響評価ガイド」を厳格に適用し、半径160キロ内の火山で今後起こる噴火の規模が推定できない場合、過去最大の噴火を想定すべきだと指摘。伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山について「9万年前の最大噴火で火砕流が敷地に到達した可能性が十分小さいと評価できない。原発の立地は認められない」と述べた。地質調査などを基に「火砕流は到達せず安全」としていた四電の主張を退けた。
新聞社の世論調査でも原発再稼働の賛否については各社多少の差はあるものの反対55%、賛成26%と反対が大きく上回っています。
今回の広島高裁の判断、これまでにない火山噴火というそれも9万年前の事例を引き出して「立地として不適」としたのは、原発についてそこまで安全性を考えなければならないという慎重論だと思います。


伊方運転差し止め、阿蘇噴火で「火砕流到達も」
四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)について、広島、松山両市の住民が運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、広島高裁は13日、差し止めを命じる決定をした。
野々上裁判長は「阿蘇山(熊本県)の火砕流が敷地に到達する可能性が十分小さいとはいえない。立地として不適」と断じ、重大事故で「住民の生命・身体への具体的危険がある」と認めた。差し止め期限は来年9月末とした。高裁段階の差し止め判断は初めて。・・・
・・・ 決定で野々上裁判長は、規制委の内規「火山影響評価ガイド」を厳格に適用し、半径160キロ内の火山で今後起こる噴火の規模が推定できない場合、過去最大の噴火を想定すべきだと指摘。伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山について「9万年前の最大噴火で火砕流が敷地に到達した可能性が十分小さいと評価できない。原発の立地は認められない」と述べた。地質調査などを基に「火砕流は到達せず安全」としていた四電の主張を退けた。
今日は日本語の話。
見出しを見て思わず考えさせられるくらい日本語を正確に理解していない自分自身を失笑してしまう。
私ならこんな時に使うかも知れません。
でも間違っているらしい。
読売新聞 くらし教育面に【なぜなに日本語】というコーナーがあり今日で379回目の様子、番号が振ってありました。
内容は以下の記事から・・
「先生が突然、タレントの物まねを始めたので、みんな失笑した」といったとき、教室の様子は次のどちらだと思いますか?
①シーンと静まりかえった
②ワハハと笑い声が響いた-----。
失望(望みを失う)、失業(仕事を失う)といった熟語があるので、失笑は、笑いを失う、つまり、笑いも出ないくらいあきれる様子だと思っている人が多いようです。しかし、それは間違い。おかしさをこらえきれずに笑うのが失笑です。正解は②です。
「失笑を買う」の言い方でよく使われます。考えのたりない、ばかげた発言や行動で笑われることで、その笑いの中には、あきれる気持ちが入っています。そこから、笑うのを通り越し、笑いも出ないくらいあきれるという意味にとらえられるようになったのかもしれません。
また、嘲笑(軽蔑して笑う)や、冷笑(冷ややかに笑う)と同じように使われることもありますが、本来の意味とはやはり少しずれるでしょう。
「失」で始まる熟語に失言と言うのもありますね。言(言葉)を失う(=何も言えなくなる)のではありません。言ってはならないことをうっかり言ってしまうこと。失笑を買う原因のひとつです。(関根健一)

関根健一
(せきね・けんいち)
1957年、群馬県生まれ。1979年、同志社大学法学部卒業。1981年、立教大学文学部卒業。現在、読売新聞東京本社紙面審査委員会用語幹事。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。文化審議会国語分科会委員。
著書に、『日本人が必ず間違う日本語1000』『大人の10人中9人が間違ってつかう! 日本語ドリル1000』(以上、宝島社)、『ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室』『ちびまる子ちゃんの敬語教室』『ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室』(以上、集英社)、『笑う敬語術-オトナ社会のことばのしくみ』(勁草書房)、『ビジネス文書の作り方』(日本経団連出版)、『なぜなに日本語』『日本語・日めくり』(以上、読売新聞社「読売ebooks」)などがある。
見出しを見て思わず考えさせられるくらい日本語を正確に理解していない自分自身を失笑してしまう。
私ならこんな時に使うかも知れません。
でも間違っているらしい。
読売新聞 くらし教育面に【なぜなに日本語】というコーナーがあり今日で379回目の様子、番号が振ってありました。
内容は以下の記事から・・
「先生が突然、タレントの物まねを始めたので、みんな失笑した」といったとき、教室の様子は次のどちらだと思いますか?
①シーンと静まりかえった
②ワハハと笑い声が響いた-----。
失望(望みを失う)、失業(仕事を失う)といった熟語があるので、失笑は、笑いを失う、つまり、笑いも出ないくらいあきれる様子だと思っている人が多いようです。しかし、それは間違い。おかしさをこらえきれずに笑うのが失笑です。正解は②です。
「失笑を買う」の言い方でよく使われます。考えのたりない、ばかげた発言や行動で笑われることで、その笑いの中には、あきれる気持ちが入っています。そこから、笑うのを通り越し、笑いも出ないくらいあきれるという意味にとらえられるようになったのかもしれません。
また、嘲笑(軽蔑して笑う)や、冷笑(冷ややかに笑う)と同じように使われることもありますが、本来の意味とはやはり少しずれるでしょう。
「失」で始まる熟語に失言と言うのもありますね。言(言葉)を失う(=何も言えなくなる)のではありません。言ってはならないことをうっかり言ってしまうこと。失笑を買う原因のひとつです。(関根健一)

関根健一
(せきね・けんいち)
1957年、群馬県生まれ。1979年、同志社大学法学部卒業。1981年、立教大学文学部卒業。現在、読売新聞東京本社紙面審査委員会用語幹事。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。文化審議会国語分科会委員。
著書に、『日本人が必ず間違う日本語1000』『大人の10人中9人が間違ってつかう! 日本語ドリル1000』(以上、宝島社)、『ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室』『ちびまる子ちゃんの敬語教室』『ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室』(以上、集英社)、『笑う敬語術-オトナ社会のことばのしくみ』(勁草書房)、『ビジネス文書の作り方』(日本経団連出版)、『なぜなに日本語』『日本語・日めくり』(以上、読売新聞社「読売ebooks」)などがある。
早いもので明日は「煤払い」という。我が家では家内に指示をされて少しづつ掃除を始めている。今までは家の掃除は家内に任せきりであったので要領が分からない事もあり、指示されるままに動かざるを得ない。これまでに障子の張替や風呂掃除くらいはマスターした。今回は台所の換気扇の掃除である。今日の【編集手帳】は煤払いの話、丁髷で時代をつなぎ大相撲の話を引き出して、締めの話は横綱のほこりに持ってゆくところなど、「煤払い」から「埃」と「誇り」に結ぶ話の繋ぎ方がじつに上手い。
 油汚れを落とすのも大変な作業です
油汚れを落とすのも大変な作業です
師走の江戸川柳という。〈銭金がこうたまればと十三日〉。この時代の風習を知らなければ、何のことだか分からない◆12月13日は、年に一度大そうじ「煤(すす)払い」の日だった。たまったものは、ちりやほこりだろう。はたきを手に駆けずり回る曲げ姿の江戸庶民を浮かべたとき、ふと、この現代にも古式ゆかしくまげ姿を受け継ぐ人たちがいるのに気づく◆さっぱりとそうじがすみ、来年を迎える準備が整うのはいつだろう。。元横綱、日馬富士の傷害事件を引きずる相撲界である。鳥取県警が書類送検し、捜査は一つの区切りを迎えた◆依然すっきりしないのは、被害者の貴ノ岩が口をつぐんだままでいることに尽きよう。元横綱によれば、相撲部屋はちがっても、自らと同じく親を失う不幸を経験した貴ノ岩を他人とは思えず、兄弟のような付き合いをしていた。礼節を欠く態度に必要以上にカッとなったのは、若い力士への思いがあったからだという◆暴力は許されない。それは当然として、元横綱の気持ちのみは理解できる。信じていいものか。真実にかぶさるほこりを払えるのは貴ノ岩その人しかあるまい。
読売新聞 【編集手帳】 2017・12・12

煤払い
現代の大掃除のもととなるのが、12月13日の「正月事始め」で行われていた「煤払い」です。
お正月は年神様を家に招き入れる行事ですが、昔はご先祖様も帰ってくるとされていました。そこで、神棚や仏壇の掃除をして正月の準備をする習わしがあり、やがて家中を掃除して年神様をお迎えするようになりました。
正月に年神様を迎えるために、1年の汚れを払い、清めることが「煤払い」です。
江戸時代、12月13日に江戸城では「煤払い」を行っていました。
1年間の汚れを払い隅から隅まできれいにすると、年神様がたくさんのご利益を持って降りてくるといわれ、江戸城では城内や神棚を煤払いし、江戸庶民も煤払いに精を出しました。これが今日まで伝えられ、煤汚れとは無縁の生活になった現在でも、社寺などでは煤払い行事が残っています。
一般の家庭でも、幸多き新年にするために、13日には大掃除をして正月準備を始めたいところですが、家中の掃除を終わらせるのは無理というもの。この日は神棚や仏壇などをきれいにし、大掃除の計画を立ててみてはいかがでしょう。本格的な大掃除は、もう少し日にちが経ってから、天気の良い日を選んで行います。
 油汚れを落とすのも大変な作業です
油汚れを落とすのも大変な作業です師走の江戸川柳という。〈銭金がこうたまればと十三日〉。この時代の風習を知らなければ、何のことだか分からない◆12月13日は、年に一度大そうじ「煤(すす)払い」の日だった。たまったものは、ちりやほこりだろう。はたきを手に駆けずり回る曲げ姿の江戸庶民を浮かべたとき、ふと、この現代にも古式ゆかしくまげ姿を受け継ぐ人たちがいるのに気づく◆さっぱりとそうじがすみ、来年を迎える準備が整うのはいつだろう。。元横綱、日馬富士の傷害事件を引きずる相撲界である。鳥取県警が書類送検し、捜査は一つの区切りを迎えた◆依然すっきりしないのは、被害者の貴ノ岩が口をつぐんだままでいることに尽きよう。元横綱によれば、相撲部屋はちがっても、自らと同じく親を失う不幸を経験した貴ノ岩を他人とは思えず、兄弟のような付き合いをしていた。礼節を欠く態度に必要以上にカッとなったのは、若い力士への思いがあったからだという◆暴力は許されない。それは当然として、元横綱の気持ちのみは理解できる。信じていいものか。真実にかぶさるほこりを払えるのは貴ノ岩その人しかあるまい。
読売新聞 【編集手帳】 2017・12・12

煤払い
現代の大掃除のもととなるのが、12月13日の「正月事始め」で行われていた「煤払い」です。
お正月は年神様を家に招き入れる行事ですが、昔はご先祖様も帰ってくるとされていました。そこで、神棚や仏壇の掃除をして正月の準備をする習わしがあり、やがて家中を掃除して年神様をお迎えするようになりました。
正月に年神様を迎えるために、1年の汚れを払い、清めることが「煤払い」です。
江戸時代、12月13日に江戸城では「煤払い」を行っていました。
1年間の汚れを払い隅から隅まできれいにすると、年神様がたくさんのご利益を持って降りてくるといわれ、江戸城では城内や神棚を煤払いし、江戸庶民も煤払いに精を出しました。これが今日まで伝えられ、煤汚れとは無縁の生活になった現在でも、社寺などでは煤払い行事が残っています。
一般の家庭でも、幸多き新年にするために、13日には大掃除をして正月準備を始めたいところですが、家中の掃除を終わらせるのは無理というもの。この日は神棚や仏壇などをきれいにし、大掃除の計画を立ててみてはいかがでしょう。本格的な大掃除は、もう少し日にちが経ってから、天気の良い日を選んで行います。




