


 遥拝堰
遥拝堰 遥拝堰
遥拝堰 遥拝堰
遥拝堰今日は花曇り、毎年いつもなら近所の公園で良く晴れた日にお弁当を持ってお花見をするのですが、今年は遥拝神社の方に行ってみないかとの家内からの要望があり夕方近くになって球磨川河口近くの遥拝神社下の遥拝堰まで行くことにしました。
今日までは気温も上がり天気もそこそこ良かったのですが今夜からは下り坂の天気になり花冷えがするそうです。
球磨川〜遥拝堰〜
萩原堤からわずか上流にある『遥拝頭首工(ようはいとうしゅこう)』。
球磨川の水を農業用水や工業用水として支えるための施設。
鎌倉時代からすでに「杭瀬(くいせ)」と呼ばれる堰があり、「江戸時代に加藤清正が杭瀬を大石堰に改築した・・・」とある。球磨川は、八代海を育む一方で地域産業にも欠かせない川なのである。
案内マップで八代マリーナを探すと(記載はないけど探してみて)とってもいい場所に位置。

世界大百科事典内の花冷えの言及
【日本列島】より
…天気の言葉には,〈風〉と〈雨〉の両方の意味をもつものが多い。 花冷えサクラの花の咲くころに急に気温が低くなる現象をいい,寒冷前線通過後の寒気や北東気流による冷気などが侵入すると起こりやすい。 花曇りサクラの花の咲くころ,空一面ねずみ色に見える曇天をいう。…
全国的に気温上昇 花粉症の方は対策を

© ウェザーマップ 30日の天気予報。
きのう29日(火)は北日本では晴れて気温が上昇し、札幌では今季最高の13.1℃を記録しました。一方、西・東日本は雲が優勢の空で雨の降った所もありました。
きょう30日(水)は全国的に晴れる所が多くなりますが、西日本を中心ににわか雨となる所があるでしょう。気温はきのうより高くなる所が多く、仙台ではきのうより10℃高い19℃まで上がる予想です。
ただ、前線が通過する北海道では雨や雪となる所もあるでしょう。
気温が上がるため、花粉が多く飛散しそうです。気になる方は、洗濯物をよく払ってから取りこむなど、花粉対策をした方がよいでしょう。
(気象予報士・森本 啓介)
※今日の天気予報に注意してテレビなどの情報に耳を傾けていると、〝春本番〟〝寒の戻り〟〝花粉対策〟などの言葉が印象に残りました。
日本の気候は暖かくなったり、寒くなったり、風が吹いたりこの小さな日本で地域によってこれだけ気候が変わるのは時期的には珍しい事なんでしょうね。

© ウェザーマップ 30日の天気予報。
きのう29日(火)は北日本では晴れて気温が上昇し、札幌では今季最高の13.1℃を記録しました。一方、西・東日本は雲が優勢の空で雨の降った所もありました。
きょう30日(水)は全国的に晴れる所が多くなりますが、西日本を中心ににわか雨となる所があるでしょう。気温はきのうより高くなる所が多く、仙台ではきのうより10℃高い19℃まで上がる予想です。
ただ、前線が通過する北海道では雨や雪となる所もあるでしょう。
気温が上がるため、花粉が多く飛散しそうです。気になる方は、洗濯物をよく払ってから取りこむなど、花粉対策をした方がよいでしょう。
(気象予報士・森本 啓介)
※今日の天気予報に注意してテレビなどの情報に耳を傾けていると、〝春本番〟〝寒の戻り〟〝花粉対策〟などの言葉が印象に残りました。
日本の気候は暖かくなったり、寒くなったり、風が吹いたりこの小さな日本で地域によってこれだけ気候が変わるのは時期的には珍しい事なんでしょうね。
「このエネルギー源は適切に扱えばほとんど環境を汚さない。しかしこの魔法のような資源を使うには、尋常ならざる警戒心を社会が長く持ち続けなければならない」。物理学者ワインバーグは1971年、原子力を「ファウストの取引」になぞらえて論じた▲ファウストは悪魔と取引し、自分の命と引き換えに魔力を得る。マンハッタン計画参加に始まり原子炉の設計を主導したワインバーグには悪魔が自身、そして魂を売ったファウストが人類と重なったのだろう▲研究の粋を集めた米スリーマイル島原発2号機で事故が起きたのは79年3月28日早朝。設計の不備に人為ミスも重なり、冷却機能を失った原子炉は炉心溶融に至る。世界は肝を冷やし、近隣住民80万人も一時、被ばくの恐怖を味わった▲事故を機に米政府は安全基準を大幅に見直した。ワインバーグの警句の意味と高すぎる代償に社会は気づいたはずだ。しかしその後もチェルノブイリ、福島と深刻な原発事故は相次ぎ、大規模な環境破壊を招いた▲「アトムズ・フォー・ピース(平和のための原子力)」を旗印に進められてきた原発が、今度は戦場と化した21世紀の地球である。核を脅しに使う露大統領の前では原発も武器にしか見えないらしい▲核戦争などによって人類が滅びるまでの猶予を象徴的に示す「終末時計」は今年1月時点で「100秒前」だった。冷戦終結直後の「17分前」から大幅に進み、今後さらに進むのは確実だ。さて、何から手をつけるべきか。
毎日新聞余禄 2021.03.29

終末時計とは正式には 「世界終末時計」 と呼びます。 人類 (地球)滅亡時刻=0秒 (0時0分)とみなした時に、今は何秒(何分)前なのか? をいろいろな情報をもとに算出し、1年に1度発表しています。 要は 「地球 (人類)の運命の時間まであとどれくらい? 」 ということですね。 世界終末時計が設置されたのは1947年で、そこから 2020年が過去最短=もっとも地球 (人類)滅亡に近づいた と発表されました。 米国の科学者らは23日、地球滅亡までの時間を示す「終末時計」を公表した。 昨年より20秒進み、残り100秒となった。 公表を始めた1947年以降で最も滅亡に近づいた。
※コロナ禍で世界中の国や人々が困っている中で、突然、ウクライナに軍事侵攻し避難をしている武器を持たない女性や子供まで殺害するプーチン露大統領の一方的な侵略のやり方は決して許されるべきものではありません。
軍事侵攻が始まってひと月以上が経ち何ら治まる気配もありません。
どうにかならないものでしょうか?
毎日新聞余禄 2021.03.29

終末時計とは正式には 「世界終末時計」 と呼びます。 人類 (地球)滅亡時刻=0秒 (0時0分)とみなした時に、今は何秒(何分)前なのか? をいろいろな情報をもとに算出し、1年に1度発表しています。 要は 「地球 (人類)の運命の時間まであとどれくらい? 」 ということですね。 世界終末時計が設置されたのは1947年で、そこから 2020年が過去最短=もっとも地球 (人類)滅亡に近づいた と発表されました。 米国の科学者らは23日、地球滅亡までの時間を示す「終末時計」を公表した。 昨年より20秒進み、残り100秒となった。 公表を始めた1947年以降で最も滅亡に近づいた。
※コロナ禍で世界中の国や人々が困っている中で、突然、ウクライナに軍事侵攻し避難をしている武器を持たない女性や子供まで殺害するプーチン露大統領の一方的な侵略のやり方は決して許されるべきものではありません。
軍事侵攻が始まってひと月以上が経ち何ら治まる気配もありません。
どうにかならないものでしょうか?
今日はあまり聞かない言葉ですが朝のニュースにこんな気象言葉が使われました日本語では毎年耳にする言葉です。
メイストームとは、日本の3月から5月にかけて見られる気象現象のひとつです。台風並みの暴風や大吹雪、海岸では高波などが全国的に発生します。
その原因は、日本の北から入ってくる冷たい空気と、南から流れてくる暖かい空気が衝突すること。冷たい空気と暖かい空気の上下が入れ替わると、運動エネルギーが生まれます。これにより温帯低気圧が一気に発達し、強風を引き起こします。
メイストームの特徴は風の吹き方です。台風の場合、強風になるのは渦の中心部の周辺ですが、メイストームの場合、低気圧の中心部から離れたエリアでも強風になります。被害も広範囲にわたりやすく、全国各地で記録的な暴風を観測したケースもあります。

久しぶりに孫たちが遊びに来ました。こんなに良い天気だったのですが今日はずっと雨模様。




メイストームとは、日本の3月から5月にかけて見られる気象現象のひとつです。台風並みの暴風や大吹雪、海岸では高波などが全国的に発生します。
その原因は、日本の北から入ってくる冷たい空気と、南から流れてくる暖かい空気が衝突すること。冷たい空気と暖かい空気の上下が入れ替わると、運動エネルギーが生まれます。これにより温帯低気圧が一気に発達し、強風を引き起こします。
メイストームの特徴は風の吹き方です。台風の場合、強風になるのは渦の中心部の周辺ですが、メイストームの場合、低気圧の中心部から離れたエリアでも強風になります。被害も広範囲にわたりやすく、全国各地で記録的な暴風を観測したケースもあります。

久しぶりに孫たちが遊びに来ました。こんなに良い天気だったのですが今日はずっと雨模様。




今日は彼岸明け、昔からよく言ったもので〝暑さ寒さも彼岸まで〟彼岸を挟んで季節が変わっていきます。急に寒い日が続き曇りや雨の日の後、今日は肌に感じるほどの暖かい日差しを感じます。

「暑さ寒さも彼岸(ひがん)まで」とは、「夏の暑さも冬の寒さも春秋の彼岸を境に和らぐ」という意味の、季節の変転を表すことわざです。 具体的には、夏の暑さは秋分頃まで、冬の寒さは春分頃までには和らぎ、それ以後は気候が落ち着いて過ごしやすくなるという意味で、教訓的な意味を含めず、季節を巡る慣習的な言い習わしとして使われます。 「暑さ寒さも彼岸まで」は、先に説明した季節を巡る慣習的な言い習わしの意味で使われるほかに、「辛いことや厳しい状況もやがては終わりが訪れる」という意味のことわざとして使われることもあります。

「暑さ寒さも彼岸(ひがん)まで」とは、「夏の暑さも冬の寒さも春秋の彼岸を境に和らぐ」という意味の、季節の変転を表すことわざです。 具体的には、夏の暑さは秋分頃まで、冬の寒さは春分頃までには和らぎ、それ以後は気候が落ち着いて過ごしやすくなるという意味で、教訓的な意味を含めず、季節を巡る慣習的な言い習わしとして使われます。 「暑さ寒さも彼岸まで」は、先に説明した季節を巡る慣習的な言い習わしの意味で使われるほかに、「辛いことや厳しい状況もやがては終わりが訪れる」という意味のことわざとして使われることもあります。
朝食中にテレビの天気予報で「催花雨」というあまり聞き慣れない言葉を耳にしました。
アナウンサーが話の中で桜の開花の話をされていたことまでは頭の中に残っているのですが肝心の「催〇〇」の文字がどんな字を書いて有ったのかどうしても思い出さず家内とお互いに確かめ合っている間に番組が終わってしまってーーー頭の中はチンプンカンプン。
後ほど記憶を頼りに調べてみますと「催花雨」にたどり着きました。
この歳になると覚える事より忘れる事の方が多くて記憶もあまり頼りになりません。
催花雨とは - コトバンク
https://kotobank.jp/word/催花雨
デジタル大辞泉 「催花雨」の解説 さいか‐う〔サイクワ‐〕【催花雨】 春、早く咲けと花をせきたてるように降る雨。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
催す【もよおす】の意味と例文(使い方):日本語表現インフォ
https://hyogen.info/word/4005509
催す【もよおす】とは 1.刺激を与えて、物事を起こす状態にさせる。 そういう気持ちにさせる。 2.催促する。 早くするように急がせる。 3.人を集めて会などを開く。 計画して行事をす
※催花雨とは、開花を促すような雨のこと 。 桜をはじめ、いろいろな花を催す(=早く咲くようにせかす)雨という意味です。 俳句の春の季語でもある 催花雨 。 響きがとても美しい日本語だなって思います。
参照: mikaco.info/early-spring-rain/

アナウンサーが話の中で桜の開花の話をされていたことまでは頭の中に残っているのですが肝心の「催〇〇」の文字がどんな字を書いて有ったのかどうしても思い出さず家内とお互いに確かめ合っている間に番組が終わってしまってーーー頭の中はチンプンカンプン。
後ほど記憶を頼りに調べてみますと「催花雨」にたどり着きました。
この歳になると覚える事より忘れる事の方が多くて記憶もあまり頼りになりません。
催花雨とは - コトバンク
https://kotobank.jp/word/催花雨
デジタル大辞泉 「催花雨」の解説 さいか‐う〔サイクワ‐〕【催花雨】 春、早く咲けと花をせきたてるように降る雨。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
催す【もよおす】の意味と例文(使い方):日本語表現インフォ
https://hyogen.info/word/4005509
催す【もよおす】とは 1.刺激を与えて、物事を起こす状態にさせる。 そういう気持ちにさせる。 2.催促する。 早くするように急がせる。 3.人を集めて会などを開く。 計画して行事をす
※催花雨とは、開花を促すような雨のこと 。 桜をはじめ、いろいろな花を催す(=早く咲くようにせかす)雨という意味です。 俳句の春の季語でもある 催花雨 。 響きがとても美しい日本語だなって思います。
参照: mikaco.info/early-spring-rain/

昨日までは暖かい気候で桜の開花が楽しみな日々でありましたが、今朝の寒さには防寒着に逆戻りの寒さ対策。
年寄りには急激な寒さはなかなか体がついて行けず非常に酷な季節の変わり目の時期でもあります。

寒の戻り(読み)かんのもどり
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「寒の戻り」の解説
寒の戻り
かんのもどり
立春以降の寒さのぶり返し。春は気温の上昇の時期であるが,ときに冬型の気圧配置(→西高東低の気圧型)になるなど,寒気がぶり返すことがある。寒戻り,さえ返る,寒返る,早春寒波などともいう

南岸低気圧で冷たい雨や雪
鹿児島沖には前線を伴った低気圧があって東進中。関東沖にも別の低気圧がある。これらの影響で、西日本から東日本にかけては広く雨が降り、山沿いや関東の内陸ではみぞれや雪になる所も。北海道は上空の寒気の影響で、日本海側で雪が降っている所があり、天気の急変に注意が必要だ。 ウエザーニュースより
年寄りには急激な寒さはなかなか体がついて行けず非常に酷な季節の変わり目の時期でもあります。

寒の戻り(読み)かんのもどり
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「寒の戻り」の解説
寒の戻り
かんのもどり
立春以降の寒さのぶり返し。春は気温の上昇の時期であるが,ときに冬型の気圧配置(→西高東低の気圧型)になるなど,寒気がぶり返すことがある。寒戻り,さえ返る,寒返る,早春寒波などともいう

南岸低気圧で冷たい雨や雪
鹿児島沖には前線を伴った低気圧があって東進中。関東沖にも別の低気圧がある。これらの影響で、西日本から東日本にかけては広く雨が降り、山沿いや関東の内陸ではみぞれや雪になる所も。北海道は上空の寒気の影響で、日本海側で雪が降っている所があり、天気の急変に注意が必要だ。 ウエザーニュースより
今日は春分の日『3月21日(月)』
春分の日(しゅんぶんのひ)は、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により天文観測による春分が起こる春分日が選定され休日とされる。通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日。 しばしば昼が長くなって「昼と夜の長さが等しくなる日」といわれるが、実際は昼の方が少し長い。詳細は春分を参照。 本項では「春分の日」と「春分日」と区別して記述する。 Wikipediaより

春分
[しゅんぶん]
定義
二十四節気の一。二月中気。太陽の黄経が0度になる時をいう。春の彼岸の中日で,現行の太陽暦で3月21日頃。この日,太陽は天の赤道上にあり,ほぼ真東から出てほぼ真西に沈む。昼夜はほぼ同時間だが,日の出入りの定義と大気による光の屈折などのため,昼間のほうがやや長い。秋分


彼岸
日本の雑節の一つ
彼岸(ひがん)とは、日本の雑節の一つで、春分・秋分を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)である。この期間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼ぶ。 最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶ。 俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜」を1日に1つずつ修める日とされている。
Wikipediaより

…
春分の日(しゅんぶんのひ)は、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により天文観測による春分が起こる春分日が選定され休日とされる。通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日。 しばしば昼が長くなって「昼と夜の長さが等しくなる日」といわれるが、実際は昼の方が少し長い。詳細は春分を参照。 本項では「春分の日」と「春分日」と区別して記述する。 Wikipediaより

春分
[しゅんぶん]
定義
二十四節気の一。二月中気。太陽の黄経が0度になる時をいう。春の彼岸の中日で,現行の太陽暦で3月21日頃。この日,太陽は天の赤道上にあり,ほぼ真東から出てほぼ真西に沈む。昼夜はほぼ同時間だが,日の出入りの定義と大気による光の屈折などのため,昼間のほうがやや長い。秋分


彼岸
日本の雑節の一つ
彼岸(ひがん)とは、日本の雑節の一つで、春分・秋分を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)である。この期間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼ぶ。 最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶ。 俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜」を1日に1つずつ修める日とされている。
Wikipediaより

…
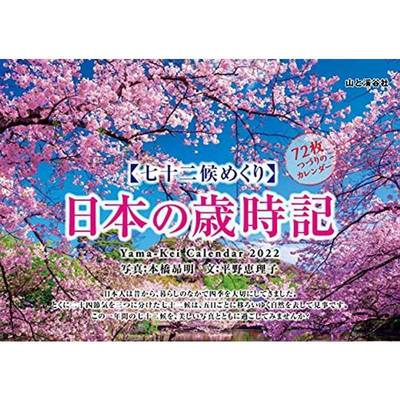
気温が上がり、急に春らしくなってきた。空気が澄んで、 陽ひ の光が明るく万物を照らすという「清明」は4月上旬に迎える二十四節気の一つだが、月を飛び越してきたかのような陽気が各地を包む◆清明が歳時記だけの言葉ではないことを、医師の南杏子さんの小説『ヴァイタル・サイン』(小学館)に教わった。表題は患者の「生命兆候」のことで、脈拍、呼吸、体温、血圧、意識レベルの観察を基本とする◆このうち五つ目の意識レベルが良好な状態を、「清明」と呼ぶという。看護現場を描く物語を読みつつ、病床に差す陽の光のような言葉だと思った◆サインが揺らげば警報が鳴るらしい。<致命的事態となれば耳を刺す一オクターブ違うアラーム>。救急救命医の犬養楓さんの歌集『前線』(書肆侃侃房)から引いた。病棟の 喧騒けんそう を伝える歌集は去年の2月に刊行されている。一年以上過ぎて、現在の感染の波ははるかに大きい◆犬養さんの歌からもう一つ。<昼が来て夜が来てまた昼が来て看護師はこれを一日と呼ぶ>。医療従事者の疲弊はいかばかりだろう。今週、国内の累計感染者が500万人を超えた。
讀賣新聞編集手帳 2022・03・02
●コロナウイルス感染感染者数は(3月01日現在)
累計感染者数 507万9191人
累計死者数 2万3919人
●入院等の状況(3月1日)
入院・療養中(うち重症者) 70万3651(1456)人
●ワクチンの接種状況(2月28日)
1回目総接種数 1億171万7059人 接種率 80,3%
2回目 1億24万6835人 79,2%
3回目 2579万8092人 20,4%
※政府は3回目の接種の遅れを大いに反省してあらゆる予防対策と、医療体制の強化に万全を図ってもらいたい。
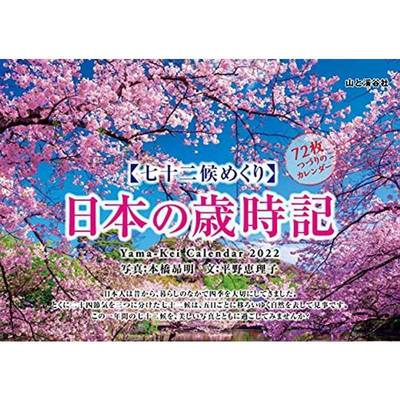
気温が上がり、急に春らしくなってきた。空気が澄んで、 陽 の光が明るく万物を照らすという「清明」は4月上旬に迎える二十四節気の一つだが、月を飛び越してきたかのような陽気が各地を包む◆清明が歳時記だけの言葉ではないことを、医師の南杏子さんの小説『ヴァイタル・サイン』(小学館)に教わった。表題は患者の「生命兆候」のことで、脈拍、呼吸、体温、血圧、意識レベルの観察を基本とする◆このうち五つ目の意識レベルが良好な状態を、「清明」と呼ぶという。看護現場を描く物語を読みつつ、病床に差す陽の光のような言葉だと思った◆サインが揺らげば警報が鳴るらしい。<致命的事態となれば耳を刺す一オクターブ違うアラーム>。救急救命医の犬養楓さんの歌集『前線』(書肆侃侃房)から引いた。病棟の 喧騒 を伝える歌集は去年の2月に刊行されている。一年以上過ぎて、現在の感染の波ははるかに大きい◆犬養さんの歌からもう一つ。<昼が来て夜が来てまた昼が来て看護師はこれを一日と呼ぶ>。医療従事者の疲弊はいかばかりだろう。今週、国内の累計感染者が500万人を超えた。
讀賣新聞編集手帳 2022・03・02
●コロナウイルス感染感染者数は(3月01日現在)
累計感染者数 507万9191人
累計死者数 2万3919人
●入院等の状況(3月1日)
入院・療養中(うち重症者) 70万3651(1456)人
●ワクチンの接種状況(2月28日)
1回目総接種数 1億171万7059人 接種率 80,3%
2回目 1億24万6835人 79,2%
3回目 2579万8092人 20,4%
※政府は3回目の接種の遅れを大いに反省してあらゆる予防対策と、医療体制の強化に万全を図ってもらいたい。

3月1日(火)
今日は久しぶりに雨ですがこの後どんどん気温も上がり春らしくなってきます。
月替わりなので和暦月名をおさらいします。
【和風月名】
●1月睦月(むつき)正月に親類一同が集まる、睦び(親しくする)の月。
●2月如月(きさらぎ)衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。
●3月弥生(やよい)木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月。
●4月卯月(うづき)卯の花の月。
●5月皐月(さつき)早月(さつき)とも言う。早苗(さなえ)を植える月。
●6月水無月
(みなづき、みなつき)水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月の意と言われる。
●7月文月
(ふみづき、ふづき)稲の穂が実る月(穂含月:ほふみづき)
●8月葉月
(はづき、はつき)木々の葉落ち月(はおちづき)。
●9月長月
(ながつき、ながづき)夜長月(よながづき)。
●10月神無月(かんなづき)神の月(「無」は「の」を意味する)の意味。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月という説などもある。
●11月霜月(しもつき)霜の降る月。
●12月師走(しわす)師匠といえども趨走(すうそう、走り回る)する月。
旧暦では、和風月名(わふうげつめい)と呼ばれる月の和風の呼び名を使用していました。和風月名は旧暦の季節や行事に合わせたもので、現在の暦でも使用されることがありますが、現在の季節感とは1~2ヶ月ほどのずれがあります。


 メンバー登録はこちら
メンバー登録はこちら


