
9月1日は二百十日です。この二百十日は 雑節。立春から数えて 210日目。処暑→二百十日→白露。 (2013年は9月1日)。 この時季は稲が開花・結実する大事なときですが、台風が相次いで襲来し、 農作物が被害を受けてしまうことがよくあり、厄日とか荒れ日などと言われています。
八朔(旧暦8月1日)や二百二十日とともに、農家の三大厄日とされている。太陽暦(新暦)では9月1日前後で一定するが、太陰太陽暦(旧暦)では閏月が入るなどして、7月17日から8月11日前後まで、「二百十日」がどの日に該当するのかが一定ではなかった。そのために必要になった暦注であると言われている。台風襲来の特異日とされ、奈良県大和神社で二百十日前3日に行う「風鎮祭」、富山県富山市の「おわら風の盆」など、各地で風鎮めの祭が催されてきた。実際は210日頃の台風はむしろ少ない。この頃が稲の出穂期に当たり、強風が吹くと減収となる恐れがあるために注意を喚起する意味で言われ始めたと言われています。季節の移り変わりの目安となる「季節点」のひとつ。
暦注(れきちゅう)とは、暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などの事項のことである。暦注の大半は、陰陽五行説、十干十二支(干支)に基づいたものである。
風祭り(かざまつり)
風害から農作物を守るため、神に祈願する祭り。全国的に行われているようですが、関東・中部・東海地方では、風祭りと共に風神・風宮の伝承が色濃くあるようです。二百十日前後に行うところが多いですが、正月・2月・4月・7月・8月に行う地方もあります。

妙見宮
8月21日に図書館にて佐藤伸二先生の「八代の歴史」について「八代海沿岸の神社と神々」と題しての講座がありました。歴史には興味があるのですが、お話の中身が神社となるとちょっと抵抗を感じました。知識が全くないからです。聞いていても話について行けないんです。佐藤先生は郷土史家の方で戴いたレシピを見ると細かな部分までよく調べられているなと感心させられます。この日の話の内容は八代地域一帯には妙見信仰が根強く残っていて、日本各地にみられる諏訪信仰の形跡がほとんど見受けられない「国郡一統志・肥後国誌」と言う研究結果と何故なのか?と言う疑問です。先生の所見によると、小西行長(キリシタン大名)がこの地を統治していた時代に小西領の信仰に対しての影響を受けて諏訪信仰やその他の神社信仰が消えていった可能性があると述べられています。・・少し難しすぎて・・・
・・神社や神道について少し調べました。
神道は日本の民族信仰。日本民族の間に発生し、儒教・仏教など外来の宗教・思想などと対立しつつ、しかもその影響を受けて発達し、その精神生活の基盤となってきた民族信仰のこと、さらにその民族信仰を根底としての国民道徳、倫理、習俗までを含めていう場合もある。
神道の原初形態とみられるものは、農耕文化、稲作と大きな関係があり、弥生(やよい)式文化の時代まで進み、農耕生活が定着し始めたころに、神道の原初形態は成立したものとみられる。つまり、この国土の各地に人々が定着して共同体をつくり、農耕を始めたとき、その共同体の生活のなかで、農耕に関連してなされた祭りより神道は発したとみられるのである。
自然と深いかかわりをもった生活のなかで、具体的に接した日、月、海、山、川、木、また雷、風など自然物、自然現象などに、人力以上の威力、呪力(じゅりょく)、神聖性を感じ、それをカミとして畏敬(いけい)したことがみられる。すなわち自然崇拝的なカミであるが、これがいちばん多くみられる。次に鏡、剣、玉などにも霊力、神聖性をみての庶物崇拝的なカミ観念の存したこともみられる。
神社(じんじゃ・かむやしろ)とは、神道の信仰に基づき作られた、恒設の祭祀施設、及びその施設を中心とした祭祀儀礼・信仰を行う組織。鳥居の内の区域一帯を、神霊が鎮まる神域とみなす。神社によっては式年遷宮の習わしがあり、数年ごとに、社殿などを新しく造り替える場合もある。
古くは社殿がなくとも「神社」とした。神聖な山、滝、岩、森、巨木などに「カミ」(=信仰対象、神)が宿るとして敬い、俗(生活に活かす)の山、滝、岩、森、巨木と区別したのである。現在の社殿を伴う「神社」は、これらの神々が御神体から移し祀られた祭殿が常設化したものとされる
神社の種類と数について
神社本庁が平成2年(1990年)から平成7年(1995年)にかけて実施した「全国神社祭祀祭礼総合調査」に基づく数字では神社の数は79,335社です。ただ明治の国家統制(国家神道)によって、日本の伝統的な祭神の多くが捨てられ、「王権神話」の神への祭神変更が行われ神仏分離の処置で、本来の祭神や社の姿が現在では非常に見え難くなっているのが現状です。
もっとも数が多いのは、大分県の宇佐神宮を総本宮とする八幡信仰(八幡神社・若宮神社・八幡大神社など)です。神社数にして7,817社、なんと全体の約一割を占めています。
第二位は、4,425社を数えた伊勢信仰。ここ伊勢神宮(三重県)の皇大神宮(内宮)には皇室の 祖神 おやがみ である 天照大神 あまてらすおおみかみ が祀られています。もともとは皇室の氏神的存在でしたが、中世以降に武士による東国への勧請が盛んになり、しだいに庶民の参詣も隆盛をみせるようになりました。
三番手は天神信仰。学問の神さまとしても有名な菅原道真を崇敬の対象としています。神社数は3,953社、宗祀は京都の北野天満宮です。道真の霊威が雷に代表されることからもわかるように、初めは天候を司る神とされたが、やがて文道・詩歌、連歌の神としての性格が付与されるようになり、さらに江戸時代には、学問の神さまとして広く信仰を集めていきました。
以下、稲荷信仰(2970社)、熊野信仰(2693社)、諏訪信仰(2616社)、祇園信仰(2299社)、白山信仰(1893社)、日吉信仰(1724社)、山神信仰(1571社)--と続きます。
別の資料では
稲荷社(約19800社)、八幡社 (約14800社)、天神社(天満宮) (約10300社)、諏訪神社 (約5700社)、神明神社 (約5400社)、熊野神社(約3300社)、春日神社 (約3100社)、八坂神社 (約2900社)、白山神社 (約2700社)、住吉神社 (約2100社)、日吉(山王)神社 (約2000社)、金毘羅神社 (約1900社)、恵比寿神社 (約1500社)
とありますが上の資料が正しいのではないかと思います。
地区別祭神分布(多い祭神)
『北海道・東北』 八幡・伊勢・稲荷・熊野
『関東』 八幡・伊勢・稲荷・熊野
『北陸・甲信』 八幡・伊勢・諏訪・白山
『東海』 八幡・伊勢・白山
『近畿』八幡・春日・稲荷
『中国』 八幡・天神・稲荷
『四国』 八幡・天神・山神
『九州』 八幡・天神・熊野・貴船
所在地別神社数(沖縄を除く)
数が多い順
1 新潟 4778社 2 兵庫 3840社 3 福岡 3385社 4 愛知 3334社 5 岐阜 3227社 6 千葉 3173社 7 福島 3029社 8 静岡 2859社
9 長野 2734社 10 茨城 2464社 11 富山 2178社 12 高知 2171社 13 大分 2130社 14 埼玉 2011社・・
数が少ない順
1 和歌山(注)426社 2 大阪 568社 3 北海道 594社 4 宮崎 653社 5 青森 729社 6 山口 737社 7 鳥取 822社 8 三重 825社 9 岩手 835社 10 香川 836社 11 宮城 975社・・
(注){明治39年12月、「神社合祀令」<一町村一社を原則に神社統廃合を行なうという主旨>;三重県では6500社が1/7以下に、和歌山県では3700社が1/6以下に統合・合祀されたとされる。結果として全国ではおよそ19万社が12万社に統合されたと云う。}
◇{祭神が八幡神、天神、熊野権現、牛頭天王などを祀る社では、明治維新前までは、神社というより実態は寺院であるといったほうが適切である社が多数を占めることが見てとれる。 特に'大社'であればあるほどその傾向は強かったと思われる。
またさらに、白山、日吉、春日、愛宕、金毘羅、秋葉、石動などを加えれば、社僧・寺院が実権を握り祭祀した社あるいは寺院の鎮守的な地位であった社が大多数を占めていたことも見えてくる。 }
◇{明治の神仏分離の過程を経て、国家神道の成立で、出雲神道系などの信仰が否定され衰退し、また、多くの祭神が、地主神や氏神から「古事記」「日本書紀」などの皇統譜につながる神々に付会され、祭神変更が強引になされたケースが極めて多かったことも考えあわせると、現今、神社と称するものの多数の実態は依然として「国家神道」そのものが見事に「保存」されているというべきである。
【諏訪信仰】
諏訪大社の歴史は大変古く古事記の中では出雲を舞台に国譲りに反対して諏訪までやってきて、そこに国を築いたとあり、また日本書紀には持統天皇が勅使を派遣したと書かれています。
諏訪大社の特徴は、諏訪大社には本殿と呼ばれる建物がありません。代りに秋宮は一位の木を春宮は杉の木を御神木とし、上社は御山を御神体として拝しております。
古代の神社には社殿がなかったとも言われています。つまり、諏訪大社はその古くからの姿を残しております。
諏訪明神は古くは風・水の守護神で五穀豊穣を祈る神。また武勇の神として広く信迎され、現在は生命の根源・生活の源を守る神として御神徳は広大無辺で、多くの方が参拝に訪れます。
【妙見信仰】
妙見(ミョウケン)信仰とは、一般には仏教でいう北辰妙見菩薩(ホクシンミョウケンボサツ)に対する信仰をいうが、その原姿は、道教における星辰信仰、特に北極星・北斗七星に対する信仰である。この北辰・北斗信仰がわが国に入ったのは推古天皇のころというが、その真偽は不明。ただ、奈良・明日香の高松塚古墳の天井に北斗七星が、北壁に北斗の象徴である玄武像(ゲンブ、亀と蛇とがかみついた像)が描かれ、また正倉院御物にも金泥・銀泥で北斗七星が描かれた合子(ゴウス)があることなどからみると、奈良時代に知られていたのは確かである。
【日本三大妙見】福島の相馬妙見、大阪の能勢妙見、八代の妙見宮
795年(延暦14年)、横岳頂上に上宮を創祀。1160年(永暦元年)、中宮を建立。1186年(文治2年)に、後鳥羽天皇の勅願で、検校散位(けんぎょうさんみ)大江朝臣隆房により下宮が創建された。
1870年(明治3年)までは妙見宮と呼ばれた。妙見神とは、北極星・北斗七星の象徴である。神道と仏教の両部の宮寺で、広く崇敬を受け、八代、下益城、芦北三郡の一の宮として栄えた。1871年(明治4年)、神仏分離令により、天之御中主神、国常立尊を祭神とし、社名を八代神社と改められ、県社となった。

この神社は福正元町にある少名彦命神社です。

この看板にこの神社が天正16年(1588)頃小西行長によって破却されたとあります。この時期八代の神社や仏閣はほとんど焼き討ちされたようですが、現存するものは加藤清正の時代に再興されたものが多いようです。たまたま頭に残っていたので写真を調べてみるとこの資料が出てきました。
Posted by マー君 at
17:28
│Comments(0)

暦には8月23日処暑とありますが・・・
●「処暑」とは - 二十四節気 : 立秋→処暑→白露 二十四節気の一つ。旧暦七月(文月)の 中気。 暑さが峠を越えて後退し始める頃。毎年8月23~24日頃。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の白露前日までである。
●処暑とは、暑さが終わるという意味です。
まだ昼間は暑い日が続きますが、朝夕は涼しい風が吹き渡わたり、気持ちのよい時期です。
また、この頃には秋の台風が訪れます
夏の暑さに陰りが見えはじめる頃。
●「処暑」とは、暑気が止むという意味。
萩の花が咲き、夕方には赤とんぼが飛び回ります。朝夕には心地よい涼風が吹くなど、次第に秋の気配が増し、残り少ない夏への恋しさが募る時期でもあります。また、柿や梨、林檎、葡萄などの果実がたわわに実り「食欲の秋」の到来を告げます。
・・・???今年は少し違う様な気がします。・・白露前日までの期間で捉えるとこの季節を上手く捉えているのかも知れませんね。
皆様はどう思われますか。
25日 朝晩は確かに涼しくなりましたが、各地での記録的大雨は気に成ります。


矢嶋楫子 やじまかじこ ・・熊本の凄い人、しかも女性この人ほど米国の新聞を賑わした人は今だかって居ないそうです。70歳を過ぎてから渡米し、米国で爆発的な人気を巻き起こしました。しかも英語は喋れなかったそうです。
2013・08・21 熊本県民カレッジリレー講座 「世界の矢嶋楫子」 熊本学園大学教授 米岡ジュリ氏のお話より・・
天保(てんぽう)4年4月24日肥後国上益城郡津森村杉堂(現・熊本県上益城郡益城町)の惣庄屋矢島忠左衛門直明・母鶴の1男7女の6女(末子)に生まれ、かつと命名された。極端な男性社会にあって度重なる女児の誕生は歓迎されず、名付け親は10歳違いの姉である三女・順子であった。順子(竹崎順子)は、横井小楠の高弟である竹崎茶堂と結婚し、熊本女学校校長となった教育者である。また、順子のすぐ下の姉・久子(徳富久子)も同じく横井小楠の高弟である徳富一敬と結婚し、徳富蘇峰・徳冨蘆花の兄弟を生んでいる。蘇峰は明治、大正、昭和にかけての大論客、蘆花は明治、大正の文豪である。また、かつのすぐ上の姉つせ子(横井つせ子)は横井小楠の後妻となった。この姉妹4人は「肥後の猛婦」、「四賢婦人」と呼ばれた。一本気で不器用な熊本男児の気質を表す「肥後もっこす」。熱く頑固なこの気質は女性にも共通し、「肥後の猛婦」という言葉は戦後、大宅壮一が作り出した。
◎竹崎順子(1825-1905)矢島家3女で、熊本女学校(現・熊本フェイス学院高等学校)を創立した女子教育の先覚者。
◎徳富久子(1829-1919)同家4女で、徳富家に嫁し蘇峰、蘆花の母。楫子の矯風事業を援助した。
◎横井つせ子(1831-1894)同家5女で小楠の妻となるが実際は「妾」同然。夫を「殿」、わが子を「さん」付けし、子供からは「お乳」と呼ばれた。
◎矢島楫子 やじま-かじこ (1833-1925)矢島家6女で、明治-大正時代の教育者,社会事業家。
●湯浅初子(1860-1935)蘇峰、蘆花の姉。日本で最初の男女共学を受けた。禁酒・廃娼運動家。
●海老名みや子(1862-1935)小楠の長女。同志社設立に奔走。夫は海老名弾正。
●徳富愛子(1874-1947)蘆花夫人。夫と作家活動、「蘆花全集」を出版。
●久布白落実(1882-1972)蘇峰らの姪。廃娼、婦人参政権運動に尽力
「★5女つせ子と横井小楠の息子横井時雄が、山本覚馬の娘みねと夫婦になる。覚馬の妹八重は新島襄と夫婦」
矢島楫子
女子教育者、社会改良家。25歳で結婚、1男2女をもうけたが、35歳のとき離婚して矢島家に帰る。1872年(明治5)上京、40歳にして教員伝習所に学び、1876年新栄女学校教師となり、翌1877年受洗。1889年桜井女学校、新栄女学校が合併して女子学院となるや院長に就任、1914年(大正3)退職までキリスト教に基づいた教育によって多くの子女を訓育した。東京婦人矯風会(きょうふうかい)(1886)、日本キリスト教婦人矯風会(1893)を組織して会長となり、第7回矯風会世界大会(1906 73歳のとき)出席のため渡米し、ルーズベルト大統領に会見するなど、女性運動、社会改良事業に尽力。大正10年89歳の高齢でワシントン平和会議に出席の際、米ハーディング大統領より記念の花器を贈られ、その功を称えられた。大正14年6月16日死去。93歳。 ・・・矢嶋家って本当に凄い家系です。熊本の誇り。
益城町大字上陳436 4賢婦人記念館 入館料 無料
暦では8月21日(水)は旧盆とありますが?・・・8月のお盆(旧盆の時期)について。この宗教的行事を仏教だけのものと思いがちですが、お盆の行事は日本古来からの先祖祭りと、外来仏教の盂蘭盆が混交して現在の形になったと云われています。
8月のお盆や、旧盆の時期となると少し複雑になりますが、8月に行われる場合は月遅れの盆となり、必ずしも旧暦7月15日の日にちと合致するものではありません。
旧盆=陰暦で行う盂蘭盆(うらぼん) 祖先の霊を祀る一連の行事・・仏教行事としてのお盆と一般に言われるお盆とは人により、また地方によっては少々受け取られ方は違う様です。
日本のお盆の儀礼は伝統的に、旧暦7月15日に行われてきましたが、明治になり、日本でも新暦が採用されたため、それ以降、統一されず地方によって時期が異なるお盆を行なって来ました。
(お盆の時期)
・旧暦7月15日 ⇒伝統通り昔のまま(旧盆)。年度で日付が変わる。
・新暦7月15日 ⇒もしくは前後の土日。
・新暦8月15日 ⇒月遅れの盆。これを旧盆とも云うので複雑化した。
※その他に8月1日のお盆などもあります。
明治になってからは、旧暦盆の廃止の勧告を行うことなどもあり、旧暦7月15日の伝統派は少なくなり、全国的には旧暦の日にちに近い、8月の月遅れのお盆、いわゆる旧盆が多いようです。
8月のお盆が多い事には、農作業や、お供え物も大きく影響していると思われます。新暦のお盆では、祖霊に季節の初物をお供えすると云う習慣的にも、農作業の日程的にも、新暦のお盆である現在の7月15日では都合が良くないのです。そこで月遅れの8月のお盆が多勢を占めるようになって行ったのではないでしょうか。
メディアなどでも、現在では8月のお盆を指す様になり、「おぼん」と云えば、月遅れのお盆を云う事になりつつあります。

8月のお盆や、旧盆の時期となると少し複雑になりますが、8月に行われる場合は月遅れの盆となり、必ずしも旧暦7月15日の日にちと合致するものではありません。
旧盆=陰暦で行う盂蘭盆(うらぼん) 祖先の霊を祀る一連の行事・・仏教行事としてのお盆と一般に言われるお盆とは人により、また地方によっては少々受け取られ方は違う様です。
日本のお盆の儀礼は伝統的に、旧暦7月15日に行われてきましたが、明治になり、日本でも新暦が採用されたため、それ以降、統一されず地方によって時期が異なるお盆を行なって来ました。
(お盆の時期)
・旧暦7月15日 ⇒伝統通り昔のまま(旧盆)。年度で日付が変わる。
・新暦7月15日 ⇒もしくは前後の土日。
・新暦8月15日 ⇒月遅れの盆。これを旧盆とも云うので複雑化した。
※その他に8月1日のお盆などもあります。
明治になってからは、旧暦盆の廃止の勧告を行うことなどもあり、旧暦7月15日の伝統派は少なくなり、全国的には旧暦の日にちに近い、8月の月遅れのお盆、いわゆる旧盆が多いようです。
8月のお盆が多い事には、農作業や、お供え物も大きく影響していると思われます。新暦のお盆では、祖霊に季節の初物をお供えすると云う習慣的にも、農作業の日程的にも、新暦のお盆である現在の7月15日では都合が良くないのです。そこで月遅れの8月のお盆が多勢を占めるようになって行ったのではないでしょうか。
メディアなどでも、現在では8月のお盆を指す様になり、「おぼん」と云えば、月遅れのお盆を云う事になりつつあります。


クリックすれば写真は大きくなります
夜香木 やこうぼく Cestrum nocturnum/ヤコウカ 夜香花/夜香樹・・わたしはてっきりイエライシャンと思っていましたが・・
この写真は散歩の途中で松高小学校の近くの民家に咲いていたものを撮らせて戴いたものですが、興味が有る方は坂本のクレヨンの奥の元湯に行けば中庭に同じものが有ると思います。
聞いた事は有ると思うのですが、夜になると白く(レモン色)筒状に開花する花に香りがすることから、夜香木と呼ばれています。夜中に花びらを少し開らかせ、あたり一面いいにおいを放ちます。そして朝に成ると花は閉じてしまいます。花そのものは美しいものではありませんが、夜に放つにおいはいい香りがします。昼間は花は萎んで、においもありません。
イエライシャン、「夜来香(いえらいしゃん)」とは和名「トンキンカズラ(東京葛)Telosma cordata、ガガイモ科テロスマ属の常緑つる性低木で、上の写真とは別の植物。・・つる性なんですね。

今年の4月より県の松橋収蔵庫の現地講座「くまもとの大地の成り立ち」担当・川路芳弘氏に参加しています。8月11日(日)は竜門ダム付近の八方ヶ岳南方菊池市上虎口周辺山地斜面にて安山岩や玄武岩そして花こう岩の採集を行いました。座学ではないので、日頃経験のない山登りもあります。車でいけない所は歩きます。きついです。慣れないと足がパンパンになります。足には自信はあったのですが、このグループの人達には負けました。みんな元気です、歯が立ちません女の方もいるのに・・。現地で飛び交う言葉がまたあまり解らない。・・と言う事で少し勉強不足を補う事にしました。
これは中学生程度の地質学の知識の一部らしいのだが・・
火成岩は、できる過程のちがいで、2つに分けられます。
火山岩と深成岩 マグマは高温ですが、冷えると岩石になります。
火山岩・・地表や地表に近いところでできる マグマが急に冷えて固まったもの・・斑状組織 (石基の中に斑晶が混ざっている)石基…急に冷やされたため、結晶になりそこなったガラス質や小さな結晶の集まり 斑晶…比較的大きな結晶・・・ 流紋岩・安山岩・玄武岩
深成岩・・地下の深いところでできる マグマがゆっくり冷えて固まったもの・・等粒状組織 (同じような大きさの結晶が集まっている)ゆっくり冷えたため、大きな結晶ができます。・・花こう岩・せん緑岩・斑れい岩

ようけつぎょうかいがん【溶結凝灰岩 】
火砕流堆積物は急速かつ多量に積もると,高温の軽石や火山灰の粒子どうしが塑性変形して堆積物自身の重さで押しつぶされる。こうして冷却後は緻密な溶岩に近い固さをもった溶結凝灰岩ができる。しかし火砕流堆積物の基底部では冷却が速いため溶結しにくい。 火砕流堆積物は元の尾根や谷のある地形を埋めて,表面が平坦で広大な台地をつくるが,溶結現象がおこると厚さの厚い,谷を埋めた部分ほど溶結による押しつぶされ方が大きいため,堆積物の表面が低くなり,この部分に再び河川ができて浸食が始まる。
火山噴火の際、火砕流のような形で高温の火山灰、軽石、岩滓などが大量に厚く堆積すると、高熱と自重による圧力のため溶結作用がおこって緻密、偏平な岩塊をつくる。岩質としては石英安山岩質ないし流紋岩質であることが多い。このようにしてできた溶結凝灰岩はかなり大規模に分布し、垂直に近い崖(がけ)や柱状節理の発達のためみごとな景観を示す。日本では十和田湖(青森・秋田県)周辺、大雪山の層雲峡(北海道)、阿蘇(あそ)(熊本県)などに分布する。

道路に向き出た溶結凝灰岩 阿蘇4と言う年代・約8〜9万年前に阿蘇カルデラから噴出した
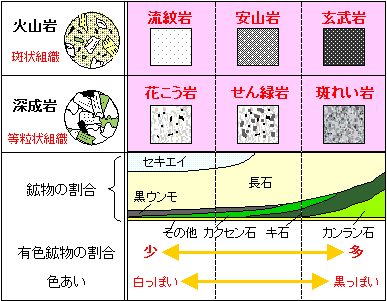
覚え方、「借り上げの新幹線速い」 か(火山岩)り(流紋岩)あ(安山岩)げ(玄武岩)のしん(深成岩)か(花こう岩)んせん(せん緑岩)は(斑れい岩)やい
硬さ・・ かたい←セキエイ・カンラン石>長石・カクセン石・キ石>黒ウンモ→やわらかい ・・ 少しは復讐が出来たかな?
これは中学生程度の地質学の知識の一部らしいのだが・・
火成岩は、できる過程のちがいで、2つに分けられます。
火山岩と深成岩 マグマは高温ですが、冷えると岩石になります。
火山岩・・地表や地表に近いところでできる マグマが急に冷えて固まったもの・・斑状組織 (石基の中に斑晶が混ざっている)石基…急に冷やされたため、結晶になりそこなったガラス質や小さな結晶の集まり 斑晶…比較的大きな結晶・・・ 流紋岩・安山岩・玄武岩
深成岩・・地下の深いところでできる マグマがゆっくり冷えて固まったもの・・等粒状組織 (同じような大きさの結晶が集まっている)ゆっくり冷えたため、大きな結晶ができます。・・花こう岩・せん緑岩・斑れい岩

ようけつぎょうかいがん【溶結凝灰岩 】
火砕流堆積物は急速かつ多量に積もると,高温の軽石や火山灰の粒子どうしが塑性変形して堆積物自身の重さで押しつぶされる。こうして冷却後は緻密な溶岩に近い固さをもった溶結凝灰岩ができる。しかし火砕流堆積物の基底部では冷却が速いため溶結しにくい。 火砕流堆積物は元の尾根や谷のある地形を埋めて,表面が平坦で広大な台地をつくるが,溶結現象がおこると厚さの厚い,谷を埋めた部分ほど溶結による押しつぶされ方が大きいため,堆積物の表面が低くなり,この部分に再び河川ができて浸食が始まる。
火山噴火の際、火砕流のような形で高温の火山灰、軽石、岩滓などが大量に厚く堆積すると、高熱と自重による圧力のため溶結作用がおこって緻密、偏平な岩塊をつくる。岩質としては石英安山岩質ないし流紋岩質であることが多い。このようにしてできた溶結凝灰岩はかなり大規模に分布し、垂直に近い崖(がけ)や柱状節理の発達のためみごとな景観を示す。日本では十和田湖(青森・秋田県)周辺、大雪山の層雲峡(北海道)、阿蘇(あそ)(熊本県)などに分布する。

道路に向き出た溶結凝灰岩 阿蘇4と言う年代・約8〜9万年前に阿蘇カルデラから噴出した
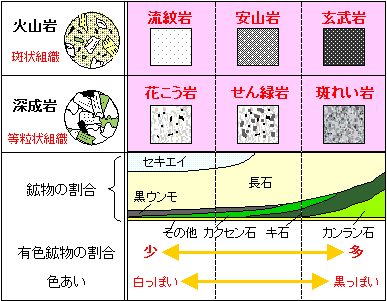
覚え方、「借り上げの新幹線速い」 か(火山岩)り(流紋岩)あ(安山岩)げ(玄武岩)のしん(深成岩)か(花こう岩)んせん(せん緑岩)は(斑れい岩)やい
硬さ・・ かたい←セキエイ・カンラン石>長石・カクセン石・キ石>黒ウンモ→やわらかい ・・ 少しは復讐が出来たかな?
仏教伝来以前 7月7日 七夕[たなばた] 七夕の節句旧暦の7月15日の夜に戻って来る祖先の霊に着せる衣服を機織して棚に置いておく習慣があり、棚に機で織った衣服を備えることから「棚機[たなばた]」という言葉が生まれた。その後仏教が伝来すると、7月15日は仏教上の行事「盂蘭盆(盆)うらぼん」となり、棚機は盆の準備をする日ということになって7月7日に繰り上げられた。これに中国から伝わった織女・牽牛の伝説が結び附けられ、天の川を隔てた織姫(織女星、こと座のベガ)と彦星(牽牛星、わし座のアルタイル)が年に一度の再会を許される日とされた。
『日本の七夕祭りの由来』・・七夕(たなばた)は、平安時代には「乞巧奠(きこうでん)」とも呼び、宮中や貴族の家庭で広く行われた年中行事です。
日本の七夕の起源は、乞巧奠(きこうでん)・陰暦7月7日の行事。女子が手芸・裁縫などの上達を祈ったもの。もと中国の行事・だけではありません。日本では、毎年7月7日に「棚機女(タナバタツメ)」という巫女が水辺で神の降臨を待つ という民間信仰とむすびついた行事があります。
日本の七夕は、この「タナバタツメ」と、中国の乞巧奠とが合体したものだという説が 有力です。ちなみに乞巧奠は、平安時代の貴族たちが中国の風習を真似て導入していた ようで、その後乞巧奠が民間に流れていき、次第に「タナバタツメ」と合わさっていった のでしょう。
民俗調査などでは、七夕がお盆(旧7月15日)を迎えるための準備としての意味をもつ (七夕盆)場合や、農業の豊作を願う意味で行う場合など、様々な意味合いを持っている 場合があります。これは後世になって民間のいろんな行事と混ざり合っていて、出来上 がったものだと思われます。


下の浮世絵は『市中繁栄七夕祭』(名所江戸百景の一つ。歌川広重)
今年は特別暑いお盆に成りそう。
『日本の七夕祭りの由来』・・七夕(たなばた)は、平安時代には「乞巧奠(きこうでん)」とも呼び、宮中や貴族の家庭で広く行われた年中行事です。
日本の七夕の起源は、乞巧奠(きこうでん)・陰暦7月7日の行事。女子が手芸・裁縫などの上達を祈ったもの。もと中国の行事・だけではありません。日本では、毎年7月7日に「棚機女(タナバタツメ)」という巫女が水辺で神の降臨を待つ という民間信仰とむすびついた行事があります。
日本の七夕は、この「タナバタツメ」と、中国の乞巧奠とが合体したものだという説が 有力です。ちなみに乞巧奠は、平安時代の貴族たちが中国の風習を真似て導入していた ようで、その後乞巧奠が民間に流れていき、次第に「タナバタツメ」と合わさっていった のでしょう。
民俗調査などでは、七夕がお盆(旧7月15日)を迎えるための準備としての意味をもつ (七夕盆)場合や、農業の豊作を願う意味で行う場合など、様々な意味合いを持っている 場合があります。これは後世になって民間のいろんな行事と混ざり合っていて、出来上 がったものだと思われます。


下の浮世絵は『市中繁栄七夕祭』(名所江戸百景の一つ。歌川広重)
今年は特別暑いお盆に成りそう。

広重の浮世絵「東海道五十三次 日本橋」の絵です。良く見ると、鰹を前後に担った男、そしてその後ろに「剣菱」の商標の付いた樽を担いでいる二人の男が描かれています。江戸の国学者平田篤胤の著書の中に「・・・極楽よりは此の世が楽しみだ 美濃米を飯にたいて 鰻茶漬 初堅魚に剣菱の酒を呑み・・・」とあるように、その当時は初鰹を肴に剣菱を呑むのが極楽とされていた。
話は鰹の話ではなく、「剣菱」の樽のほうで、剣菱は灘のお酒です。この絵はお酒が上方からくだって、日本橋を通って江戸に運ばれるところを描いています。橋の上を見ると色々な物が江戸に運ばれています。当時は京都に天皇が居られたので、上方は京都方面を指します。しかし江戸には幕府が有り、町としては日本一、上方に江戸からの注文は絶えません。つまり下るものと下らないものが出来てきます。下るものは値打ちが有り江戸の人達に好まれるもの、下らないものは値打ちが無い、つまらないもの・・・「くだらない」の語源はこんな処に有りました。日本語って面白いと思いませんか?
くまもと県民カレッジリレー講座 「浮世絵に描かれた江戸時代の食文化」 東海大学准教授 新田時世氏のお話より

普段当たり前のように使っている言葉、小さい頃からずっと使っている言葉、でも本当の意味はつい最近知りました。「午前」、「午後」??何故「ごぜん」、「ごご」なのか?午の前、午の後 午=うま うまの前と後の事。今の時は、午前の12時間、午後の12時間、併せて24時間で一日を区切っている。然し、こうなったのは明治以後で、それ迄は丑の刻とか巳の刻とかと言った、十二支を使っていた。
午前0時・・・子(ね)の刻・・・・九つ 23:00~1:00
午前2時・・・丑(うし)の刻・・・八つ 1:00~3:00
午前4時・・・寅(とら)の刻・・・七つ 3:00~5:00
午前6時・・・卯(う)の刻・・・・六つ 5:00~7:00
午前8時・・・辰(たつ)の刻・・・五つ 7:00~9:00
午前10時・・巳(み)の刻・・・・四つ 9:00~11:00
午後0時・・・午(うま)の刻・・・九つ 11:00~13:00
午後2時・・・未(ひつじ)の刻・・八つ 13:00~15:00
午後4時・・・申(さる)の刻・・・七つ 15:00~17:00
午後6時・・・酉(とり)の刻・・・六つ 17:00~19:00
午後8時・・・戌(いぬ)の刻・・・五つ 19:00~21:00
午後10時・・亥(い)の刻・・・・四つ 21:00~23:00
と言ったようになる。0時が九つで2時間経つと1つ減る。そうして四つでお終い、三つというのはない。
明治になるまでは朝、太陽が出る時を午前6時、つまり明け六つ、夕方、太陽が沈む時を午後6時、つまり暮れ六つとして昼間も夜もそれを6等分した。お昼の十二時のことを「正午」といいますが、これは午の刻の真ん中と言う意味。
熊本県民カレッジリレー講座 東海大学 新田時世准教授のお話より 2013・8・7
この鏡にも上のような意味の絵が描かれていたのかな?

卑弥呼が貰った鏡 景初三年銘の三角縁神獣鏡「魏志倭人伝の中に魏王が邪馬台国の卑弥呼に100枚贈ったとされる鏡」

暦の上では立秋とは言え暑さは残暑((ざんしょ)立秋から秋分までの暑さのこと。)どころか今からが本番と言えるような今年の夏です。今年の異常気象どうなっているんだろう?「立秋とは名ばかりのこの暑さ」と言う事でやっぱり暑いのが正しいらしい。
立秋とは・・8月8日頃(2013年は8月7日)。および処暑までの期間。 太陽黄径135度。大暑から数えて15日目頃。朝夕が涼しくなり、秋の気配が立つ日。立春からちょうど半年が経過し、この日から立冬の前日までが秋。暦の上では秋になりますが、日中はまだ残暑が厳しく、1年で最も気温が高くなる時期です。この頃は、月遅れのお盆を前に各地で夏祭りが開催されます。・・・ということでやっぱり暑さは続きそう。・・・この日から、残暑見舞いになります。 残暑が厳しくても、出すのは8月末まで。 大暑→立秋→処暑→二百十日と暦は続きます。
立秋の雲の動きのなつかしき /虚子 暦の上でも俳句の季語も秋なんだけど???

記憶の片隅に残っていた調子のいい言葉「うんた、わに、きょうさん」、古代出雲歴史博物館でその意味を確認しました。平安時代の教科書に有った当時の建物の高さの順位を表す言葉です。うんた=雲太、わに=和二、きょうさん=京三・・・1位の「雲太」とは出雲大社本殿のことで一番高く、ついで2位の「和二」は東大寺大仏殿で、3位の「京三」は京都御所の大極殿の順ということです。写真は博物館に展示されている(縮尺10分の1)で造られた当時の出雲大社・高層神殿の模型です。48メートルほどあったと言われています。次の写真は博物館の中央ロビーに展示されている宇豆柱(うづばしら)の出土品。出雲大社境内遺跡で平成12年(2000)、出雲大社拝殿の北側で、巨大な3本ひと組の柱根が発掘されました。直径約1.35mの杉の柱を3本束ねた形状の宇豆柱(うづばしら)で、鎌倉初期の造営と推定されています。その後、柱材の科学分析調査や、考古資料・絵画、文献記録などの調査などから、この柱は、鎌倉時代前半の宝治2年(1248年)に造営された本殿を支えていた柱である可能性が極めて高くなったと言う事です。



写真はクリックすると大きくなります。
Posted by マー君 at
10:08
│Comments(0)

土用の丑の日(どようのうしのひ)は、土用の間のうち十二支が丑の日である。8月3日は丑の日
夏の土用の丑の日のことを言うことが多い。夏の土用には丑の日が年に1日か2日(平均1.57日)あり、2日ある場合はそれぞれ一の丑・二の丑という。・・・土用の丑の日のうち、18日間として考えると土用入りの日から6日以内に丑の日があって、もう一度丑の日が巡って来た場合の2回目の土用の丑の日のこと。
土用の丑の日は暦で言えばちょうど節目に当たるので、 新しい期間に入る為に体力を付けて乗り切ろうと滋養強壮が強いうなぎを食べる意味合いも重なり「土用の丑の日はうなぎ」が習慣になっているそうです。一般的には「うなぎ」は一の丑の日に食べるとされている様ですが、今年は梅雨明けが早くて何しろ暑い、「うなぎ」にはビタミンA・ビタミンEなど栄養が豊富なので、真夏や季節の変わり目に食べるのは理にかなっています二の丑おおいに「うなぎ」を食べましょう。来年の夏は丑の日は1回だけしかありません。

暦に今日は八朔との記述が有りましたのでちょっと調べてみました。
八朔(はっさく)とは八月朔日(ついたち)の略で、旧暦の8月1日のこと。
この頃、早稲の穂が実るので、農民の間で初穂を恩人などに贈る風習が古くからあった。このことから、田の実の節句ともいう。この「たのみ」を「頼み」にかけ、武家や公家の間でも、日頃お世話になっている(頼み合っている)人に、その恩を感謝する意味で贈り物をするようになった。
熊本の八朔祭(はっさくまつり)
熊本県上益城郡山都町の浜町では、野山の自然素材を豊富に使った巨大な「造り物」が名物の「八朔祭」が、旧暦に合わせて、毎年、9月第一土日・二日間にわたって開催されている。この祭りは江戸時代中期から始まったとされ、田の神に感謝し、収穫の目安を立てる日とされ、NHKなど全国ニュースにも毎年取り上げられているほど有名な祭りである。
是非みんなで見に行って祭りを盛り上げましょう!



