
●年越しとは・・
新年を迎える夜の行事。普通は大晦日(おおみそか)の夜であるが,立春・七日正月・十五日正月の前夜をいうこともある。年神を迎えるために物忌(ものいみ)をし,終夜起きているのが古い形であった。〈としとり〉と称して特定の食事をする例があり,年越そばもその一つである。
●大祓(おおはらえ)とは・・
人々の罪やけがれを祓い清める神事。中古以降、6月と12月の晦日みそかを恒例とし、臨時に大嘗祭の前後、疫病・災害などの際にも行なった。現在でも宮中や神社の年中行事の一つとなっている。おおはらい。
●大晦日とは・・
大晦日(おおみそか)は、1年の最後の日。天保暦(旧暦)など日本の太陰太陽暦では12月30日、または12月29日である。現在のグレゴリオ暦(新暦)では12月31日。翌日は新年(1月1日)である。大つごもりともいう。日本では、年神を迎えることにちなむ行事が行われる。 旧暦では毎月の最終日を晦日(みそか)といった。晦日のうち、年内で最後の晦日、つまり12月(または閏12月)の晦日を大晦日といった。元々“みそ”は“三十”であり、“みそか”は30日の意味だった。ただし、月の大小が年によって変動するので、実際には29日のこともあった。後の新暦の12月31日を指すようになった。
※いいお年を
今日は言葉のお勉強。
いつも使っている言葉だがその言葉の由来や語源が分からない。
そんな言葉っていっぱいありますよね。
その中から・・
「ややこしい」は、こみいって分かりにくい、複雑で面倒だ、厄介だ、紛らわしい、などの意味である。西日本の地域でよく用いられる言葉である。

関西地方などでは「赤ちゃん」「赤ん坊」のことを「ややこ」という。赤ちゃんは可愛いが、時に泣き出す。まだ言葉が話せず、なぜ泣いているのか分からないことも多く、赤ちゃんの世話は難しい面もある。その世話のわずらわしさから、複雑で面倒だ、などの意味になったとされる。
ややこしい問題、ややこしい道、説明がややこしくて分からない、今日の天気はややこしい、などのように使われる。
「ややこ」は漢字では「稚児」または「嬰児」と書く。「ややこ」の語源は、小さい子、次第に大きくなる子という意味の「漸漸(やうやう)子」に由来する説や、泣き声の「ヤヤ」から「ヤヤと泣く子」に由来する説がある。
また、「赤ちゃん」の対義語は「大人」であり、これに由来して「ややこしい」の対義語は「大人しい」である。「大人しい」は、性質や態度が穏やかで素直だ、落ち着いて静かだ、大胆さがあまり感じられない、などの意味である。
雑学ネタ帳より
いつも使っている言葉だがその言葉の由来や語源が分からない。
そんな言葉っていっぱいありますよね。
その中から・・
「ややこしい」は、こみいって分かりにくい、複雑で面倒だ、厄介だ、紛らわしい、などの意味である。西日本の地域でよく用いられる言葉である。

関西地方などでは「赤ちゃん」「赤ん坊」のことを「ややこ」という。赤ちゃんは可愛いが、時に泣き出す。まだ言葉が話せず、なぜ泣いているのか分からないことも多く、赤ちゃんの世話は難しい面もある。その世話のわずらわしさから、複雑で面倒だ、などの意味になったとされる。
ややこしい問題、ややこしい道、説明がややこしくて分からない、今日の天気はややこしい、などのように使われる。
「ややこ」は漢字では「稚児」または「嬰児」と書く。「ややこ」の語源は、小さい子、次第に大きくなる子という意味の「漸漸(やうやう)子」に由来する説や、泣き声の「ヤヤ」から「ヤヤと泣く子」に由来する説がある。
また、「赤ちゃん」の対義語は「大人」であり、これに由来して「ややこしい」の対義語は「大人しい」である。「大人しい」は、性質や態度が穏やかで素直だ、落ち着いて静かだ、大胆さがあまり感じられない、などの意味である。
雑学ネタ帳より
今日は椋鳩十さんの教育者としての生き方について2日前の【春秋】から拾い上げてみました。

鹿児島県で高校教師や図書館長を務めつつ動物文学を執筆した椋鳩十(むくはとじゅう)。文学を志したのは中学時代の若き恩師2人の影響という
▼早稲田大を出たての国語教師は教室でトルストイを読み聞かせ、文学へいざなった。椋が70代半ばで全集を出版すると、60年も保管していた椋の中2の作文と絵を送ってくれた
▼東京帝大生のまま着任した英語教師は、椋ら文学好きの生徒10人を「またたく星の群れ」と名付けた。放課後にガリ版で刷った英文の詩を訳し、「生きた心で自然を見よ」と説いた
▼こんなふうに若者を光へと導くのが教師であろうが、今はなり手不足が深刻。昨年度の公立小学校教員採用試験の競争率がバブル期と並び過去最低になった。九州では福岡県1・3倍、佐賀県1・6倍の低さ。教員の質の確保が心配になる
▼背景にはいじめや過激な保護者への対応の負担もあろう。何より、部活動の指導や採点でいくら残業をしても残業代が支払われない変な法律が存在する。これでは先生があまりにかわいそうだ
▼それでも自分は教えたいという若者にこの逸話を。1987年末、病床の椋に富山の小学教諭から手紙が。椋の作品の解釈を巡り児童の意見が割れ困っているという。椋は「今なら2学期に間に合う」と無理を押して返信し、間もなく逝く。動かしたのは教育者としての誇りか情熱か。きょうは教師の在り方を考えさせられる椋の命日である。
むくはとじゅう【椋鳩十】
作家・脚本・エッセイスト
[1905~1987]児童文学作家。長野の生まれ。本名、久保田彦穂 (ひこほ) 。自然や野生動物をテーマとする作品を多く書いた。作「片耳の大鹿」「孤島の野犬」「大造じいさんとガン」など。
出生地
長野県下伊那郡喬木村阿島
生年月日
1905年1月22日 みずがめ座
没年月日
1987年12月27日(享年82歳)

鹿児島県で高校教師や図書館長を務めつつ動物文学を執筆した椋鳩十(むくはとじゅう)。文学を志したのは中学時代の若き恩師2人の影響という
▼早稲田大を出たての国語教師は教室でトルストイを読み聞かせ、文学へいざなった。椋が70代半ばで全集を出版すると、60年も保管していた椋の中2の作文と絵を送ってくれた
▼東京帝大生のまま着任した英語教師は、椋ら文学好きの生徒10人を「またたく星の群れ」と名付けた。放課後にガリ版で刷った英文の詩を訳し、「生きた心で自然を見よ」と説いた
▼こんなふうに若者を光へと導くのが教師であろうが、今はなり手不足が深刻。昨年度の公立小学校教員採用試験の競争率がバブル期と並び過去最低になった。九州では福岡県1・3倍、佐賀県1・6倍の低さ。教員の質の確保が心配になる
▼背景にはいじめや過激な保護者への対応の負担もあろう。何より、部活動の指導や採点でいくら残業をしても残業代が支払われない変な法律が存在する。これでは先生があまりにかわいそうだ
▼それでも自分は教えたいという若者にこの逸話を。1987年末、病床の椋に富山の小学教諭から手紙が。椋の作品の解釈を巡り児童の意見が割れ困っているという。椋は「今なら2学期に間に合う」と無理を押して返信し、間もなく逝く。動かしたのは教育者としての誇りか情熱か。きょうは教師の在り方を考えさせられる椋の命日である。
むくはとじゅう【椋鳩十】
作家・脚本・エッセイスト
[1905~1987]児童文学作家。長野の生まれ。本名、久保田彦穂 (ひこほ) 。自然や野生動物をテーマとする作品を多く書いた。作「片耳の大鹿」「孤島の野犬」「大造じいさんとガン」など。
出生地
長野県下伊那郡喬木村阿島
生年月日
1905年1月22日 みずがめ座
没年月日
1987年12月27日(享年82歳)
今日はこんな日・・
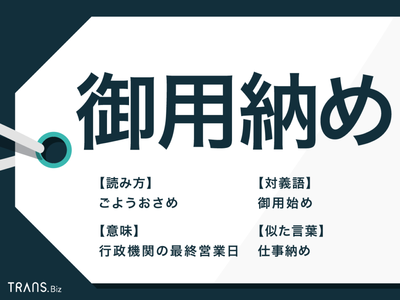
官公庁では「御用納め」とも呼ばれ、年末年始の休日を前にその年の最後の事務を執ることを意味する。また、多くの民間企業でもこの日が「仕事納め」となる。
古くは1873年(明治6年)から、官公庁は12月29日から1月3日までを休暇とすることが法律で定められており、12月28日が最後の業務日であり「仕事納め」となる。現在では1988年(昭和63年)の「行政機関の休日に関する法律」により定められている。
通常は12月28日であるが、この日が土曜日・日曜日の場合は直前の金曜日となり、それぞれ12月27日(金)、12月26日(金)が「仕事納め」となる。また、裁判所については「裁判所の休日に関する法律」、地方公共団体については「条例」において定められている。
通常は1月4日が「御用始め・仕事始め」の日となる。官公庁や企業において、年末に「仕事納め式」、年始に「仕事始め式」が実施される場合もある。一方で、近年では「働き方改革」の一環として、年末年始に連続休暇が取りやすいように、これらの式を廃止する動きも見られる。
●「御用納め」と似た言葉に「仕事納め」があります。
「仕事納め」は一般の民間企業で使われる言葉、「御用納め」と「仕事納め」の違いは仕事納め」は一般の民間企業で「その年の最後の営業日」を指すため仕事の最終日であるという点では「御用納め」と変わりはありません。官公庁や役所などの行政機関か一般の民間企業かによるということです。でも前文にもあるように「仕事納め」については多様に使われるようです。
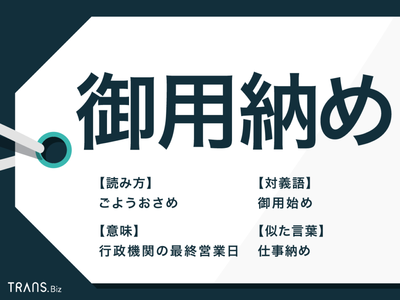
官公庁では「御用納め」とも呼ばれ、年末年始の休日を前にその年の最後の事務を執ることを意味する。また、多くの民間企業でもこの日が「仕事納め」となる。
古くは1873年(明治6年)から、官公庁は12月29日から1月3日までを休暇とすることが法律で定められており、12月28日が最後の業務日であり「仕事納め」となる。現在では1988年(昭和63年)の「行政機関の休日に関する法律」により定められている。
通常は12月28日であるが、この日が土曜日・日曜日の場合は直前の金曜日となり、それぞれ12月27日(金)、12月26日(金)が「仕事納め」となる。また、裁判所については「裁判所の休日に関する法律」、地方公共団体については「条例」において定められている。
通常は1月4日が「御用始め・仕事始め」の日となる。官公庁や企業において、年末に「仕事納め式」、年始に「仕事始め式」が実施される場合もある。一方で、近年では「働き方改革」の一環として、年末年始に連続休暇が取りやすいように、これらの式を廃止する動きも見られる。
●「御用納め」と似た言葉に「仕事納め」があります。
「仕事納め」は一般の民間企業で使われる言葉、「御用納め」と「仕事納め」の違いは仕事納め」は一般の民間企業で「その年の最後の営業日」を指すため仕事の最終日であるという点では「御用納め」と変わりはありません。官公庁や役所などの行政機関か一般の民間企業かによるということです。でも前文にもあるように「仕事納め」については多様に使われるようです。
今日は寒天のお話・・
寒天発祥の日(12月27日 記念日)
京都府京都市に事務局を置く「伏見寒天記念碑を建てる会」が制定。
日付は、現在の暦で12月末頃に初めての「寒天」の元となるトコロテンが京都市伏見区御駕籠町(おかごちょう)で島津藩に提供されたと資料から推察できることとから12月。伏見=ふしみ(243)を「24+3=27」と見立てて27日。この月と日を組み合わせて12月27日とした。
京都の伏見が「寒天発祥の地」であることをアピールし、御駕籠町近辺に記念碑を建て、啓発活動を行いながら寒天の発祥を祝い後世に伝えていくことが目的。記念日は2019年(令和元年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

寒天について
寒天(かんてん)は、テングサ(天草)・オゴノリなどの紅藻類の粘液質を凍結・乾燥したものである。また、寒天ゲルは、乾燥寒天を冷水に浸し沸騰させて炭水化物鎖を溶かし、他の物質を加えて漉(こ)し、38℃以下に冷ますことによって固めて作られる。
ちなみに、ゼラチンは動物の皮膚や骨、腱などの結合組織の主成分であるコラーゲンに熱を加え抽出したもの。食用のゲル(ゼリー)の材料という点では、寒天とゼラチンはよく似ているが、化学的には異なる物質である。
江戸時代前期、山城国紀伊郡伏見御駕籠町(現:京都市伏見区御駕籠町)において旅館「美濃屋」の主人・美濃太郎左衛門が、島津大隅守滞在のおりに戸外に捨てたトコロテンが凍結し、日中に融けたあと日を経て乾物状になったものを発見した。
試しに溶解してみたところ、従来のトコロテンよりも美しく海藻くささもなかった。これを黄檗山(おうばくさん)萬福寺を開創した隠元(いんげん)禅師に試食してもらったところ、精進料理の食材として活用できると奨励され、その際に隠元によって「寒天」と命名されたという。
雑学ネタ帳より
寒天発祥の日(12月27日 記念日)
京都府京都市に事務局を置く「伏見寒天記念碑を建てる会」が制定。
日付は、現在の暦で12月末頃に初めての「寒天」の元となるトコロテンが京都市伏見区御駕籠町(おかごちょう)で島津藩に提供されたと資料から推察できることとから12月。伏見=ふしみ(243)を「24+3=27」と見立てて27日。この月と日を組み合わせて12月27日とした。
京都の伏見が「寒天発祥の地」であることをアピールし、御駕籠町近辺に記念碑を建て、啓発活動を行いながら寒天の発祥を祝い後世に伝えていくことが目的。記念日は2019年(令和元年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

寒天について
寒天(かんてん)は、テングサ(天草)・オゴノリなどの紅藻類の粘液質を凍結・乾燥したものである。また、寒天ゲルは、乾燥寒天を冷水に浸し沸騰させて炭水化物鎖を溶かし、他の物質を加えて漉(こ)し、38℃以下に冷ますことによって固めて作られる。
ちなみに、ゼラチンは動物の皮膚や骨、腱などの結合組織の主成分であるコラーゲンに熱を加え抽出したもの。食用のゲル(ゼリー)の材料という点では、寒天とゼラチンはよく似ているが、化学的には異なる物質である。
江戸時代前期、山城国紀伊郡伏見御駕籠町(現:京都市伏見区御駕籠町)において旅館「美濃屋」の主人・美濃太郎左衛門が、島津大隅守滞在のおりに戸外に捨てたトコロテンが凍結し、日中に融けたあと日を経て乾物状になったものを発見した。
試しに溶解してみたところ、従来のトコロテンよりも美しく海藻くささもなかった。これを黄檗山(おうばくさん)萬福寺を開創した隠元(いんげん)禅師に試食してもらったところ、精進料理の食材として活用できると奨励され、その際に隠元によって「寒天」と命名されたという。
雑学ネタ帳より
これは昨日の「春秋」の出だしの言葉。
記事を少し読み進めると出だしの言葉の意味は直ぐ分かる。
「帰省」から「反省」まで「省」の字の意味で綴られたこの文章、流石だなーと感心させられました。

東京の人口が減り始めた。朝夕の電車の混雑は和らぎ、車内では大きな旅行ケースを抱えた親子連れが目立つ。帰省シーズンである
▼年越しの前後、東京の人口は半減し、地方では人口が1~2割増える市町村もある、といわれる。つかの間でも、東京の息苦しさが消え、列島各地ににぎわいが戻るのはどこかうれしい
▼帰省の「省」には「振り返る」「はぶく」に加え、「訪ねる」「見舞う」の意がある。帰省とは元々古里で暮らす父母らが元気でいるか、安否を確認する営みだ
▼問題は永田町・霞が関の面々だろう。国民の声に耳を傾ける、政策の議論を尽くす、説明責任を果たす、といった肝心の作業はおざなり。つまり「はぶく」ことだけが得意技のよう
▼気の毒なのは、クリスマスも正月休みも返上して机に向かう高校生らだ。大学入試での英語民間試験は延期、数学・国語試験での記述式導入は見送り。かねて、これらは拙速で問題点が多いと言われていたのに。ごり押しで実施に走った結果、大混乱が生じた
▼文部科学省をはじめ、中央官庁は「省」の名で呼ばれる。皮肉である。漢和辞典を引いてほしい。「省」の本来の意は物事をじっくり見ること。その上で、真に無駄なものをはぶくのが「省略」、自らの過ちを謙虚に認めるのが「反省」である。今の政治まかせでは東京一極集中が一向に是正されない。その理由も分かったような気がする。
記事を少し読み進めると出だしの言葉の意味は直ぐ分かる。
「帰省」から「反省」まで「省」の字の意味で綴られたこの文章、流石だなーと感心させられました。

東京の人口が減り始めた。朝夕の電車の混雑は和らぎ、車内では大きな旅行ケースを抱えた親子連れが目立つ。帰省シーズンである
▼年越しの前後、東京の人口は半減し、地方では人口が1~2割増える市町村もある、といわれる。つかの間でも、東京の息苦しさが消え、列島各地ににぎわいが戻るのはどこかうれしい
▼帰省の「省」には「振り返る」「はぶく」に加え、「訪ねる」「見舞う」の意がある。帰省とは元々古里で暮らす父母らが元気でいるか、安否を確認する営みだ
▼問題は永田町・霞が関の面々だろう。国民の声に耳を傾ける、政策の議論を尽くす、説明責任を果たす、といった肝心の作業はおざなり。つまり「はぶく」ことだけが得意技のよう
▼気の毒なのは、クリスマスも正月休みも返上して机に向かう高校生らだ。大学入試での英語民間試験は延期、数学・国語試験での記述式導入は見送り。かねて、これらは拙速で問題点が多いと言われていたのに。ごり押しで実施に走った結果、大混乱が生じた
▼文部科学省をはじめ、中央官庁は「省」の名で呼ばれる。皮肉である。漢和辞典を引いてほしい。「省」の本来の意は物事をじっくり見ること。その上で、真に無駄なものをはぶくのが「省略」、自らの過ちを謙虚に認めるのが「反省」である。今の政治まかせでは東京一極集中が一向に是正されない。その理由も分かったような気がする。
●クリスマス(Christmas)

キリストの誕生日とされる日で、降誕祭を祝う風習は4世紀ころから広まった。
だが、キリストがこの日に生まれた確証はなく、古くからの太陽の新生を祝う
祭(冬至)と結合したとも言われる。Xmasとも書き、フランス語ではノエ
ル、イタリアではナターレ、ドイツではワイナハテンと言う。
こどもたちはどんな贈り物をもらったでしょうか?

キリストの誕生日とされる日で、降誕祭を祝う風習は4世紀ころから広まった。
だが、キリストがこの日に生まれた確証はなく、古くからの太陽の新生を祝う
祭(冬至)と結合したとも言われる。Xmasとも書き、フランス語ではノエ
ル、イタリアではナターレ、ドイツではワイナハテンと言う。
こどもたちはどんな贈り物をもらったでしょうか?
こどもの詩
心の手紙
川嶋 里空・りく
もしもし ばあちゃん
ぼくね 夜中の12時に
心の手紙を送ったからね
じいちゃん ばあちゃん
大好きって
(千葉県八千代市・坪井幼稚園年長)
読売新聞 くらし面 12月24日

今日はクリスマス・イブ
孫からの「大好き」はおじいさんやおばあさんにとっては最高の贈り物。
気持ちがホッとするこどもの詩ですね。
ありがとう。
心の手紙
川嶋 里空・りく
もしもし ばあちゃん
ぼくね 夜中の12時に
心の手紙を送ったからね
じいちゃん ばあちゃん
大好きって
(千葉県八千代市・坪井幼稚園年長)
読売新聞 くらし面 12月24日

今日はクリスマス・イブ
孫からの「大好き」はおじいさんやおばあさんにとっては最高の贈り物。
気持ちがホッとするこどもの詩ですね。
ありがとう。
年の瀬を迎え早いもので明日はクリスマス・イブである。
この「イブ」の意味を長い間、間違って理解していたようである。今日の私の勉強は「eve」のお話。

「クリスマス・イヴ」(Christmas Eve)は、「クリスマス」(キリスト降誕祭)の前夜。
「eve」は夜を意味する古語「even」から来たもので「クリスマスの夜」の意味になる。キリスト教会暦では日没が1日の始まりであり、クリスマスは24日の日没から25日の日没までとなるので、その間の夜である24日の夜のことを「クリスマス・イヴ」と呼ぶ。日本では、「クリスマスの前夜」と認識されることが多い。
日常会話では単に「イヴ」と呼ばれることがある。キリスト降誕の前夜祭として、クリスマス当日にかけて礼拝が行われる。欧米ではこの日から1月1日または1月6日までが「クリスマス休暇」となる。
キリスト教の祭礼の一つだが、日本では宗教とは関係なく年中行事のようになっている。この日が近づくとデパートや商店街、一般家庭でもクリスマスツリーを飾ったり、クリスマスプレゼントを用意したり、クリスマスムードが一気に盛り上がる。
この「イブ」の意味を長い間、間違って理解していたようである。今日の私の勉強は「eve」のお話。

「クリスマス・イヴ」(Christmas Eve)は、「クリスマス」(キリスト降誕祭)の前夜。
「eve」は夜を意味する古語「even」から来たもので「クリスマスの夜」の意味になる。キリスト教会暦では日没が1日の始まりであり、クリスマスは24日の日没から25日の日没までとなるので、その間の夜である24日の夜のことを「クリスマス・イヴ」と呼ぶ。日本では、「クリスマスの前夜」と認識されることが多い。
日常会話では単に「イヴ」と呼ばれることがある。キリスト降誕の前夜祭として、クリスマス当日にかけて礼拝が行われる。欧米ではこの日から1月1日または1月6日までが「クリスマス休暇」となる。
キリスト教の祭礼の一つだが、日本では宗教とは関係なく年中行事のようになっている。この日が近づくとデパートや商店街、一般家庭でもクリスマスツリーを飾ったり、クリスマスプレゼントを用意したり、クリスマスムードが一気に盛り上がる。
12月22日頃(2019年は12月22日、2020年は12月21日)。
および小寒までの期間。
太陽黄径270度。
大雪から数えて15日目頃。
太陽が軌道上の最も南に来るときで、夏至と反対に、夜が最も長く、昼が短い日。
夏至から徐々に日照時間が減っていき、南中の高さも1年で最も低くなることから、太陽の力が一番衰える日と考えられてきました。
冬至は「日短きこと至る(きわまる)」という意味。中国では、この日から新年の始まる日とされ先祖を祀る習俗がありました。
※一陽来復(いちようらいふく)とも言います。
「一陽来復」は中国の「易経」に出てくる言葉。中国の昔の暦では10月はすべて陰の気で覆われ、11月になると陽の気が復活し、冬至を境に長くなっていくとされています。つまり、衰えていた太陽の力が再び勢いを増してくるというわけ。そのため、新しい年が来るという意味の他に、悪いことが続いた後に幸運に向かうという意味も込められているのです。良くないことが続いている人も、冬至が来たら「さあ、これからは良いことがどんどんやって来る」と気持ちを切り替えましょう。そういうきっかけを与えてくれる日でもあるんですよ。
早稲田の穴八幡などの神社では「一陽来復」のお守りが配られます。

暦便覧には・冬至 (とうじ) 〝日南の限りを行て日の短きの至りなれば也〟
および小寒までの期間。
太陽黄径270度。
大雪から数えて15日目頃。
太陽が軌道上の最も南に来るときで、夏至と反対に、夜が最も長く、昼が短い日。
夏至から徐々に日照時間が減っていき、南中の高さも1年で最も低くなることから、太陽の力が一番衰える日と考えられてきました。
冬至は「日短きこと至る(きわまる)」という意味。中国では、この日から新年の始まる日とされ先祖を祀る習俗がありました。
※一陽来復(いちようらいふく)とも言います。
「一陽来復」は中国の「易経」に出てくる言葉。中国の昔の暦では10月はすべて陰の気で覆われ、11月になると陽の気が復活し、冬至を境に長くなっていくとされています。つまり、衰えていた太陽の力が再び勢いを増してくるというわけ。そのため、新しい年が来るという意味の他に、悪いことが続いた後に幸運に向かうという意味も込められているのです。良くないことが続いている人も、冬至が来たら「さあ、これからは良いことがどんどんやって来る」と気持ちを切り替えましょう。そういうきっかけを与えてくれる日でもあるんですよ。
早稲田の穴八幡などの神社では「一陽来復」のお守りが配られます。

暦便覧には・冬至 (とうじ) 〝日南の限りを行て日の短きの至りなれば也〟





手水鉢の説明に玉造邸跡から移したと書かれています。
ガラシャ夫人の手水鉢は竹葉石か?を確かめに立田自然公園にある細川家菩提寺泰勝寺跡に行ってきました。
現物を確認しましたが手水鉢は粗削りに作られているのと外に置きっ放しなので表面の石材の柄が素人の私では判明しがたいものでした。
ガラシャ夫人の手水鉢は大阪の玉造邸から移築されたものですので、竹葉石産地(熊本県宇城市小川町、茨城県常陸太田市など)の関係から別の石と思われます。
武藤玉仙という宇土藩士が江戸で石細工の修練を積み、明治三十九年の東京博覧会においては出品作の一点が宮内省に買い上げられ、残りは細川家より買い上げられたという手水鉢の話があり、それが竹葉石の手水鉢です。
■ガラシャ夫人愛用のつくばい
「四つ御廟」の前のまるい手水鉢がガラシャ夫人愛用のものです。彼女の美しい顔を水面に映したであろう鉢はこもれ陽をあびて、ひっそれ佇んでいます。 ガラシャ夫人辞世の句 「散りぬべき 時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ」。 ...
●つくばい
つくばい(蹲踞、蹲)とは日本庭園の添景物の一つで露地(茶庭)に設置される。茶室に入る前に、手を清めるために置かれた背の低い手水鉢に役石をおいて趣を加えたもの。手水で手を洗うとき「つくばう(しゃがむ)」ことからその名がある。
もともと茶道の習わしで、客人が這いつくばるように身を低くして、手を清めたのが始まりである。茶事を行うための茶室という特別な空間に向かうための結界としても作用する。
●手水鉢(ちょうずばち)
水鉢(みずばち)とも。茶事の時に客人は席入りする前にここから柄杓一杯の水をとり、手を洗う事によって身を清める。
大きな手洗鉢
明治27(1894)年に旧熊本藩士、甘棠会員704人が
泰勝寺に奉納した竹葉石の手洗鉢。
作者は旧宇土藩士の玉仙。
江戸で石細工の修行を積み
明治39年の東京博覧会出品作の一点が宮内省に買い上げられ
残りは細川家に買い上げられたほどの名人だそうです。

※スマホで写した写真がブログに入らない???・・何故?。
画像取り込みが多すぎたのと画像取り込み時に動画も入っていたようです。
不要画像を取り消すことによって少し改善されました。
まだだいぶかかりそうです。22日午後3時前。
こどもの声って甲高いけれどもそれを聞くと何か癒される。
右隣の道路が小中高の通学路になっている。中高生はほとんどが自転車通学、小学生は徒歩での通学。朝7時頃からじゃれ合いながら通学する子供たちの声が聞こえる。今日も元気に登校している。・・・窓を開けると元気な子供たちの姿が見える。
こどもの詩 12月19日 読売新聞
心はどこに?
村井美智乃
くやしいなみだ
うれしいなみだ
あきらめないなみだ
いろいろななみだで
わたしの心はつよくなる
こころはなみだの中にある
(石川県小松市・稚松小2年)
こどもの詩 12月20日 読売新聞
ぶらんこ
渡辺 理生(りお)
りおちゃんままとねないよ
ひとりでねるからね
でもままとぶらんこには
のるからね
(東京都三鷹市・牟礼保育園4歳)

この子たちはどんな詩を書くのだろうか・・年末には子守がまってます。
右隣の道路が小中高の通学路になっている。中高生はほとんどが自転車通学、小学生は徒歩での通学。朝7時頃からじゃれ合いながら通学する子供たちの声が聞こえる。今日も元気に登校している。・・・窓を開けると元気な子供たちの姿が見える。
こどもの詩 12月19日 読売新聞
心はどこに?
村井美智乃
くやしいなみだ
うれしいなみだ
あきらめないなみだ
いろいろななみだで
わたしの心はつよくなる
こころはなみだの中にある
(石川県小松市・稚松小2年)
こどもの詩 12月20日 読売新聞
ぶらんこ
渡辺 理生(りお)
りおちゃんままとねないよ
ひとりでねるからね
でもままとぶらんこには
のるからね
(東京都三鷹市・牟礼保育園4歳)

この子たちはどんな詩を書くのだろうか・・年末には子守がまってます。
〝ONE TEAM〟今年の流行語大賞に選ばれた言葉です。
今年のワールドカップでは8強入りを果たした日本のラクビー少しラクビーについての豆知識を。
ラグビーはイギリスが発祥の地なのですが、もともとフットボールが盛んなところでラクビーのルールについてはまちまちなものでした。そんな中、イギリスの「ラグビー校」というところがやっていたフットボールのルールが現在のラグビーの原型となったと言われています。
ラグビーの起源は1823年ごろと言われていますがこの頃はラクビーとサッカーの区別がつかないものでした。1871年になってようやくサッカー団体から脱退する形でラグビー協会が設立されました。そして1895年にラグビーリーグと分裂して、現在のラグビーであるラグビーユニオンが誕生しました。またラクビーには2種類あり、イギリス南部を母体とするアマチュア主義をうたった組織はラグビーユニオン(15人制ラグビー)、イギリス北部を母体とする報酬を目的とするものはラグビーリーグ(13人制ラグビー)と呼ばれます。日本で「ラグビー」というと、ラグビーユニオンのことをいいます。
日本のラグビーの最初の試合は1874年にイギリスの船員によって横浜で行われました。その後1920年代になってようやく日本のラグビーが成長し始めていきました。
明治大学、慶應義塾大学、早稲田大学、同志社大学が日本ラグビーの中心となり、早慶戦も1924年から行われています。

ワンチームについて皮肉った使われ方をした記事があります、これが日本の現状だと思いながら一読してください。
西日本新聞・2019・12・15 【春秋】より
今年の新語・流行語大賞はラグビーW杯日本代表のスローガン「ONE TEAM(ワンチーム)」。チーム一丸の大健闘は日本中を感動で包んだ
▼こちらは話題になったけれど感動には無縁の永田町の新語・流行語。「子どもを産まなかった方が問題なんだ」(麻生太郎副総理兼財務相)。長寿化より少子化の方が社会保障や財政の脅威になると言いたかったとか
▼「私が忖度(そんたく)した」(塚田一郎国土交通副大臣=後に辞任)。安倍晋三首相と麻生氏の地元の下関北九州道路建設を巡り、2人の意向を代弁した、と。道路行政の担当副大臣の立場も忘れ
▼東日本大震災の被災地が地盤の同僚議員のパーティーで、同僚が「復興以上に大事」(桜田義孝五輪相=同)。記録的豪雨となった台風19号でも、被害が「まずまずに収まった」(自民党の二階俊博幹事長)、「私は雨男」(河野太郎防衛相)
▼「適材適所」「任命責任」(安倍首相)。政治と金の問題で菅原一秀経済産業相と河井克行法相が相次いで辞任。適材適所ではなかったが「任命責任がある」と言うだけで幕引き。「大型シュレッダー」「反社会的勢力」。首相官邸の庭には疑惑の桜が乱れ咲き
▼小欄が選んだ大賞は「身の丈に合わせて頑張って」(萩生田光一文部科学相)。受験の機会均等に責任を負う大臣が、地方や貧しい家庭の受験生を見下す非情さ。以上、みんな安倍政権の「ワンチーム」。
今年のワールドカップでは8強入りを果たした日本のラクビー少しラクビーについての豆知識を。
ラグビーはイギリスが発祥の地なのですが、もともとフットボールが盛んなところでラクビーのルールについてはまちまちなものでした。そんな中、イギリスの「ラグビー校」というところがやっていたフットボールのルールが現在のラグビーの原型となったと言われています。
ラグビーの起源は1823年ごろと言われていますがこの頃はラクビーとサッカーの区別がつかないものでした。1871年になってようやくサッカー団体から脱退する形でラグビー協会が設立されました。そして1895年にラグビーリーグと分裂して、現在のラグビーであるラグビーユニオンが誕生しました。またラクビーには2種類あり、イギリス南部を母体とするアマチュア主義をうたった組織はラグビーユニオン(15人制ラグビー)、イギリス北部を母体とする報酬を目的とするものはラグビーリーグ(13人制ラグビー)と呼ばれます。日本で「ラグビー」というと、ラグビーユニオンのことをいいます。
日本のラグビーの最初の試合は1874年にイギリスの船員によって横浜で行われました。その後1920年代になってようやく日本のラグビーが成長し始めていきました。
明治大学、慶應義塾大学、早稲田大学、同志社大学が日本ラグビーの中心となり、早慶戦も1924年から行われています。

ワンチームについて皮肉った使われ方をした記事があります、これが日本の現状だと思いながら一読してください。
西日本新聞・2019・12・15 【春秋】より
今年の新語・流行語大賞はラグビーW杯日本代表のスローガン「ONE TEAM(ワンチーム)」。チーム一丸の大健闘は日本中を感動で包んだ
▼こちらは話題になったけれど感動には無縁の永田町の新語・流行語。「子どもを産まなかった方が問題なんだ」(麻生太郎副総理兼財務相)。長寿化より少子化の方が社会保障や財政の脅威になると言いたかったとか
▼「私が忖度(そんたく)した」(塚田一郎国土交通副大臣=後に辞任)。安倍晋三首相と麻生氏の地元の下関北九州道路建設を巡り、2人の意向を代弁した、と。道路行政の担当副大臣の立場も忘れ
▼東日本大震災の被災地が地盤の同僚議員のパーティーで、同僚が「復興以上に大事」(桜田義孝五輪相=同)。記録的豪雨となった台風19号でも、被害が「まずまずに収まった」(自民党の二階俊博幹事長)、「私は雨男」(河野太郎防衛相)
▼「適材適所」「任命責任」(安倍首相)。政治と金の問題で菅原一秀経済産業相と河井克行法相が相次いで辞任。適材適所ではなかったが「任命責任がある」と言うだけで幕引き。「大型シュレッダー」「反社会的勢力」。首相官邸の庭には疑惑の桜が乱れ咲き
▼小欄が選んだ大賞は「身の丈に合わせて頑張って」(萩生田光一文部科学相)。受験の機会均等に責任を負う大臣が、地方や貧しい家庭の受験生を見下す非情さ。以上、みんな安倍政権の「ワンチーム」。
今日の雑学ネタ帳で北朝鮮が国連加盟国であったことを初めて知りました。

1956年(昭和31年)のこの日、日本の国際連合加盟案が全会一致で可決され、国連加盟が承認された。
1933年(昭和8年)2月の国際連盟総会で「満州国」の不承認などを不服として松岡洋右主席全権が議場から退席、国際連盟から脱退しており、23年ぶりに国際社会への復帰を果たした。
日本は、サンフランシスコ講和条約が発効して主権が回復した1952年(昭和27年)に国際連合に加盟申請をしていた。しかし、冷戦の最中であり、ソ連など社会主義諸国の反対によってなかなか実現しなかった。
1956年(昭和31年)10月の日ソ共同宣言とソ連との国交回復によってこの障害がなくなったことで、国連加盟が実現した。80番目の加盟国であった。2019年(平成31年)3月時点で、日本を含む国連加盟国は193ヵ国である。
日本が承認している国の数は195ヵ国であり、これに日本を加えた196ヵ国が日本における世界の国の数となる。日本が承認している国のうち、バチカン、コソボ、クック、ニウエは国連未加盟である。他方、日本が承認していない北朝鮮は国連に加盟している。

1956年(昭和31年)のこの日、日本の国際連合加盟案が全会一致で可決され、国連加盟が承認された。
1933年(昭和8年)2月の国際連盟総会で「満州国」の不承認などを不服として松岡洋右主席全権が議場から退席、国際連盟から脱退しており、23年ぶりに国際社会への復帰を果たした。
日本は、サンフランシスコ講和条約が発効して主権が回復した1952年(昭和27年)に国際連合に加盟申請をしていた。しかし、冷戦の最中であり、ソ連など社会主義諸国の反対によってなかなか実現しなかった。
1956年(昭和31年)10月の日ソ共同宣言とソ連との国交回復によってこの障害がなくなったことで、国連加盟が実現した。80番目の加盟国であった。2019年(平成31年)3月時点で、日本を含む国連加盟国は193ヵ国である。
日本が承認している国の数は195ヵ国であり、これに日本を加えた196ヵ国が日本における世界の国の数となる。日本が承認している国のうち、バチカン、コソボ、クック、ニウエは国連未加盟である。他方、日本が承認していない北朝鮮は国連に加盟している。
これって何が違うんだろうと思うことに気づく時があります。
今日の青じそと大葉もその一例です。
雑学ネタ帳に詳しく説明がありました。
「青じそ」と「大葉」の違いとは

スーパーなどでは「青じそ」と「大葉(おおば)」の両方の名前で商品が売られているが、これらは呼び方が違うだけである。
「青じそ」と「大葉」は同じ植物で、「青じそ」は植物名で、「大葉」は商品名という違いがある。
「青じそ」は古くからある植物の名前で、この「青じそ」に1960年(昭和35年)頃に愛知県の生産者が「大葉」という商品名を付けたと言われている。静岡県の生産者が名付けたという説もある。その名残で今でも二つの呼び名がある。正確には青紫蘇(アオジソ)という植物の葉に「大葉」という商品名を付けたことになる。
「青じそ」または「大葉」は、香味野菜として刺身のつまや天ぷら、薬味に用いられる。青紫蘇の若葉を摘んだものを「大葉」、花穂のつぼみの開き初めに摘んだものを「穂じそ」と呼ぶ。「青じそ」は西日本の一部では「青蘇(せいそ)」とも呼ばれる。
また、青紫蘇に対して、葉が赤紫色をした品種は赤紫蘇(アカジソ)である。アントシアン系の赤橙色のシアニジンという色素成分を含み、日本では梅干しを作る際に用いられる。
梅の成分であるクエン酸によってシアニジンが強く赤く発色することで、梅干し特有の赤い色となる。また、葉を乾燥させたものはハーブや香辛料として、京都などでは七味唐辛子に配合されることもあるほか、ふりかけなどにも用いられる。
紫蘇(シソ)は中国などが原産とされ、昔は薬草として使われていた。その昔、蟹(カニ)を食べて食中毒にかかり死にかけた子供に、紫色のシソの葉を食べさせたところ蘇った。それからこの草を「紫蘇」と呼ぶようになったという言い伝えがある。
今日の青じそと大葉もその一例です。
雑学ネタ帳に詳しく説明がありました。
「青じそ」と「大葉」の違いとは

スーパーなどでは「青じそ」と「大葉(おおば)」の両方の名前で商品が売られているが、これらは呼び方が違うだけである。
「青じそ」と「大葉」は同じ植物で、「青じそ」は植物名で、「大葉」は商品名という違いがある。
「青じそ」は古くからある植物の名前で、この「青じそ」に1960年(昭和35年)頃に愛知県の生産者が「大葉」という商品名を付けたと言われている。静岡県の生産者が名付けたという説もある。その名残で今でも二つの呼び名がある。正確には青紫蘇(アオジソ)という植物の葉に「大葉」という商品名を付けたことになる。
「青じそ」または「大葉」は、香味野菜として刺身のつまや天ぷら、薬味に用いられる。青紫蘇の若葉を摘んだものを「大葉」、花穂のつぼみの開き初めに摘んだものを「穂じそ」と呼ぶ。「青じそ」は西日本の一部では「青蘇(せいそ)」とも呼ばれる。
また、青紫蘇に対して、葉が赤紫色をした品種は赤紫蘇(アカジソ)である。アントシアン系の赤橙色のシアニジンという色素成分を含み、日本では梅干しを作る際に用いられる。
梅の成分であるクエン酸によってシアニジンが強く赤く発色することで、梅干し特有の赤い色となる。また、葉を乾燥させたものはハーブや香辛料として、京都などでは七味唐辛子に配合されることもあるほか、ふりかけなどにも用いられる。
紫蘇(シソ)は中国などが原産とされ、昔は薬草として使われていた。その昔、蟹(カニ)を食べて食中毒にかかり死にかけた子供に、紫色のシソの葉を食べさせたところ蘇った。それからこの草を「紫蘇」と呼ぶようになったという言い伝えがある。
1890年(明治23年)のこの日、東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始し、千代田区に設置された電話交換局が営業を始めた。
加入電話は東京155台・横浜44台、電話交換手は女子7人・夜間専門の男子2人が対応した。当時の電話料金は定額料金で東京が40円・横浜35円。この時代、1円で米が15kg買えたため、今の値段にすれば40円は24万円くらいに相当し、当時の電話はとても高価なサービスだったことが分かる。
これよりも21年前の1869年(明治2年)10月23日、横浜裁判所構内に電信機役所が設置され、東京~横浜間で公衆電信線の架設工事が始まった。これに由来して10月23日は「電信電話記念日」、10月20日~26日は「電信電話週間」となっている。
東京~横浜間で電信サービスが開始されたのはその翌年の1870年(明治3年)のことである。
さらに、1876年(明治9年)にアレクサンダー・グラハム・ベル(Alexander Graham Bell、1847~1922年)が電話機を発明すると、翌1877年(明治10年)には工部省が電話機を早速輸入して実験を行い、電話機の国産化に着手した。
そして、上記のように1890年(明治23年)に逓信省により東京~横浜間の電話交換サービスが開始され、電信・電話は同省の下で運営管理されることになった。
電話交換局(八重洲町、1902年頃)


当時の電話には電話交換手という電話の回線をつなぐ業務を行う人がいた。電話局内にある交換台において、一組の電話プラグを適切なジャックに差し込むことで、電話の回線を接続し、電話で話すことができた。そのため、電話をかける時は、最初に電話局の交換手を呼び出し、相手の電話に接続してもらっていた。
雑学ネタ帳より
※10月23日「電信電話記念日」、10月20日~26日「電信電話週間」、12月16日「電話創業の日」今は携帯電話で通信手段としては随分便利になりました。
加入電話は東京155台・横浜44台、電話交換手は女子7人・夜間専門の男子2人が対応した。当時の電話料金は定額料金で東京が40円・横浜35円。この時代、1円で米が15kg買えたため、今の値段にすれば40円は24万円くらいに相当し、当時の電話はとても高価なサービスだったことが分かる。
これよりも21年前の1869年(明治2年)10月23日、横浜裁判所構内に電信機役所が設置され、東京~横浜間で公衆電信線の架設工事が始まった。これに由来して10月23日は「電信電話記念日」、10月20日~26日は「電信電話週間」となっている。
東京~横浜間で電信サービスが開始されたのはその翌年の1870年(明治3年)のことである。
さらに、1876年(明治9年)にアレクサンダー・グラハム・ベル(Alexander Graham Bell、1847~1922年)が電話機を発明すると、翌1877年(明治10年)には工部省が電話機を早速輸入して実験を行い、電話機の国産化に着手した。
そして、上記のように1890年(明治23年)に逓信省により東京~横浜間の電話交換サービスが開始され、電信・電話は同省の下で運営管理されることになった。
電話交換局(八重洲町、1902年頃)


当時の電話には電話交換手という電話の回線をつなぐ業務を行う人がいた。電話局内にある交換台において、一組の電話プラグを適切なジャックに差し込むことで、電話の回線を接続し、電話で話すことができた。そのため、電話をかける時は、最初に電話局の交換手を呼び出し、相手の電話に接続してもらっていた。
雑学ネタ帳より
※10月23日「電信電話記念日」、10月20日~26日「電信電話週間」、12月16日「電話創業の日」今は携帯電話で通信手段としては随分便利になりました。
暦に「年賀郵便特別扱い開始日」とありますがこの特別扱いとはどういう事かご存知でしょうか?
全国の郵便局では、この日から年賀はがきの特別扱いを開始しています。
25日までに投函された分についての年賀はがきは、翌年1月1日(元旦)に必ず配達されるという特別な制度です。


この日から12月25日までの間に年賀状を投函すると、翌年の元旦・1月1日に届く。
年賀状の特別扱いの制度ができたのは1906年(明治39年)から。日本では、古く奈良時代から新年の年始回りという年始の挨拶をする行事があり、平安時代には貴族や公家にもその風習が広まり、挨拶が行えないような遠方などの人への年始回りに変わるものとして書状による年始挨拶が行われるようになった。時代とともに新年の挨拶は一般に広まり、江戸時代になると飛脚が書状を運ぶようになった。
季節のお便り、雑学ネタ帳今日は何の日より
全国の郵便局では、この日から年賀はがきの特別扱いを開始しています。
25日までに投函された分についての年賀はがきは、翌年1月1日(元旦)に必ず配達されるという特別な制度です。


この日から12月25日までの間に年賀状を投函すると、翌年の元旦・1月1日に届く。
年賀状の特別扱いの制度ができたのは1906年(明治39年)から。日本では、古く奈良時代から新年の年始回りという年始の挨拶をする行事があり、平安時代には貴族や公家にもその風習が広まり、挨拶が行えないような遠方などの人への年始回りに変わるものとして書状による年始挨拶が行われるようになった。時代とともに新年の挨拶は一般に広まり、江戸時代になると飛脚が書状を運ぶようになった。
季節のお便り、雑学ネタ帳今日は何の日より
このお話、雑学として記載されているものですが時間の観念の捉え方について日本では初めてのもので物語としてはその当時非常に新鮮なものでした。
どなたが書かれたんでしようか。
浦島太郎の「玉手箱」とは何か
おとぎ話の「浦島太郎」には、軽々しく開けてはいけない「玉手箱(たまてばこ)」という箱が登場する。この玉手箱とは一体何なのか。

「浦島太郎」の物語といえば、浦島太郎は助けた亀に乗り、竜宮城を訪れる。帰ろうとした時、乙姫から「開けてはいけない」と念を押されつつ「玉手箱」を渡される。
帰り着くと、竜宮城で過ごした時間より遥かに長い年月が経っており、失意の余り玉手箱を開けてしまう。すると、中から白い煙が発生し、浦島は白髪の老人になるというお話である。

この物語に出てくる「玉手箱」とは、もともと化粧道具を入れるための箱であり、現在でいう「化粧ポーチ」に当たる。玉手箱は物語の中だけに出てくる架空の品物ではなく、実際に使われていたものである。
玉手箱は奈良時代ごろから使われ始めたとされる。京都府伊根町には浦島太郎を祀る「浦嶋神社」という神社があり、「玉手箱」が残されている。神社の創建は平安時代の825年(天長2年)とされ、浦島太郎の物語にちなんで、室町時代に奉納された玉手箱がある。
その玉手箱の中には、化粧筆や櫛(くし)、お守りが収められている。このような箱はもともと「櫛笥(くしげ)」と呼ばれ、櫛を入れる箱だったが、時代とともに化粧道具全般を入れる箱になった。さらに、庶民の間に広まった際に「手箱(てばこ)」と呼ばれるようになった。
玉手箱の「玉」とは、大切な宝物という意味であり、「玉手箱」は大切なものをしまっておく箱のことである。当時の化粧道具はとても貴重なもので、女性にとって宝物と言えるものだった。
ところで、乙姫は玉手箱に何を入れて浦島太郎に渡したのか。それは浦島太郎の「魂」である。おとぎ話の「浦島太郎」ともとになった物語は少し違い、もともとは浦島太郎ときれいな異界の女性が恋に落ちて、素晴らしい時間を過ごすという恋愛小説だった。
浦島は亀を釣り上げ、逃がしてやると、その亀は美しい女性に姿を変えた。二人は竜宮城で幸せに暮らすが、3年が経ったある日、浦島は故郷が心配になり、一度帰りたいと申し出る。竜宮城での3年間は人間界での300年に当たり、そのまま帰すと浦島は一気に300歳の年をとり死んでしまう。
そこで、乙姫は浦島の魂を大切な宝物を入れる「玉手箱」に閉じ込めて渡した。これは魂さえ時間から守れば、肉体も守られるという考えである。浦島は誰も知り合いのいない300年後の世界に戻り、寂しさの余り、乙姫に会いたくなり玉手箱を開けてしまう。すると、浦島は老人になるのではなく、一気にかき消えてしまう。
もともとの浦島太郎のお話は、人間の過ごしている時間とは違う、もう一つ別の時間が流れているという時間の観念を日本で初めて取り入れた物語だった。
このように、「玉手箱」とは化粧道具のような大切なものを入れるための箱だった。ちなみに、現在のようなおとぎ話の「浦島太郎」になったのは明治時代である。児童文学書や教科書に載せる際に男女の恋の部分を省くことで、現在のような「浦島太郎」の物語になった。
雑学ネタ帳より
どなたが書かれたんでしようか。
浦島太郎の「玉手箱」とは何か
おとぎ話の「浦島太郎」には、軽々しく開けてはいけない「玉手箱(たまてばこ)」という箱が登場する。この玉手箱とは一体何なのか。

「浦島太郎」の物語といえば、浦島太郎は助けた亀に乗り、竜宮城を訪れる。帰ろうとした時、乙姫から「開けてはいけない」と念を押されつつ「玉手箱」を渡される。
帰り着くと、竜宮城で過ごした時間より遥かに長い年月が経っており、失意の余り玉手箱を開けてしまう。すると、中から白い煙が発生し、浦島は白髪の老人になるというお話である。

この物語に出てくる「玉手箱」とは、もともと化粧道具を入れるための箱であり、現在でいう「化粧ポーチ」に当たる。玉手箱は物語の中だけに出てくる架空の品物ではなく、実際に使われていたものである。
玉手箱は奈良時代ごろから使われ始めたとされる。京都府伊根町には浦島太郎を祀る「浦嶋神社」という神社があり、「玉手箱」が残されている。神社の創建は平安時代の825年(天長2年)とされ、浦島太郎の物語にちなんで、室町時代に奉納された玉手箱がある。
その玉手箱の中には、化粧筆や櫛(くし)、お守りが収められている。このような箱はもともと「櫛笥(くしげ)」と呼ばれ、櫛を入れる箱だったが、時代とともに化粧道具全般を入れる箱になった。さらに、庶民の間に広まった際に「手箱(てばこ)」と呼ばれるようになった。
玉手箱の「玉」とは、大切な宝物という意味であり、「玉手箱」は大切なものをしまっておく箱のことである。当時の化粧道具はとても貴重なもので、女性にとって宝物と言えるものだった。
ところで、乙姫は玉手箱に何を入れて浦島太郎に渡したのか。それは浦島太郎の「魂」である。おとぎ話の「浦島太郎」ともとになった物語は少し違い、もともとは浦島太郎ときれいな異界の女性が恋に落ちて、素晴らしい時間を過ごすという恋愛小説だった。
浦島は亀を釣り上げ、逃がしてやると、その亀は美しい女性に姿を変えた。二人は竜宮城で幸せに暮らすが、3年が経ったある日、浦島は故郷が心配になり、一度帰りたいと申し出る。竜宮城での3年間は人間界での300年に当たり、そのまま帰すと浦島は一気に300歳の年をとり死んでしまう。
そこで、乙姫は浦島の魂を大切な宝物を入れる「玉手箱」に閉じ込めて渡した。これは魂さえ時間から守れば、肉体も守られるという考えである。浦島は誰も知り合いのいない300年後の世界に戻り、寂しさの余り、乙姫に会いたくなり玉手箱を開けてしまう。すると、浦島は老人になるのではなく、一気にかき消えてしまう。
もともとの浦島太郎のお話は、人間の過ごしている時間とは違う、もう一つ別の時間が流れているという時間の観念を日本で初めて取り入れた物語だった。
このように、「玉手箱」とは化粧道具のような大切なものを入れるための箱だった。ちなみに、現在のようなおとぎ話の「浦島太郎」になったのは明治時代である。児童文学書や教科書に載せる際に男女の恋の部分を省くことで、現在のような「浦島太郎」の物語になった。
雑学ネタ帳より

正月事始め・煤払い・松迎え(12月13日 年中行事)
煤払い(すすはらい)などをして、年神様を迎える準備を始める日。
昔はこの日に門松やお雑煮を炊くための薪など、お正月に必要な木を山へ取りに行く習慣があった。
江戸時代中期まで使われていた「宣明暦(せんみょうれき)」では旧暦12月13日の二十七宿は必ず「鬼(き)」になっており、鬼の日は婚礼以外は全てのことに吉とされているので、正月の年神様を迎えるのに良いとして、この日が選ばれた。その後の改暦で日付と二十七宿は一致しなくなったが、「正月事始め」の日付は12月13日のままとなった。
京都祇園では、芸妓や舞妓が芸事の師匠宅やお茶屋を訪れ、あいさつをする習わしが続いている。また、地域によっては12月8日の「御事始め」として正月の準備を始める場合もある。

2019年の世相を表す「今年の漢字」に「令」が選ばれ、12日、世界遺産・清水寺(京都市東山区)で森 清範貫主 (せいはんかんす)が 揮毫 (きごう)した。
公益財団法人「日本漢字能力検定協会」が毎年公募し、応募総数21万6325票のうち「令」は最多の3万427票を獲得した。新元号が「令和」となったことに加え、相次ぐ災害で避難勧告・指示が発令されたことなどが主な理由という。
2位は「新」、3位は「和」だった。
雑学ネタ帳、読売新聞より
※そろそろ今年も終わりです。来年はいい年でありますように!
昨日、八代市保健センターで令和元年度、生活習慣病重症化予防教室がありました。糖尿病主治医の関上泰司先生が「糖尿病、ほうっておいたらどうなるの?」というお題で3時から1時間半講演をされました。私も家内も糖尿病を患っているので揃って聞きに行きました。保健センターの方でも糖尿病が進行して糖尿病性腎症のため人工透析の患者が増え続け、健康保険の医療費を圧迫している現状打破の為に設けられた講座だと説明。この病気は治療をしたからと言って治るということはありません。でもこれ以上悪くしないようにすることができる病気です。
糖尿病になってから今回、関上先生が話されたことは何度となく聞きましたが、その時ばかりで時間がたつとつい忘れて注意すべきことを忘れがちです。そして徐々に病気は悪くなってきます。自覚症状がない病気です。後悔先に立たずです。忘れた頃の刺激のために是非、この生活習慣病重症化予防教室は続けてもらいたいものです。
今日の雑学ネタ帳に「太ると知りながらご飯を食べ過ぎる理由」の話がありました。
昨日の生活習慣病の話によく似たところがありますので紹介します。

人間はご飯を食べ過ぎると太ってしまう。しかし、太ると分かっていても食べるのは止められないものである。
ご飯の米(精白米)はその成分の約70~80%がデンプンである。炊いてある温かいご飯のデンプンは、口の中で唾液に含まれる消化酵素の働きで、甘みのある「糖」に分解される。温かいご飯が甘く感じるのは、この糖によるもので、糖は人間の「エネルギーの源」である。
このエネルギー源の糖をたくさん摂取できるように、人の脳は甘みに対して最も快感を感じるようになったと考えられている。ご飯を食べ過ぎると太ると知りながらも食べてしまうのは、ご飯が「甘み」を感じる食べ物のためである。
舌で感じた甘みの刺激により、脳では「β-エンドルフィン」(beta-endorphin)という神経伝達物質が出る。これが幸福感や陶酔感を引き起こし、「幸せ」を感じさせる。しかし、β-エンドルフィンには一度好きになったものを病みつきにさせる作用がある。
さらに、β-エンドルフィンが出ると、新たに神経伝達物質の「ドーパミン」(dopamine)も分泌される。このドーパミンは意欲を起こすという特徴があり、食欲を増進させてしまう。人間は甘みに病みつきになり、それを食べ過ぎるような仕組みを持っている。
ご飯をつい食べ過ぎてしまうという行動の原点は、人類が甘いものを知ってしまったことである。そして、ご飯が甘いのは、人が米を炊く技術を持ったことにさかのぼり、これは人類が火を扱えるようになったことがその始まりとも言える。
糖尿病になってから今回、関上先生が話されたことは何度となく聞きましたが、その時ばかりで時間がたつとつい忘れて注意すべきことを忘れがちです。そして徐々に病気は悪くなってきます。自覚症状がない病気です。後悔先に立たずです。忘れた頃の刺激のために是非、この生活習慣病重症化予防教室は続けてもらいたいものです。
今日の雑学ネタ帳に「太ると知りながらご飯を食べ過ぎる理由」の話がありました。
昨日の生活習慣病の話によく似たところがありますので紹介します。

人間はご飯を食べ過ぎると太ってしまう。しかし、太ると分かっていても食べるのは止められないものである。
ご飯の米(精白米)はその成分の約70~80%がデンプンである。炊いてある温かいご飯のデンプンは、口の中で唾液に含まれる消化酵素の働きで、甘みのある「糖」に分解される。温かいご飯が甘く感じるのは、この糖によるもので、糖は人間の「エネルギーの源」である。
このエネルギー源の糖をたくさん摂取できるように、人の脳は甘みに対して最も快感を感じるようになったと考えられている。ご飯を食べ過ぎると太ると知りながらも食べてしまうのは、ご飯が「甘み」を感じる食べ物のためである。
舌で感じた甘みの刺激により、脳では「β-エンドルフィン」(beta-endorphin)という神経伝達物質が出る。これが幸福感や陶酔感を引き起こし、「幸せ」を感じさせる。しかし、β-エンドルフィンには一度好きになったものを病みつきにさせる作用がある。
さらに、β-エンドルフィンが出ると、新たに神経伝達物質の「ドーパミン」(dopamine)も分泌される。このドーパミンは意欲を起こすという特徴があり、食欲を増進させてしまう。人間は甘みに病みつきになり、それを食べ過ぎるような仕組みを持っている。
ご飯をつい食べ過ぎてしまうという行動の原点は、人類が甘いものを知ってしまったことである。そして、ご飯が甘いのは、人が米を炊く技術を持ったことにさかのぼり、これは人類が火を扱えるようになったことがその始まりとも言える。




