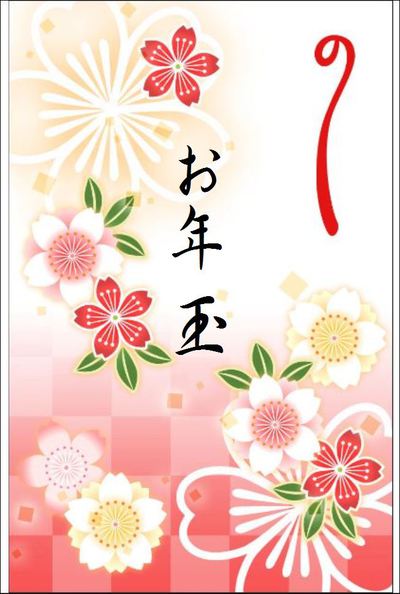
ほうじ
菊屋 由梨
ひいおばあちゃんの
ほうじがあった
18人くらい人がきていた
おぼうさんのおきょうは
20分くらいあった
さいごにおしょうこうをした
ひいばあちゃんがいるから
いまわたしがいる
ということがわかった
(山口県下関市・勝山小5年)
4月28日掲載
12月29日の読売新聞【くらし】の中にあった子供の詩ですが、今の自分をよく見つめているやさしい詩です。
子供さんやお孫さんのお年玉の準備はできましたか? みんな楽しみにしてますよ。
もうすぐ午年(うまどし)とはいえ、千里の馬でもあるまいに。就任から1年で国家安全保障会議、特定秘密保護法、他国軍への武器供与、そして靖国神社参拝。安倍晋三首相、走りすぎではないか、馬脚を現したと言うべきか▶前の安倍政権で参拝しなかったのが「痛恨の極み」と公言した首相だ。周囲の諌止(かんし)にも馬耳東風で信念を貫いた。戦没者に哀悼の意をささげたいとの思いは理解できる。あくまでも私人としてならば▶公事には針も通らず、私事には馬も通る、という。「私人の立場」と強調しても、首相の行動は国家、国民の総意と受け止められかねない。針も通さないほどのけじめが必要ではないか▶「中国、韓国の人々の気持ちを傷つける考えはない」。そんな言い分が通るとは首相自身も思ってはいまい。「白馬は馬にあらず」と強弁するに等しい▶<驥尾に付く・きびにつく>は、名馬の尾に付いていれば小さな虫も1日に千里を移動できるという例えだ。戦後、日本の安全保障は米国という強大な驥に頼ってきた。首相の外交も「日米同盟の強化」が基本だ。その米国からも「失望した」と突き放された▶中国が覇権主義を強め、北朝鮮の動向も不穏な中で、周辺国との溝を深めることが国益にかなうとは思えない。この先は集団的自衛権の行使、憲法改正へと駆け馬に鞭なのか。誠に危うい。竜馬(りょうめ)の躓きにご注意を。馬に乗っては三間先を見よ、という戒めもある。
今日12/28の西日本新聞の【春秋】もうすぐやってくる午年にちなみ安倍首相の1年を上手に比喩しています。
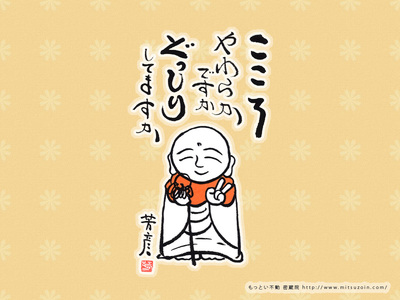
何事も慎重に慎重にでお願いしたいものである。
今日12/28の西日本新聞の【春秋】もうすぐやってくる午年にちなみ安倍首相の1年を上手に比喩しています。
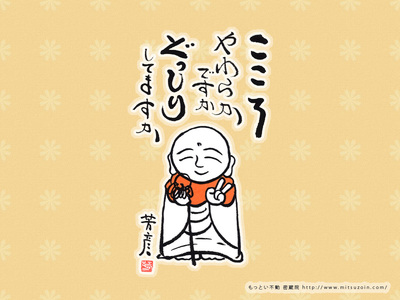
何事も慎重に慎重にでお願いしたいものである。
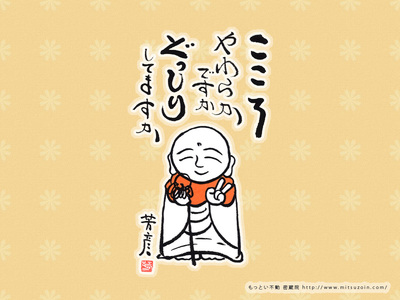
12月23日の記事
【「萬年正續」771年経て〝恩返し〟】博多千年門の扁額に中国の禅僧、書贈る・・こんな見出しで社会面に記事がありました。内容は聖一国師(しょういちこくし・諡号(しごう)円爾(えんに)鎌倉時代中期の臨済宗の僧。駿河(静岡県)の出身。が1235年から41年まで中国の杭州市の径山(きんざん)にある「萬壽寺」で修業し帰国して博多にある「承天寺」や京都五山の東福寺などを開き、製粉技術など先進文化を持ち帰りました。ところが、帰国の翌年、萬壽寺が火災で焼失。聖一国師は博多の豪商・謝国明の協力を得て、再建用に木材千枚を送り、復興に尽力しました。この度博多「承天寺」近くに「寺社町・博多」のシンボルとして建設中の「博多千年門」の扁額に、 揮毫(きごう・ふでを揮(ふる)う意)したのは「萬壽寺」の戒興和尚、日中両政府の関係が冷え込んでいるが、21日の夜寺を訪れた福岡側の関係者に書が渡され、民間の交流で771年前の〝返礼〟が実現した。
千年門の扁額に用いられる書は「萬年正續・まんねんしょうぞく」で、「千年も萬年も長きにわたり栄えるように」の意味。太宰府天満宮にあった樹齢千年のクスを加工し、掘り込まれる。企業や住民らでつくる「博多千年門期成会」のメンバー5人が訪中し、書を受け取った。期成会の瀧田喜代三副会長は「素晴らしい【言葉】をいただいた。博多と径山の交流を深めることが、日中の友好親善にもつながる」と謝辞を述べた。戒興住職は「長く中日の交流が続くようにと祈って書いた」と話した。
こころあったまる「ほっと」するいい記事ですね。こんな話がいっぱいあればいいのに。・・・
 12月22日は冬至です ①冬至のかぼちゃはなぜ食べる?
12月22日は冬至です ①冬至のかぼちゃはなぜ食べる?この日にかぼちゃを食べ始めた由来するのは江戸時代位からはじまったとされています。
現在では、かぼちゃの栄養価が注目されてビタミンAやカロチンが多く含まれるから風邪の予防になりやすいというような裏付けがあるようですが、昔は冬場は特に野菜が不足しがちでその期間に栄養価があるとされていてさらに比較的保存のきく食材だったカボチャを冬至の日に食べて冬を乗り切ろうという知恵が由来のようです。
冬至にかぼちゃを食べる由来は諸説あってどれもが冬を乗り切るための知恵という考えで発生したものである。
②冬至の日になぜ柚子湯?
柚子の木の性質に由来しているというのが一番有力な説のようです。
その特徴は柚子の木というのは寿命が長く虫などに強い特徴があってそれらの姿に照らし合わせて、柚子のお風呂に入ると長生きと病気にならない無病息災というものへの願いが込められています。
実際には柚子の栄養にはビタミンがたくさん入っているため病気の予防などには有効であると現在では分かっているようですが、当時の人たちの知恵というのはすばらしいなと思います。

冬至の日の太陽光の当たり方。冬至では太陽は南回帰線上にあるため、北半球では昼が最も短く、夜が最も長い。冬至(とうじ)は、二十四節気の第22。一年で最も昼が短い。十一月中(旧暦11月内)。
現在広まっている定気法では太陽黄経が270度のときで12月22日ごろ。恒気法は節気を冬至からの経過日数で定義するが、基点となる冬至は定気と同じ定義である。定気と恒気で一致する唯一の節気である。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とし、日のほうは冬至日(とうじび)と呼ぶ。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の小寒前日までである。
地球温暖化といわれて久しいこの時節ですが、この日を境に寒さが厳しくなるといわれてる日ですが今年は様子が少し違う様に思います。日本全国寒さが例年より早く来ていると思われます。

新聞記事を読んで家族などに意見を聞き、より深く考えて感想を書く「いっしょに読もう! 新聞コンクール」 第4回コンクールで八代市の八代白百合学園高の3年富田真由さんが「ネット選挙」について疑問、問いかけ、提案を投げかけ見事優秀賞に輝き、栄えある学校賞(学校賞は、新聞に触れる日常的な活動を含め、コンクールの趣旨に添って熱心に取り組んだ意欲的な学校に贈られます)にも九州では八代白百合学園高が受賞しました。こんな記事が今日の西日本新聞12面に大きく取り上げられていました。
担当教師代表者:宮嶋久美子教諭の記事 月2回の取り組み実る
昨年度までの2年間、NIE実践指定校として新聞活用に取り組んだ。高校生には社会に目を向けてほしいため、引き続き実践している。月2回全校約430人が取り組む「NIEノート」。新聞記事を選んで貼り、分からない語句を調べ、要約や感想を書く。1,2年生は興味がある記事を選ぶが、3年生になると目的意識を持ち、自分の将来に関わる記事を選ぶ生徒も多くなってきている。担任がコメントや文章指導を記入し生徒に渡している。コンクールへの応募は、3回目で学校賞と言う大変な賞を頂いたことに驚いている。本コンクールは、社会で起きていることを家族と話し合うことで、それぞれの視点を知り、学び合うことができる点が優れている。保護者も子どもの興味・関心を知り、成長を感じることができるのではないか。・・・・こんな意見が載っていました。素晴らしい取り組みだと思います。頑張れ!白百合学園。
NIE・・ (Newspaper in Education(教育に新聞を))とは、学校等で新聞を教材にして勉強する学習である。アメリカで1930年代にニューヨークタイムズが新聞の教材としてのハイスクールでの利用を考え、始めたもので、NIEを教育上利用している国家は、現代では世界で52か国にのぼっている。日本新聞教育文化財団が推進している。 【ウィキペディア参考】
●新聞を1面から最終面まで、記事や写真、広告までを読み解く
●複数の新聞を読み比べる
●読んだ結果について、ディベートを行う ディベート(debate)とは、ある公的な主題について異なる立場に分かれ議論することをいう(広義のディベート)。討論(会)ともいう。
これらの事を主軸とする。記事の切抜きや一部を使用する今までの新聞を用いた教育とは違い、学習に対する自主的で積極的なアプローチや情報の自己判断力の向上を促進させるものである。また活字離れを食い止める効果があるとされる。ディベートを行う場合、よく読み込まなくてはならないため、読解力も付けられる。
特に複数の新聞を読み比べる事で新聞のウソや偏向報道を見抜く目を養うことはメディア・リテラシーにも通じ、現代の子供にとってとても重要な意味合いを持つ。これは、松本サリン事件の時にも言われた事だが、こういったNIEを受けてきた子供達が将来大人になった時に報道被害を食い止められるのでは、とされる。
また、近年の大人にまで及んでいる政治に対する無関心(これは日本に限ったことではない)を打破する事にも繋がる。実際、今までの授業での社会科などでの政治に対する扱いは、概念的なことが中心で、今のホットな政治の動きについてはあまり扱わない事が多い。そのため、今の政治の動きを知ることで、関心を持つきっかけになる。
教育界と新聞界が協力し、推進することで家庭や学校に負担をかけずにNIEを行うことができるようになっている。具体的には、一定期間複数の新聞を供与すること等が上げられる。

上智大学名誉教授 春原昭彦氏が書いた古い記事に、
続日本の新聞人③ 光永星郎(みつながほしお)と言うのがありました。
ふた間の借家から世界一の広告会社にのし上がらせた広告業界の先駆者であり、【電通】(世界一の巨大な広告会社で日本の総広告料の約25%を電通が握っており、2位の博報堂を売上高で2.75倍も引き離しています)の創業者の記事です。電通の創業者が八代郡氷川町の出身と言うのはつい最近知りました。八代っていろんな人を輩出しているんですね地元の誇りです。
明治後期から戦前昭和期に活躍した通信・広告業界の先駆者。慶応2(1866)年7 月26 日、熊本県八代郡野津村に生まれ、徳富一敬(蘇峰の父)の共立学舎に学ぶ。その後、自由民権運動などに加わり保安条例で帝都追放になったが、1889(明治22)年秋、大阪公論記者、公論廃刊後は大阪朝日新聞九州通信員となる。国会開設後、再び自由党院外団などで政治活動を行うが、94 年、渡韓中に日清戦争が起こると従軍して、めさまし新聞、福岡日日新聞(現西日本新聞)に記事を送った。この時の通信問題への関心から、通信社経営とそれを支える新聞社への広告の供給を思い付き、1901(明治34)年7 月1 日、日本広告株式会社を創立、通信のために電報通信社を併設した。日露戦争を経て06 年12 月、電報通信社を改組、日本電報通信社を創立、翌07 年8月1 日、両社を合体して株式会社日本電報通信社が出現した。この年5月、米国のUP 通信社と通信提携したが、これが電通通信部の発展に大きく寄与することになり、以後、広告・通信とも電通の発展は目覚
しかった。だが36(昭和11)年6 月、国の統制政策により電通通信部は聯合通信部との合併を強制されて同盟通信社となり、日本電報通信社は広告専門会社として新発足する。以後戦時下の広告界は苦難の道を歩むが、光永は戦後の繁栄を見ることなく、1945(昭和20)年2月20日死去した。その生涯は話題にも富み、「心身の健全、不屈の努力、業務への誠実」を意味する「健・根・信」を信条に掲げたほか、毎年寒になると白衣の社員が広告主や新聞社を回って寒中見舞いをする「寒行」、さらに夏には社員の富士登山競争を行い、山頂から得意先に暑中見舞いを送るなど独特のアイデアで、顧客に感謝の意を表し話題を提供した。

毎日、新聞を見てもうんざりする様な記事ばかりで、だんだん新聞も見たくない様な日々が続きます。そんな中、今日気持ちがほっとする記事が二つありました。一つはキャロライン・ケネディ大使の話、あと一つは孫文と宮崎滔天(みやざきとうてん)にまつわる話。
① 「オバマ氏本人に被爆地招請状を」 長崎、広島市長にケネディ大使
長崎市の田上富久市長と広島市の松井一実市長は16日、東京都内の在日米大使館を訪れ、キャロライン・ケネディ大使に来年の「原爆の日」の式典出席を要請し、前向きの回答を受けた。オバマ米大統領の被爆地訪問も求め、ケネディ氏はオバマ氏本人に招請状を送るように助言し、両市長は連名で招請状を送る方針を決めた。・・・・オバマ氏の被爆地訪問についても、ケネディ氏は「広島、長崎が大統領に直接『来ていただきたい』という要請文を出してはどうですか。必ず検討すると思う」と話したという。オバマ氏は来年4月のアジア歴訪で日本への訪問も予定している。
もう一つは熊本に関係する話です。
② 「中国人留学生が炭鉱跡を見学」 「中国人教師グループが小中学校訪問」ー、辛亥革命の主導者、孫文ゆかりの地、熊本県荒尾市では日中交流が日常的に続く。中国が沖縄県・尖閣諸島を含む東シナ海上空に防空識別圏を設定、日中間の緊張が高まっているだけに。こうした地域の交流が妙に新鮮に映る。
同市はこの1年余、尖閣問題で揺れた。昨秋、孫文と地元出身の自由民権運動家宮崎滔天の交流を題材に中国・上海で予定していた企画展が延期になった。だが、最近になって共催の上海市と来年1月の開催で合意。上海市側から「(国家間の問題は)私らの交流に影響しない。やろう」との返事があったと言う。
一昨年の「辛亥革命100年」。荒尾市の日中交流の歴史は1世紀を迎えた。尖閣問題をめぐる両国の微妙な関係は続くが、地域住民の草の根交流は揺るぎない。むしろ、日中間の問題解決の力になるかもしれない。
何かしら「ほっと」するような話です。

今日の西日本新聞【秘密保護法 成立】 与党が採決強行 知る権利懸念 一面に大きな見出し、2面、3面、8面、9面、39面にすべて大きく取り上げています。決まってしまってからでは遅いんです。
紙面を大きく取るなら法案が決まる以前に何度も何度もこの記事を大きく取り上げてほしかった。ほとんどの人達が出せるかの問いに、I am〝No〟だったと思われます。
2013、12、8 春秋
「閑古鳥が鳴く」は、訪れる客もなく商売がうまくいかない様を表す慣用句。同じ「かんこどり」ながら、違う意味合いを持つ故事成語がある。▶中国の伝説上の聖太子が、君主の誤りを諌(いさ)めようとする民に打ち鳴らさせるため、あえて朝廷の門外に置いたとされる太鼓が「諌鼓(かんこ)」。それが鳴らされることがないほど善政がしかれ、太鼓が古びることを「諫鼓苔むす」。さらに、ならぬ諫鼓の周りを鶏が気ままに遊ぶことを「諫鼓鶏」という▶長崎県・対馬の歴代藩主、宗氏一族の墓所がある万松院には、この諫鼓をかたどった石像がある。東京の神田祭をにぎわす山車(だし)の中にも、諫鼓の上に鶏が鎮座するものが見られ、徳川の御世(みよ)の太平をたたえる意味があるらしい▶それにしても古来、絶対的君主の時代においてさえ民衆と権力者との間の適正な緊張関係こそが、治世の要諦と考えられていたのは間違いない▶翻(ひるがえ)って現代、万雷のごとき疑問や反対の声にもかかわらず、特定秘密保護法が自民、公明両党の賛成多数で成立した。打ち鳴らされる「諫鼓」に耳を貸さず、権力の座にいる人々が己の思惑を押し通した。▶与党幹部には諫鼓の音も烏合(うごう)の衆の脅しにしか聞こえなかったようだ。諫鼓なんて今度の法律で雲散霧消などと思っているかもしれないが、そうはいかない。諫鼓鶏どころか、太鼓の音はますます大きくなることを政府、与党は肝に銘じるべきだ。
脅迫状みたいですね


大雪(たいせつ)・・二十四節気・雑節 「おおゆき」ではなく「たいせつ」と読みます。 12月7日頃(2013年は12月7日)。 および冬至までの期間。 太陽黄径255度。 小雪から数えて15日目頃。山岳だけでなく、平野にも降雪のある時節ということから大雪といわれたものでしょう。この頃になると九州地方でも初氷が張り、全国的に冬一色になる季節です。冬の寒さが日ごとに加わります。スキー場がオープンしたり、熊が冬眠に入るのもこの頃。 鰤(ぶり)など冬の魚の漁も盛んになります。山々は雪の衣を纏い、白く染まる平野に南天の赤い実が映えはじめる頃。
新年の準備をはじめる「正月事始め」の日もこの時期。
 八代でこの雪が見られるのは東陽村から泉村あたりかな、でもまだこの時期では早いと思われます。今年は随分寒いように感じるんだけど・・・・
八代でこの雪が見られるのは東陽村から泉村あたりかな、でもまだこの時期では早いと思われます。今年は随分寒いように感じるんだけど・・・・

浄土門根元地 西山浄土宗総本山 光明寺・・パンフレットには京都の西南、西山連峰がたおやかな稜線を描き、美しい竹林や杉、桧の森に囲まれた粟生の里は、法然上人が初めて「お念仏」の教えを説かれたところです。それから800年、当本山は西山浄土宗の総本山で、報国山光明寺として法然上人の教えを受け継いできました。総門の前に立つ「浄土門根元地」という石標はそのことを表しているのです。
11月25日父母の墓参りの帰りに同じ長岡京の紅葉スポット光明寺に立ち寄ってみました。京都の片隅山崎に近い場所に有ります。今の時期は京都はどこに行っても人の行列、ここは案外穴場的な場所かもしれないと思っていましたが、知る人ぞ知る紅葉の穴場だった光明寺ですが、2009年のJR東海の「そうだ!京都へ行こう」シリーズのCMで一躍全国ネットとなり、今では京都屈指の紅葉の名所として、秋にはたくさんの観光客が訪れています。今年の光明寺の紅葉を紹介します。


















この日は生憎雨が降ったり止んだりで、足元も良くない日でしたが、もみじ参道は非常に綺麗でしたし、釈迦堂横の信楽庭(しんぎょうてい)も趣があって落ち着けました。
京都の紅葉堪能しました。
Posted by マー君 at
12:16
│Comments(0)



