天皇陛下が2019年4月30日に退位されることが決まりました。
本当にご苦労様でした。
陛下の意思をくんでもっと早くきめてあげればと・・日本の国民は思っていたのではないでしょうか。
世のすべての災いを自らの不徳のせいと考え、反省する。鎌倉時代の終わり近くに在位した花園天皇は、そんな帝だった(『人物・日本の歴史』読売新聞社)◆それでも天皇の位を退いて上皇になると、御所に参上するものがいなくなったらしい。〈かかる折にぞ、人の心もあらはれぬべき〉。こうゆうときに人間の本心があらわれる、と徒然草に嘆きの一節が見える◆天皇陛下の退位の日程が正式に決まった。700年も時代が違えば〈人の心〉が同じでなくても不思議はない。退位を境に陛下への敬愛の気持ちが変わる国民はいないだろう。戦没者の慰霊と平和の誓い、被災者に対する励まし・・・陛下と皇后さまの二人三脚の歩みとともに、平生の時間は流れてきた◆改元後にお出ましが減るのは致し方ない。陛下ご自身の年齢がある。新天皇との「二重権威」が生ずるのを避ける必要もある◆花園上皇の御所の印象を、兼好法師は〈さびしげなる〉と書き留めた。現代の日本人は、別の意味でさびしさを受け入れねばならない。
読売新聞 「よみうり寸評」 12・8夕刊
生前退位 せいぜんたいい
天皇が生きたまま天皇の地位を皇太子に譲る(=譲位)行為のこと。2016年7月13日、今上天皇が生前退位の意向を宮内庁の関係者に示されていることが政府関係者への取材で判明したという報道がなされ、にわかに生前退位についての報道や議論が活発化した。皇室についての基本法典である皇室典範では、現状、皇位の継承は天皇の崩御に限られている。
『徒然草』(つれづれぐさ)は、吉田兼好(兼好法師、兼好、卜部兼好)が書いたとされる随筆。清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』と合わせて日本三大随筆の一つと評価されている。
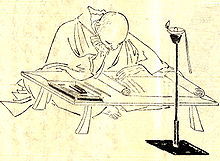
徒然草を書いたとされる吉田兼好は兼好法師ではなかったという研究をされた方がおられます。『本 よみうり堂』に「兼好法師」小川剛生。おがわたけお=1971年東京都生まれ。慶応大教授 著書に『二条良基研究』(角川源義賞)、『足利義満』など・・が中公新書で出版。
教科書の中身が又変わるかもしれません。

本当にご苦労様でした。
陛下の意思をくんでもっと早くきめてあげればと・・日本の国民は思っていたのではないでしょうか。
世のすべての災いを自らの不徳のせいと考え、反省する。鎌倉時代の終わり近くに在位した花園天皇は、そんな帝だった(『人物・日本の歴史』読売新聞社)◆それでも天皇の位を退いて上皇になると、御所に参上するものがいなくなったらしい。〈かかる折にぞ、人の心もあらはれぬべき〉。こうゆうときに人間の本心があらわれる、と徒然草に嘆きの一節が見える◆天皇陛下の退位の日程が正式に決まった。700年も時代が違えば〈人の心〉が同じでなくても不思議はない。退位を境に陛下への敬愛の気持ちが変わる国民はいないだろう。戦没者の慰霊と平和の誓い、被災者に対する励まし・・・陛下と皇后さまの二人三脚の歩みとともに、平生の時間は流れてきた◆改元後にお出ましが減るのは致し方ない。陛下ご自身の年齢がある。新天皇との「二重権威」が生ずるのを避ける必要もある◆花園上皇の御所の印象を、兼好法師は〈さびしげなる〉と書き留めた。現代の日本人は、別の意味でさびしさを受け入れねばならない。
読売新聞 「よみうり寸評」 12・8夕刊
生前退位 せいぜんたいい
天皇が生きたまま天皇の地位を皇太子に譲る(=譲位)行為のこと。2016年7月13日、今上天皇が生前退位の意向を宮内庁の関係者に示されていることが政府関係者への取材で判明したという報道がなされ、にわかに生前退位についての報道や議論が活発化した。皇室についての基本法典である皇室典範では、現状、皇位の継承は天皇の崩御に限られている。
『徒然草』(つれづれぐさ)は、吉田兼好(兼好法師、兼好、卜部兼好)が書いたとされる随筆。清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』と合わせて日本三大随筆の一つと評価されている。
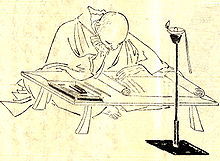
徒然草を書いたとされる吉田兼好は兼好法師ではなかったという研究をされた方がおられます。『本 よみうり堂』に「兼好法師」小川剛生。おがわたけお=1971年東京都生まれ。慶応大教授 著書に『二条良基研究』(角川源義賞)、『足利義満』など・・が中公新書で出版。
教科書の中身が又変わるかもしれません。

いつも感心するんだがこの記事を書いている方はどんな人なんだろう・・。
柳田国男、島崎藤村、若山牧水まで引っ張り出して黒潮の話、次には日本列島を中において反対側の日本海で起きているできごとに話を移して結んでいる。
この流れの中に中身がいっぱい詰まっているのが素晴らしい。
〈僕が二十一の頃だったか〉と、柳田国男は小文を書き出している。愛知の伊良湖岬で静養していたとき、海岸でヤシの実を見つけたという◆東京に戻って近所に住む島崎藤村に話した。〈名も知らぬ遠き島より/流れ寄る椰子の実一つ・・・〉『椰子の実』。藤村が詩を書くと、やがてメロディーがつき、広く国民の知るところとなる。他方、柳田も南洋からの古代人の渡来に思いをはせ、民俗学の道を切り開く◆植物の実が一つが詩に、歌に、学問に------黒潮と聞くと、真っ先にこのエピソードを思い出すものの、ことしはすこしさみしい。太平洋沿岸で長期化する黒潮大蛇行である。◆海上保安庁が今週、蛇行の幅が拡大し、さらに沿岸から遠のいたと発表した。ヤシの実はどこに向かうのだろう?〈椰子の実を拾ひつ秋の海黒きなぎさに立ちて日にかざし見る〉若山牧水。その暖流は陸からでも確かに黒く見える日があると、漁業関係者に聞いたことがある。「豊漁のサイン」とも◆おりしも反対側の日本海沿岸では、北朝鮮の木造船の漂着が相次ぎ、騒ぎとなる。流れ着いてほしいものは来ず、欲しくない者は来る。
読売新聞 【編集手帳】 2017・12・9

柳田 國男(やなぎた くにお、1875年(明治8年)7月31日 - 1962年(昭和37年)8月8日)は、日本の民俗学者・官僚。現在の兵庫県神崎郡福崎町生まれで、最晩年に名誉町民第1号となった。没後に正三位勲一等。当時の池田勇人首相が「民間人とはいえ、これだけの人物に瑞宝章では軽い」と発言し旭日大綬章が供えられた。帝国憲法下の農務官僚で貴族院書記官長、終戦後から廃止になるまで最後の枢密顧問官に就いた。
「日本人とは何か」その答えを求め、日本列島各地や当時の日本領の外地を調査旅行し、初期は山の生活に着目し、『遠野物語』で「願わくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」と述べた。日本民俗学の開拓者で、多数の著作は今日まで重版され続けている。

島崎 藤村(しまざき とうそん、1872年3月25日(明治5年2月17日)- 1943年(昭和18年)8月22日)は、日本の詩人、小説家。本名は島崎 春樹(しまざき はるき)。信州木曾の中山道馬籠[1](現在の岐阜県中津川市馬籠)生まれ。
『文学界』に参加し、ロマン主義詩人として『若菜集』などを出版。さらに小説に転じ、『破戒』『春』などで代表的な自然主義作家となった。作品は他に、日本自然主義文学の到達点とされる[誰によって?]『家』、姪との近親姦を告白した『新生』、父をモデルとした歴史小説の大作『夜明け前』などがある。

若山牧水本名は若山繁。明治18(1885)年8月24日、現在の日向市東郷町坪谷の医師の家に生まれる。坪谷尋常小学校、延岡高等小学校から県立延岡中学(現延岡高校)に入学。15歳で初めて短歌をつくり、18歳で牧水の号を使う。早稲田大学に進学し、23歳で第一歌集「海の声」を出版。旅と酒と自然を愛し、生涯で約8600余首を詠んだ。晩年は静岡県沼津市に住み、43歳で没した。
柳田国男、島崎藤村、若山牧水まで引っ張り出して黒潮の話、次には日本列島を中において反対側の日本海で起きているできごとに話を移して結んでいる。
この流れの中に中身がいっぱい詰まっているのが素晴らしい。
〈僕が二十一の頃だったか〉と、柳田国男は小文を書き出している。愛知の伊良湖岬で静養していたとき、海岸でヤシの実を見つけたという◆東京に戻って近所に住む島崎藤村に話した。〈名も知らぬ遠き島より/流れ寄る椰子の実一つ・・・〉『椰子の実』。藤村が詩を書くと、やがてメロディーがつき、広く国民の知るところとなる。他方、柳田も南洋からの古代人の渡来に思いをはせ、民俗学の道を切り開く◆植物の実が一つが詩に、歌に、学問に------黒潮と聞くと、真っ先にこのエピソードを思い出すものの、ことしはすこしさみしい。太平洋沿岸で長期化する黒潮大蛇行である。◆海上保安庁が今週、蛇行の幅が拡大し、さらに沿岸から遠のいたと発表した。ヤシの実はどこに向かうのだろう?〈椰子の実を拾ひつ秋の海黒きなぎさに立ちて日にかざし見る〉若山牧水。その暖流は陸からでも確かに黒く見える日があると、漁業関係者に聞いたことがある。「豊漁のサイン」とも◆おりしも反対側の日本海沿岸では、北朝鮮の木造船の漂着が相次ぎ、騒ぎとなる。流れ着いてほしいものは来ず、欲しくない者は来る。
読売新聞 【編集手帳】 2017・12・9

柳田 國男(やなぎた くにお、1875年(明治8年)7月31日 - 1962年(昭和37年)8月8日)は、日本の民俗学者・官僚。現在の兵庫県神崎郡福崎町生まれで、最晩年に名誉町民第1号となった。没後に正三位勲一等。当時の池田勇人首相が「民間人とはいえ、これだけの人物に瑞宝章では軽い」と発言し旭日大綬章が供えられた。帝国憲法下の農務官僚で貴族院書記官長、終戦後から廃止になるまで最後の枢密顧問官に就いた。
「日本人とは何か」その答えを求め、日本列島各地や当時の日本領の外地を調査旅行し、初期は山の生活に着目し、『遠野物語』で「願わくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」と述べた。日本民俗学の開拓者で、多数の著作は今日まで重版され続けている。

島崎 藤村(しまざき とうそん、1872年3月25日(明治5年2月17日)- 1943年(昭和18年)8月22日)は、日本の詩人、小説家。本名は島崎 春樹(しまざき はるき)。信州木曾の中山道馬籠[1](現在の岐阜県中津川市馬籠)生まれ。
『文学界』に参加し、ロマン主義詩人として『若菜集』などを出版。さらに小説に転じ、『破戒』『春』などで代表的な自然主義作家となった。作品は他に、日本自然主義文学の到達点とされる[誰によって?]『家』、姪との近親姦を告白した『新生』、父をモデルとした歴史小説の大作『夜明け前』などがある。

若山牧水本名は若山繁。明治18(1885)年8月24日、現在の日向市東郷町坪谷の医師の家に生まれる。坪谷尋常小学校、延岡高等小学校から県立延岡中学(現延岡高校)に入学。15歳で初めて短歌をつくり、18歳で牧水の号を使う。早稲田大学に進学し、23歳で第一歌集「海の声」を出版。旅と酒と自然を愛し、生涯で約8600余首を詠んだ。晩年は静岡県沼津市に住み、43歳で没した。
昨日のこと、きびしい寒さが続く中、外に出るのも嫌なんだけれども温泉となると話は違います。
ちょうど家内とも時間帯に余裕と気持ちが合ったものだから二人で日奈久温泉に行ってきました。
温泉入り口に妙な飾り物が置いてあります。
先日一人で来た時にも置いてあったので、「何だろうか?」と問いかけると「・・・?」答えようがないと言った様子。
お風呂から上がって帰りしな同じ場所を見るとなんときれいなイルミネーション。
日奈久温泉もそれなりに頑張っているんだ・・
少し元気を頂きました。
〝ありがとう〟。

 12月8日の写真
12月8日の写真
 12月6日の写真
12月6日の写真
日奈久温泉
熊本県八代市日奈久(ひなぐ)町の街中に湧く、閑静なたたずまいの温泉。
泉質は単純泉。
応永16年(1409年)浜田六郎が、父の刀傷を癒そうと神に祈り温泉を発見したと伝えられるところから孝行泉とも呼ばれています。
熊本県下で最も古い歴史を持つ温泉です。
江戸初期に細川家の藩営温泉に指定され、八代城主や参勤途上の島津公も、よくここを利用しました。
昭和5年には漂白の俳人種田山頭火も日奈久温泉の織屋旅館に宿泊し、その日記の中に「温泉はよい、 ほんとうによい。ここは山もよし海もよし、出来ることなら滞在したいのだが、いや一生動きたくないのだが・」と日奈久を称賛しております。
古い歴史と由緒を誇る日奈久温泉は、今でもたゆたう湯けむりの中に往時の表情を深く残す温泉です。
ちょうど家内とも時間帯に余裕と気持ちが合ったものだから二人で日奈久温泉に行ってきました。
温泉入り口に妙な飾り物が置いてあります。
先日一人で来た時にも置いてあったので、「何だろうか?」と問いかけると「・・・?」答えようがないと言った様子。
お風呂から上がって帰りしな同じ場所を見るとなんときれいなイルミネーション。
日奈久温泉もそれなりに頑張っているんだ・・
少し元気を頂きました。
〝ありがとう〟。


 12月8日の写真
12月8日の写真 12月6日の写真
12月6日の写真日奈久温泉
熊本県八代市日奈久(ひなぐ)町の街中に湧く、閑静なたたずまいの温泉。
泉質は単純泉。
応永16年(1409年)浜田六郎が、父の刀傷を癒そうと神に祈り温泉を発見したと伝えられるところから孝行泉とも呼ばれています。
熊本県下で最も古い歴史を持つ温泉です。
江戸初期に細川家の藩営温泉に指定され、八代城主や参勤途上の島津公も、よくここを利用しました。
昭和5年には漂白の俳人種田山頭火も日奈久温泉の織屋旅館に宿泊し、その日記の中に「温泉はよい、 ほんとうによい。ここは山もよし海もよし、出来ることなら滞在したいのだが、いや一生動きたくないのだが・」と日奈久を称賛しております。
古い歴史と由緒を誇る日奈久温泉は、今でもたゆたう湯けむりの中に往時の表情を深く残す温泉です。
暦に書いてある言葉からいろいろな事を学ぶことが出来ます。
現在の生活では忘れられているような行事や風習をわずかながら引き継いで生きて来たようにも思います。
暦に書かれている行事や風習も時の流れのなかでいつかは忘れられ,なくなってしまうかも知れませんね。
事初めと事納め
12月8日と2月8日を「事八日(ことようか)」といい、様々な行事が行われてきました。「事八日」というのは、この日が事を始めたり納めたるする大事な日だからです。
事八日には、針供養をしたり、お事汁を食べたりする風習があります。
※針供養についてはこちらをご覧ください。 → 針供養
※お事汁についてはこちらをご覧ください。 → お事汁
12月8日を「事始め」、2月8日を「事納め」という場合と、その逆に、2月8日を「事始め」、12月8日を「事納め」という場合があるのですが、それはいったいなぜでしょう?
「事」によって「始め」と「納め」が違います
「事」とは、もともと祭りあるいは祭り事を表す言葉で、コトノカミという神を祭るお祭りです。そのお祭りが12月8日と2月8日の2回あり、「事八日」「事の日」などと言われました。
コトノカミが「年神様」か「田の神様」かで、事始めと事納めの時期が逆転します。
この日付の違いは、この時に始める「事」が新年に迎える神様の「事」なのか、田畑を耕し農耕に勤しむ人の「事」かという違いです。
神様の年始めは12月8日、事納めは2月8日
年を司る神様を年神様といいます。年神様を迎えるために正月行事の準備を始めるのが12月8日の「事始め」で、年越しの「神事」が始まる日です。そして、後片付けもすべて納めるのが2月8日の「事納め」です。こうして神様に関する一連の「事」が終わると、春を迎え田畑を耕す時期となり、人々の日常が始まります。
江戸時代に入ると、12月13日が大吉日とされた鬼宿日にあたることから、この日が江戸城の「御煤納め」と定められました。このため12月13日が「正月事始め」として定着し、煤払い、松迎えなどの正月の準備にとりかかる日とされています。
人の事始めは2月8日、事納めは12月8日
年神様を迎えるための正月行事が終わって、人の日常生活が始まるのが2月8日です。2月8日を旧暦で言えば、 3月中旬の気候にあたります。春が来て暖かくなり、農作業が始まり、人の一年の営みが始まるというのがこの 2月 8日の「事始め」です。
こうして、年神様を迎える正月行事という「神事」の期間と、それ以外の人の「日常」の期間とに分けるとすれば、一方の始まりの日はまた一方の終わりの日になるわけです。
※暮らし歳時記より

田の神は、冬は山の神となり、春は里におりて田の神となって田を守り、豊作をもたらすと信じられています。
「田の神」信仰は、全国的な民俗行事として古来から農村に浸透していますが、「田の神」を石に刻み(田の神石像)豊作を祈願する風習は、18世紀初めに始まる薩摩藩独特の文化です。
「田の神石像」ができたころは、霧島の噴火・天災などが原因で、農家にとって大変きびしい時代でした。江戸時代からの赤字経済を立て直すため、薩摩藩では少しでも収穫を増やそうと、稲作を奨励する政策を行っていました。このような政策の中、農家は霧島の噴火をやめさせ、稲作の豊作を願うために「よりどころの像」を作るようになったといわれています。
えびの市の最古の「田の神石像」は1724年(享保9年)に中島地区に作られた神官型のものです。
田の神のことを、地元では「田の神さあ(タノカンサア)」と呼んでいます。えびの市内には約150体の田の神が残されています。
※えびの市 行政情報より
現在の生活では忘れられているような行事や風習をわずかながら引き継いで生きて来たようにも思います。
暦に書かれている行事や風習も時の流れのなかでいつかは忘れられ,なくなってしまうかも知れませんね。
事初めと事納め
12月8日と2月8日を「事八日(ことようか)」といい、様々な行事が行われてきました。「事八日」というのは、この日が事を始めたり納めたるする大事な日だからです。
事八日には、針供養をしたり、お事汁を食べたりする風習があります。
※針供養についてはこちらをご覧ください。 → 針供養
※お事汁についてはこちらをご覧ください。 → お事汁
12月8日を「事始め」、2月8日を「事納め」という場合と、その逆に、2月8日を「事始め」、12月8日を「事納め」という場合があるのですが、それはいったいなぜでしょう?
「事」によって「始め」と「納め」が違います
「事」とは、もともと祭りあるいは祭り事を表す言葉で、コトノカミという神を祭るお祭りです。そのお祭りが12月8日と2月8日の2回あり、「事八日」「事の日」などと言われました。
コトノカミが「年神様」か「田の神様」かで、事始めと事納めの時期が逆転します。
この日付の違いは、この時に始める「事」が新年に迎える神様の「事」なのか、田畑を耕し農耕に勤しむ人の「事」かという違いです。
神様の年始めは12月8日、事納めは2月8日
年を司る神様を年神様といいます。年神様を迎えるために正月行事の準備を始めるのが12月8日の「事始め」で、年越しの「神事」が始まる日です。そして、後片付けもすべて納めるのが2月8日の「事納め」です。こうして神様に関する一連の「事」が終わると、春を迎え田畑を耕す時期となり、人々の日常が始まります。
江戸時代に入ると、12月13日が大吉日とされた鬼宿日にあたることから、この日が江戸城の「御煤納め」と定められました。このため12月13日が「正月事始め」として定着し、煤払い、松迎えなどの正月の準備にとりかかる日とされています。
人の事始めは2月8日、事納めは12月8日
年神様を迎えるための正月行事が終わって、人の日常生活が始まるのが2月8日です。2月8日を旧暦で言えば、 3月中旬の気候にあたります。春が来て暖かくなり、農作業が始まり、人の一年の営みが始まるというのがこの 2月 8日の「事始め」です。
こうして、年神様を迎える正月行事という「神事」の期間と、それ以外の人の「日常」の期間とに分けるとすれば、一方の始まりの日はまた一方の終わりの日になるわけです。
※暮らし歳時記より

田の神は、冬は山の神となり、春は里におりて田の神となって田を守り、豊作をもたらすと信じられています。
「田の神」信仰は、全国的な民俗行事として古来から農村に浸透していますが、「田の神」を石に刻み(田の神石像)豊作を祈願する風習は、18世紀初めに始まる薩摩藩独特の文化です。
「田の神石像」ができたころは、霧島の噴火・天災などが原因で、農家にとって大変きびしい時代でした。江戸時代からの赤字経済を立て直すため、薩摩藩では少しでも収穫を増やそうと、稲作を奨励する政策を行っていました。このような政策の中、農家は霧島の噴火をやめさせ、稲作の豊作を願うために「よりどころの像」を作るようになったといわれています。
えびの市の最古の「田の神石像」は1724年(享保9年)に中島地区に作られた神官型のものです。
田の神のことを、地元では「田の神さあ(タノカンサア)」と呼んでいます。えびの市内には約150体の田の神が残されています。
※えびの市 行政情報より
 12月・日奈久温泉
12月・日奈久温泉今日は暦によると「大雪・二十四節気」とのこと。
八代ではまだこの時期は雪を見ることは出来ませんが寒さは一段と厳しく感じられます。
同じ八代地域でも九州中央山地の国定公園・五家荘や栴壇轟の滝(せんだんとどろのたき)あたりまで行けばこの時期になれば雪は見れるかもしれません。
熊本県も広くて今日の最低気温を見ると牛深7℃、熊本0℃、人吉-3℃、阿蘇乙姫-5℃と温度差が12℃もあります。
阿蘇山はこの前、初冠雪があったようです。
【熊本県の天気】
九州北部地方は、高気圧に覆われ概ね晴れていますが、寒気の影響により曇りで雨の降っている所があります。
7日の熊本県は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の接近で次第に曇りとなり雨の降る所があるでしょう。

【大雪】
●12月7日頃 大雪とは、山岳ばかりでなく平野にも雪が降り積もる季節ということからついた呼び名です。この頃になると九州地方でも氷が張ります。街はクリスマスの飾りでにぎやかになる頃ですね。
●二十四節気の一つ。陰暦11月の節で、立冬後30日、新暦では12月7日ごろにあたる。季節のうえでは、ちょうど初冬の中ごろにあたる。大都会では風の弱い日はスモッグの季節であり、また本土の日本海側では大雪が降る年もある。海は時化(しけ)る日が多くなるが、ブリやハタハタの季節でもある。クチナシやヤブコウジが赤く染まり、暖かい地方ではウメのつぼみが発育を始める季節である。
●この時期旬を迎える食材
【野菜】
・白菜(はくさい)
・大根(だいこん)
・蓮根(れんこん)
・韮(にら) など
【魚貝類】
・鰤(ぶり)
・鮭(さけ)
・筋子(すじこ) など

日記がわりにブログを書いているとふとしたことから自分の浅くて薄っぺらい知識に気づかされることがあります。
昨日、熊本の大地12月の例会で廣田さんから戴いた資料に大河内銅山のはなしがありました。・・・
寛永14年(1637)3月、葦北大河内銅山を試掘し、芦北銅の試吹きを差し上げ,開発を継続することに決定し、同15年8月には、銅の生産1ヶ月に1500斤から1600斤と報告され、更に翌12年10月には、銅山奉行鳥巣羽右衛門から、葦北銅山8月1か月間の銅吹き2500斤と報告されている・・・
この江戸時代に使われている「斤」という何かの単位について、私たちが現在使っている「斤」ですぐに思いつくものとしては食パンの単位に使われていることを思い出します。
私は今まで「斤」は物の大きさを表す単位だとばかり思っていました。
家内に「パンの1斤ってなんのこと」と尋ねると「大きさかな?重さかな?・・だって砂糖なんかも1斤ていうから・・ムニャムニャ・・」
砂糖って言われて自分の答えがぐらつきました。
調べてみると・・斤(きん)は、尺貫法の質量の単位である。伝統的には1斤は16両と定義される。
日本では、通常は1斤=16両=160匁、1匁=3.75グラム、1斤 = 160匁 = 600グラム
と規定されています。
従って銅の生産が1ヶ月に1500斤~1600斤ということは900kg~960kgあったということである。
1斤とは重さを表す単位のこと。
知らなかったのは私だけだろうか。
12月の第一日曜日(12/3)は熊本の大地(地学)の現地学習がありました。
今回は事務局の川路先生が体調不良のため道案内はメンバーの松永みよ子さんがおこなわれました。
地質や岩石については廣田さんが説明をされました。
案内では 主な見学地:芦北の銅山痕とありましたので銅の鉱山跡を巡るものだと思っていましたが当日の予定では坂本町市ノ俣(マンガン)、芦北郡芦北町箙瀬(えびらせ・マンガン)、葦北郡芦北町吉尾(銅)、八代市坂本町百済来(くたらぎ・マンガン)とずいぶん広範囲に回ることになっていました。最初に市ノ俣に行きましたが鉱山跡が見つからずに箙瀬に向かい鉱山は見つけましたが廃坑になっており中には入れませんでした。
廣田さんに頂いたレシピでは
●市ノ俣鉱山 鉱種名 マンガン 鉱山所在地 八代郡上松求麻市ノ俣 休山 昭和24頃は一時稼行 20t位採掘当時箙瀬(葦北郡吉尾村)折立 (球磨郡五木村)も同程度産出
●吉尾鉱山 鉱種名 銅 鉱山所在地 芦北郡吉尾村大岩 休山 昭24一時試掘したがそのまま休山
●大河地銅山
寛永14年(1637)3月、葦北大河内銅山を試掘し、芦北銅の試吹きを差し上げ,開発を継続することに決定し、同15年8月には、銅の生産1ヶ月に1500斤から1600斤と報告され、更に翌12年10月には、銅山奉行鳥巣羽右衛門から、葦北銅山8月1か月間の銅吹き2500斤と報告されている。宝暦12年(1762)6月には、田浦助兵衛が大河内銅山を自勘で掘方を願い出、採掘を再開している。文政10年(1827)には大河内の銅吹きが櫨方産物方の担当となり、翌11年には、葦北銅山の櫨方産物方の担当が中止され、11月から蝋締役が受継いでいる。
安政元年(1854)には、湯浦平生の江口純三郎が大河内銅山の掘方を引き受けている。以上の記録から、一時中断されているが、試掘から二百数十年の歴史がある。芦北郡誌には、吉尾銅山として、次のように書かれている。吉尾銅山は元、木の根銅山と称して大岩木の根 平にある。この銅山の発見されたことについては、一つの記録もないので、詳かに知ることは出来ないが、凡そ三百年ばかり以前の発見であることが想像される。伝えるところによると、旧熊本藩主の経営であったが、幕府からの中止の命により、一旦廃鉱になったということである。明治7年阿蘇商社の経営によって再興した。これにより先英国人が再度来訪して調査した、その後数回開掘精煉し、近く は久原鉱業株式会社の経営の下に開掘し、其鉱石を佐賀関精煉所へ輸送したこともある。
銅鉱は黄銅鉱で平均含量9%をしめすという。(農商務省地質調査所分析)
となっています。
 芦北町銅山(かなやま)集落での説明
芦北町銅山(かなやま)集落での説明
 立ち入り禁止
立ち入り禁止
 銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい
銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい
 地元の方にも鉱山の話を聞きました
地元の方にも鉱山の話を聞きました

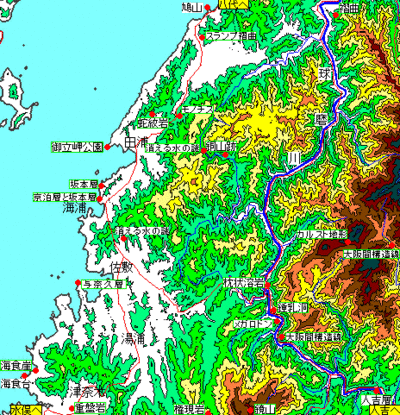 芦北地方
芦北地方
山がちな地形
「リアス式海岸」・・・海岸線は沈降海岸の様相。
t太郎」・・・「太郎」とは峠を意味する古い言葉で古来陸の難所であった。国道3号線では水俣までに赤松太郎・佐敷太郎・津奈木太郎の3つの大きなトンネルをくぐることになる。
「地質」・・・この地域では,北部と南部で地質が大きく異なっている。
北部では古生代から中生代にかけての地層が西南日本外帯共通の構造である,北東-南西の方向性をもって分布している。一方,南部は肥薩火山区に属する火山からの噴出物が地表を広くおおっており,独特の火山地形を作っています。この北部と南部の地質の違いは,地形にもはっきりと現れている。
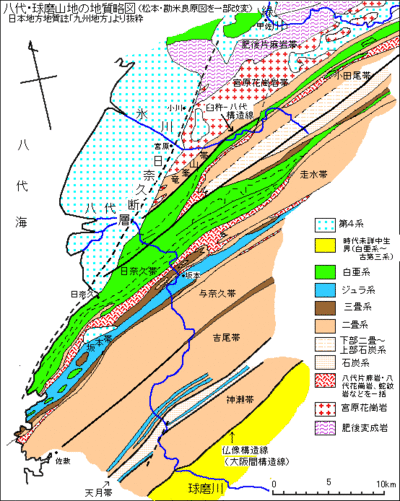

葦北海岸方面の地史
地層は人吉・球磨地方と同じ秩父累帯が分布していますが,その様子は北から南に向かって順に黒瀬川構造帯(シルル紀~白亜紀)・三宝山帯(下部三畳紀~上部ジュラ紀)となる。
[八代・球磨山地の地質略図][八代・球磨山地の地質帯の区分図]
黒瀬川構造帯では北から南に向かって宮地帯、日奈久帯、坂本帯に区分され、それらに分布する中生界は南ほど古くなる。
( 御立岬の日奈久層 )( 坂本層 )
三宝山帯では北から南に向かって与奈久層・吉尾層・神瀬層の順に新しい地層となり,仏像構造線(大坂間構造線)を境にして四万十累帯になります。
( 与奈久層と吉尾層 )
■伝統の名紙、『大河内紙』(おかわちがみ)とは・・・・
熊本県芦北町の北部、標高150mに
位置する銅山(かなやま)地区は、周囲を山林に覆われた素朴で静かな山村集落です。
集落を流れる吉尾川は、夏に蛍が乱舞し、河鹿が鳴く清流として有名です。
この銅山(かなやま)集落には、昭和初期まで和紙「大河内紙」の生産が営まれていました。


 和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。
和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。

芦北町の銅山集落はいまでも和紙を生産しています。
地元の学校では卒業証書などに使われているそうです。
今回は地学の話よりも大河内紙などの伝統工芸の話に時間が取られました。
熊本県・芦北町・銅山集落全景・・・集落の宣伝です
ふるさとの「大河内紙」は、製法も出来上がりも原始的に近く、江戸末期、安政年 間には製作されていた記録が現在でも残っています。
殆ど改良も加えられないまま代々伝えられ、地区の冬場の産業として栄え、丈夫 で防虫効果があり、障子紙として製造販売され、強くて破れにくく、―度はっ たら数年は持ち、とても好評で重宝されていました。
また、米等の穀物、乾物の保存袋《ドダイ装》として販売され、冬場の産業 として成り立っていました。
 米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。
米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。
和紙保存会では、芦北町の名紙である和紙「大河内紙」の製作体験を目的に、素 朴で温かみある、手漉き和紙発祥の地、芦北町銅山(かなやま)集落へ、この機会にお越しいただき まして、田舎の素朴さ、歴史ある本格手づくり工芸、人情味ある地区民とのふれあい、 などに親しんでいただきたいと考えております。
都会を脱し、時が止まった"田舎"を体感し、心身のリフレッシュを図ってみませんか!
また、お茶摘み、たけのこ堀り、和紙原料の"カジ"切り等の"季節の旬"を体験・ 味わえるコ―スも準備しております。
 マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)
マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)
松永みよ子さんの実家は吉尾にありすぐ傍にある小さな小川からいろいろな石が流れてくるらしい。
廣田さんの話では坂本から芦北にかけての地層はすさまじく色々な地層が入り乱れている地形だと話されます。
松永さんの実家の傍の小川の上流あたりにマンガンの採掘坑があったのかも知れません。
今回は事務局の川路先生が体調不良のため道案内はメンバーの松永みよ子さんがおこなわれました。
地質や岩石については廣田さんが説明をされました。
案内では 主な見学地:芦北の銅山痕とありましたので銅の鉱山跡を巡るものだと思っていましたが当日の予定では坂本町市ノ俣(マンガン)、芦北郡芦北町箙瀬(えびらせ・マンガン)、葦北郡芦北町吉尾(銅)、八代市坂本町百済来(くたらぎ・マンガン)とずいぶん広範囲に回ることになっていました。最初に市ノ俣に行きましたが鉱山跡が見つからずに箙瀬に向かい鉱山は見つけましたが廃坑になっており中には入れませんでした。
廣田さんに頂いたレシピでは
●市ノ俣鉱山 鉱種名 マンガン 鉱山所在地 八代郡上松求麻市ノ俣 休山 昭和24頃は一時稼行 20t位採掘当時箙瀬(葦北郡吉尾村)折立 (球磨郡五木村)も同程度産出
●吉尾鉱山 鉱種名 銅 鉱山所在地 芦北郡吉尾村大岩 休山 昭24一時試掘したがそのまま休山
●大河地銅山
寛永14年(1637)3月、葦北大河内銅山を試掘し、芦北銅の試吹きを差し上げ,開発を継続することに決定し、同15年8月には、銅の生産1ヶ月に1500斤から1600斤と報告され、更に翌12年10月には、銅山奉行鳥巣羽右衛門から、葦北銅山8月1か月間の銅吹き2500斤と報告されている。宝暦12年(1762)6月には、田浦助兵衛が大河内銅山を自勘で掘方を願い出、採掘を再開している。文政10年(1827)には大河内の銅吹きが櫨方産物方の担当となり、翌11年には、葦北銅山の櫨方産物方の担当が中止され、11月から蝋締役が受継いでいる。
安政元年(1854)には、湯浦平生の江口純三郎が大河内銅山の掘方を引き受けている。以上の記録から、一時中断されているが、試掘から二百数十年の歴史がある。芦北郡誌には、吉尾銅山として、次のように書かれている。吉尾銅山は元、木の根銅山と称して大岩木の根 平にある。この銅山の発見されたことについては、一つの記録もないので、詳かに知ることは出来ないが、凡そ三百年ばかり以前の発見であることが想像される。伝えるところによると、旧熊本藩主の経営であったが、幕府からの中止の命により、一旦廃鉱になったということである。明治7年阿蘇商社の経営によって再興した。これにより先英国人が再度来訪して調査した、その後数回開掘精煉し、近く は久原鉱業株式会社の経営の下に開掘し、其鉱石を佐賀関精煉所へ輸送したこともある。
銅鉱は黄銅鉱で平均含量9%をしめすという。(農商務省地質調査所分析)
となっています。
 芦北町銅山(かなやま)集落での説明
芦北町銅山(かなやま)集落での説明 立ち入り禁止
立ち入り禁止 銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい
銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい 地元の方にも鉱山の話を聞きました
地元の方にも鉱山の話を聞きました
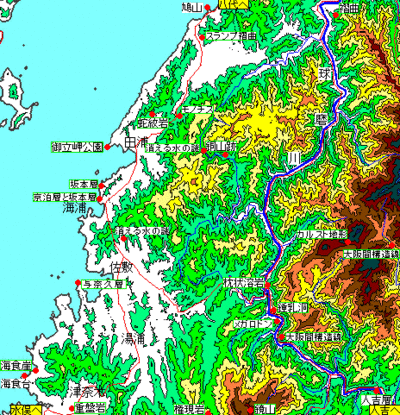 芦北地方
芦北地方山がちな地形
「リアス式海岸」・・・海岸線は沈降海岸の様相。
t太郎」・・・「太郎」とは峠を意味する古い言葉で古来陸の難所であった。国道3号線では水俣までに赤松太郎・佐敷太郎・津奈木太郎の3つの大きなトンネルをくぐることになる。
「地質」・・・この地域では,北部と南部で地質が大きく異なっている。
北部では古生代から中生代にかけての地層が西南日本外帯共通の構造である,北東-南西の方向性をもって分布している。一方,南部は肥薩火山区に属する火山からの噴出物が地表を広くおおっており,独特の火山地形を作っています。この北部と南部の地質の違いは,地形にもはっきりと現れている。
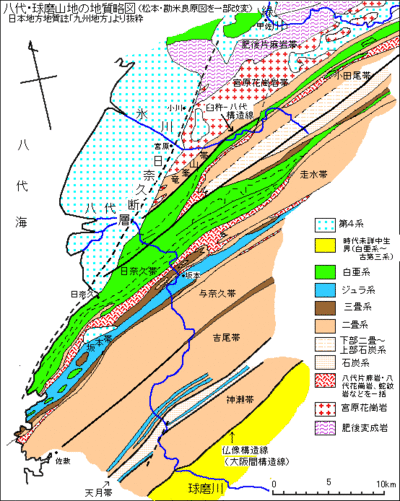

葦北海岸方面の地史
地層は人吉・球磨地方と同じ秩父累帯が分布していますが,その様子は北から南に向かって順に黒瀬川構造帯(シルル紀~白亜紀)・三宝山帯(下部三畳紀~上部ジュラ紀)となる。
[八代・球磨山地の地質略図][八代・球磨山地の地質帯の区分図]
黒瀬川構造帯では北から南に向かって宮地帯、日奈久帯、坂本帯に区分され、それらに分布する中生界は南ほど古くなる。
( 御立岬の日奈久層 )( 坂本層 )
三宝山帯では北から南に向かって与奈久層・吉尾層・神瀬層の順に新しい地層となり,仏像構造線(大坂間構造線)を境にして四万十累帯になります。
( 与奈久層と吉尾層 )
■伝統の名紙、『大河内紙』(おかわちがみ)とは・・・・
熊本県芦北町の北部、標高150mに
位置する銅山(かなやま)地区は、周囲を山林に覆われた素朴で静かな山村集落です。
集落を流れる吉尾川は、夏に蛍が乱舞し、河鹿が鳴く清流として有名です。
この銅山(かなやま)集落には、昭和初期まで和紙「大河内紙」の生産が営まれていました。


 和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。
和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。
芦北町の銅山集落はいまでも和紙を生産しています。
地元の学校では卒業証書などに使われているそうです。
今回は地学の話よりも大河内紙などの伝統工芸の話に時間が取られました。
熊本県・芦北町・銅山集落全景・・・集落の宣伝です
ふるさとの「大河内紙」は、製法も出来上がりも原始的に近く、江戸末期、安政年 間には製作されていた記録が現在でも残っています。
殆ど改良も加えられないまま代々伝えられ、地区の冬場の産業として栄え、丈夫 で防虫効果があり、障子紙として製造販売され、強くて破れにくく、―度はっ たら数年は持ち、とても好評で重宝されていました。
また、米等の穀物、乾物の保存袋《ドダイ装》として販売され、冬場の産業 として成り立っていました。
 米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。
米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。 和紙保存会では、芦北町の名紙である和紙「大河内紙」の製作体験を目的に、素 朴で温かみある、手漉き和紙発祥の地、芦北町銅山(かなやま)集落へ、この機会にお越しいただき まして、田舎の素朴さ、歴史ある本格手づくり工芸、人情味ある地区民とのふれあい、 などに親しんでいただきたいと考えております。
都会を脱し、時が止まった"田舎"を体感し、心身のリフレッシュを図ってみませんか!
また、お茶摘み、たけのこ堀り、和紙原料の"カジ"切り等の"季節の旬"を体験・ 味わえるコ―スも準備しております。
 マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)
マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)松永みよ子さんの実家は吉尾にありすぐ傍にある小さな小川からいろいろな石が流れてくるらしい。
廣田さんの話では坂本から芦北にかけての地層はすさまじく色々な地層が入り乱れている地形だと話されます。
松永さんの実家の傍の小川の上流あたりにマンガンの採掘坑があったのかも知れません。

身体の異変に気を付けないといけないのが丁度この時期、寒暖の差が激しい時には油断をするとふらついたりすることもある。気を付けているつもりでも四六時中、身体のことばかり思ってもいられない。最近特に身体の衰えを感じる。体力も然り。持続力も然り。何をするにしても自分ながら弱々しさを感じる。年齢的なことが関係しているのだろうけれど地球にも生命があるとすれば、地球の寿命ってどれくらいあるのだろうと考えさせられるような火山噴火についての記事である。

「よみうり寸評」12・2夕刊
火山の噴火はマグマが地表の近くに昇ってくることで起きる。これに伴い、地震が続いたり、山が膨張したりするので前兆を捉えやすいと言われる◆問題はその後だ。確実に噴火するのか。いつ噴火するのか。どれくらいの規模の噴火なのか。肝心なことが分からない◆今、大噴火が懸念されているインドネシア・バリ島のアグン山周辺の住民も悩んでいるのだろう。地震多発で政府が周辺8~10㌔圏に避難を呼びかけているが、依然4万人以上がとどまっているとされる。◆山頂から巨大な噴煙が上がる中、テレビ取材に「神様が決めること」と答える女性がいる。火山灰対策のマスクをした子供が学校で勉強する姿も映る。◆先月末に4段階の噴火警告レベルを3から最高の4に引き上げた政府は強制的な避難も検討中と伝えられる◆アグン山では1963年にも大噴火が起きた。高温の噴出物が斜面を掛け下る火砕流などで住民1000人以上が犠牲になった。大噴火せずに沈静化するのか、今後避難が進むのか。無事を祈る。
急に寒くなって12/1のゴルフは散々のスコアーであった。気持ちだけは何時までも若いと思っているとゴルフどころじゃなくてとんでもない目に合うというのが今日のお話。新聞は朝刊だけしかとっていないので夕刊の記事は見ることが出来ません。朝刊の2面に夕刊の担当者が書いた寸評というものがあります。毎日ではなく週に5日ほどは転載されています。読みやすい記事なので朝刊の編集手帳と共に楽しみに読んでいます。

「よみうり寸評」12・1夕刊
ゆでガエルの話はご存じだろう。カエルを熱湯に入れると驚いて飛び出すが、水から温めるとゆだってしまう◆じわじわと忍び寄る危機への注意を促す例え話だが、逆の教訓もある。零下10度の環境下にネズミを置く。徐々に温度を下げると生きているが、いきなりだと死ぬ。そんな話を齋藤茂太さんの本で読んだ(「あきらめる」のが上手な人下手な人)◆12月、ヒートショックが心配な季節になった。温かい部屋から寒い脱衣所に移る時、冷えた体で熱い湯につかる時・・・血圧や脈拍数の変動から生死に関わる事態が起きかねない。この場合、用心すべきは急激な温度変化である◆じわじわも、実は危ないらしい。この季節は水分補給を怠りがちだ。長時間、入浴したり暖房のきいた場所にいたりすると脱水症状が忍び寄る。「冬の熱中症注意」と警告したのは昨冬の記事(大阪本社版)だった◆東京消防庁では昨年11月~今年4月の半年間に、51人を熱中症で救急搬送したという。暖急二通りの危機への対処が欠かせない。
齋藤茂太
(さいとう しげた、1916年3月21日 - 2006年11月20日)日本の精神科医、随筆家である。
1916年(大正5年)、歌人で精神科医の斎藤茂吉の長男として東京市(当時)に生まれる。
出身校
昭和医学専門学校、慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程
職業
医師、随筆家

愛称はモタさん
著書
『茂吉の体臭』岩波書店/1964年
『精神科の待合室』中央公論社/1974年
『躁と鬱 -波動に生きる-』中央公論新社/1980年6月
『長男の本 みんな元気に蘇れ』情報センター出版局/1980年9月
『モタさんのヒコーキ談義』旺文社/1982年8月
『世界のクルーズ客船 中村庸夫写真集』(共著:中村庸夫、柳原良平)海事プレス社/1991年6月
『心のウサが晴れる本』PHP文庫/1992年11月
『人間的魅力の育て方』三笠書房/1995年2月
『脳を鍛える50の秘訣』成美堂出版/1997年4月
『「なぜか人に好かれる人」の共通点』新講社/1999年8月
『骨は自分で拾えない』集英社/2000年6月
『女の子がすくすく育つ親の躾け方』KKベストセラーズ ワニ文庫/2000年8月
『斎藤茂太vs梅原猛 旅・酒・文化のシンポジア』(久野昭編)南窓社/2000年12月
『時間の使い方うまい人・へたな人』三笠書房/2001年4月
『気持ちの整理 -不思議なくらい前向きになる94のヒント-』三笠書房/2003年2月
『快老生活の心得』角川書店/2003年2月
『不完璧主義』家の光協会/2004年5月
『無理せず、苦労せず、楽しく生きるコツ』文香社/2004年7月
『モタさんの快老物語』中央公論新社/2004年11月
『いい言葉は、いい人生をつくる』成美堂出版/2005年1月
『図解グズをなおせば人生はうまくいく』大和書房/2005年2月
『モタさんの10倍ツキを呼ぶ50の言葉―毎日がこんなに変わる!楽天発想』知的生きかた文庫/2006年6月
『「いい人だけどグズ」を直したい人が読む本』こう書房/2006年11月
『モタ先生と窓際OLの人づきあいがラクになる本』(共著:斎藤茂太・斎藤由香)集英社/2006年12月
『モタさんの“言葉”』(斎藤 茂太、松本春野)講談社
・『自分らしく生きて、死ぬ知恵』(遺作 2006年10月著)中経出版2010年2月発行

「よみうり寸評」12・1夕刊
ゆでガエルの話はご存じだろう。カエルを熱湯に入れると驚いて飛び出すが、水から温めるとゆだってしまう◆じわじわと忍び寄る危機への注意を促す例え話だが、逆の教訓もある。零下10度の環境下にネズミを置く。徐々に温度を下げると生きているが、いきなりだと死ぬ。そんな話を齋藤茂太さんの本で読んだ(「あきらめる」のが上手な人下手な人)◆12月、ヒートショックが心配な季節になった。温かい部屋から寒い脱衣所に移る時、冷えた体で熱い湯につかる時・・・血圧や脈拍数の変動から生死に関わる事態が起きかねない。この場合、用心すべきは急激な温度変化である◆じわじわも、実は危ないらしい。この季節は水分補給を怠りがちだ。長時間、入浴したり暖房のきいた場所にいたりすると脱水症状が忍び寄る。「冬の熱中症注意」と警告したのは昨冬の記事(大阪本社版)だった◆東京消防庁では昨年11月~今年4月の半年間に、51人を熱中症で救急搬送したという。暖急二通りの危機への対処が欠かせない。
齋藤茂太
(さいとう しげた、1916年3月21日 - 2006年11月20日)日本の精神科医、随筆家である。
1916年(大正5年)、歌人で精神科医の斎藤茂吉の長男として東京市(当時)に生まれる。
出身校
昭和医学専門学校、慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程
職業
医師、随筆家

愛称はモタさん
著書
『茂吉の体臭』岩波書店/1964年
『精神科の待合室』中央公論社/1974年
『躁と鬱 -波動に生きる-』中央公論新社/1980年6月
『長男の本 みんな元気に蘇れ』情報センター出版局/1980年9月
『モタさんのヒコーキ談義』旺文社/1982年8月
『世界のクルーズ客船 中村庸夫写真集』(共著:中村庸夫、柳原良平)海事プレス社/1991年6月
『心のウサが晴れる本』PHP文庫/1992年11月
『人間的魅力の育て方』三笠書房/1995年2月
『脳を鍛える50の秘訣』成美堂出版/1997年4月
『「なぜか人に好かれる人」の共通点』新講社/1999年8月
『骨は自分で拾えない』集英社/2000年6月
『女の子がすくすく育つ親の躾け方』KKベストセラーズ ワニ文庫/2000年8月
『斎藤茂太vs梅原猛 旅・酒・文化のシンポジア』(久野昭編)南窓社/2000年12月
『時間の使い方うまい人・へたな人』三笠書房/2001年4月
『気持ちの整理 -不思議なくらい前向きになる94のヒント-』三笠書房/2003年2月
『快老生活の心得』角川書店/2003年2月
『不完璧主義』家の光協会/2004年5月
『無理せず、苦労せず、楽しく生きるコツ』文香社/2004年7月
『モタさんの快老物語』中央公論新社/2004年11月
『いい言葉は、いい人生をつくる』成美堂出版/2005年1月
『図解グズをなおせば人生はうまくいく』大和書房/2005年2月
『モタさんの10倍ツキを呼ぶ50の言葉―毎日がこんなに変わる!楽天発想』知的生きかた文庫/2006年6月
『「いい人だけどグズ」を直したい人が読む本』こう書房/2006年11月
『モタ先生と窓際OLの人づきあいがラクになる本』(共著:斎藤茂太・斎藤由香)集英社/2006年12月
『モタさんの“言葉”』(斎藤 茂太、松本春野)講談社
・『自分らしく生きて、死ぬ知恵』(遺作 2006年10月著)中経出版2010年2月発行
 饅頭を発売した会社社長が受賞者になりました。
饅頭を発売した会社社長が受賞者になりました。今年の流行語大賞に「インスタ映え」 「忖度」が選ばれて1日に発表されました。
★インスタ映え
若い世代に人気の画像共有サービス「インスタグラム」での目を引く食べ物や場所や構図を指す言葉。
★忖度
相手の気持ちを推し量ること、森友・加計学園問題を巡る国会審議などでたびたび取り上げられた。
他に対象以外のものとして
●35億●Jアラート●睡眠負債●ひふみん●フェイクニュース●プレミアムフライデー●魔の2回生●○○ファースト
がトップ10として選ばれました。
流行語大賞対象に対象者があるなんて今まで気がつきませんでした。
今日から師走。
皆さん年賀状は何時作られますか。
わが家はいつもはもうとっくに年賀状は出来上がっているのですが今年は段取りが悪く現在作成中です。

現在、年賀状の裏面と住所録が出来上がったところ、完成まであと何日かかかりそう。
先ほどまでゴルフの忘年コンペ、明日は県の古文書講座、3日は地学の研修、ちょっと私にしては忙しい毎日が続きます。
皆さん年賀状は何時作られますか。
わが家はいつもはもうとっくに年賀状は出来上がっているのですが今年は段取りが悪く現在作成中です。

現在、年賀状の裏面と住所録が出来上がったところ、完成まであと何日かかかりそう。
先ほどまでゴルフの忘年コンペ、明日は県の古文書講座、3日は地学の研修、ちょっと私にしては忙しい毎日が続きます。




