12月の第一日曜日(12/3)は熊本の大地(地学)の現地学習がありました。
今回は事務局の川路先生が体調不良のため道案内はメンバーの松永みよ子さんがおこなわれました。
地質や岩石については廣田さんが説明をされました。
案内では 主な見学地:芦北の銅山痕とありましたので銅の鉱山跡を巡るものだと思っていましたが当日の予定では坂本町市ノ俣(マンガン)、芦北郡芦北町箙瀬(えびらせ・マンガン)、葦北郡芦北町吉尾(銅)、八代市坂本町百済来(くたらぎ・マンガン)とずいぶん広範囲に回ることになっていました。最初に市ノ俣に行きましたが鉱山跡が見つからずに箙瀬に向かい鉱山は見つけましたが廃坑になっており中には入れませんでした。
廣田さんに頂いたレシピでは
●市ノ俣鉱山 鉱種名 マンガン 鉱山所在地 八代郡上松求麻市ノ俣 休山 昭和24頃は一時稼行 20t位採掘当時箙瀬(葦北郡吉尾村)折立 (球磨郡五木村)も同程度産出
●吉尾鉱山 鉱種名 銅 鉱山所在地 芦北郡吉尾村大岩 休山 昭24一時試掘したがそのまま休山
●大河地銅山
寛永14年(1637)3月、葦北大河内銅山を試掘し、芦北銅の試吹きを差し上げ,開発を継続することに決定し、同15年8月には、銅の生産1ヶ月に1500斤から1600斤と報告され、更に翌12年10月には、銅山奉行鳥巣羽右衛門から、葦北銅山8月1か月間の銅吹き2500斤と報告されている。宝暦12年(1762)6月には、田浦助兵衛が大河内銅山を自勘で掘方を願い出、採掘を再開している。文政10年(1827)には大河内の銅吹きが櫨方産物方の担当となり、翌11年には、葦北銅山の櫨方産物方の担当が中止され、11月から蝋締役が受継いでいる。
安政元年(1854)には、湯浦平生の江口純三郎が大河内銅山の掘方を引き受けている。以上の記録から、一時中断されているが、試掘から二百数十年の歴史がある。芦北郡誌には、吉尾銅山として、次のように書かれている。吉尾銅山は元、木の根銅山と称して大岩木の根 平にある。この銅山の発見されたことについては、一つの記録もないので、詳かに知ることは出来ないが、凡そ三百年ばかり以前の発見であることが想像される。伝えるところによると、旧熊本藩主の経営であったが、幕府からの中止の命により、一旦廃鉱になったということである。明治7年阿蘇商社の経営によって再興した。これにより先英国人が再度来訪して調査した、その後数回開掘精煉し、近く は久原鉱業株式会社の経営の下に開掘し、其鉱石を佐賀関精煉所へ輸送したこともある。
銅鉱は黄銅鉱で平均含量9%をしめすという。(農商務省地質調査所分析)
となっています。
 芦北町銅山(かなやま)集落での説明
芦北町銅山(かなやま)集落での説明
 立ち入り禁止
立ち入り禁止
 銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい
銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい
 地元の方にも鉱山の話を聞きました
地元の方にも鉱山の話を聞きました

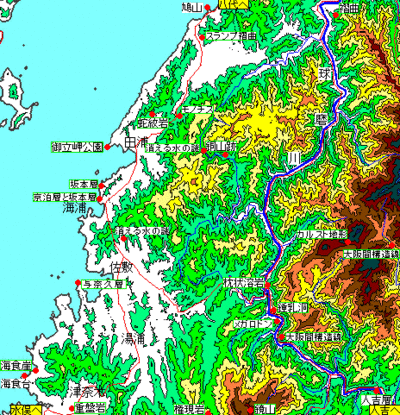 芦北地方
芦北地方
山がちな地形
「リアス式海岸」・・・海岸線は沈降海岸の様相。
t太郎」・・・「太郎」とは峠を意味する古い言葉で古来陸の難所であった。国道3号線では水俣までに赤松太郎・佐敷太郎・津奈木太郎の3つの大きなトンネルをくぐることになる。
「地質」・・・この地域では,北部と南部で地質が大きく異なっている。
北部では古生代から中生代にかけての地層が西南日本外帯共通の構造である,北東-南西の方向性をもって分布している。一方,南部は肥薩火山区に属する火山からの噴出物が地表を広くおおっており,独特の火山地形を作っています。この北部と南部の地質の違いは,地形にもはっきりと現れている。
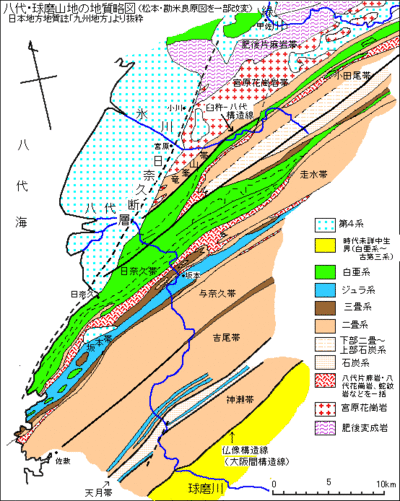

葦北海岸方面の地史
地層は人吉・球磨地方と同じ秩父累帯が分布していますが,その様子は北から南に向かって順に黒瀬川構造帯(シルル紀~白亜紀)・三宝山帯(下部三畳紀~上部ジュラ紀)となる。
[八代・球磨山地の地質略図][八代・球磨山地の地質帯の区分図]
黒瀬川構造帯では北から南に向かって宮地帯、日奈久帯、坂本帯に区分され、それらに分布する中生界は南ほど古くなる。
( 御立岬の日奈久層 )( 坂本層 )
三宝山帯では北から南に向かって与奈久層・吉尾層・神瀬層の順に新しい地層となり,仏像構造線(大坂間構造線)を境にして四万十累帯になります。
( 与奈久層と吉尾層 )
■伝統の名紙、『大河内紙』(おかわちがみ)とは・・・・
熊本県芦北町の北部、標高150mに
位置する銅山(かなやま)地区は、周囲を山林に覆われた素朴で静かな山村集落です。
集落を流れる吉尾川は、夏に蛍が乱舞し、河鹿が鳴く清流として有名です。
この銅山(かなやま)集落には、昭和初期まで和紙「大河内紙」の生産が営まれていました。


 和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。
和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。

芦北町の銅山集落はいまでも和紙を生産しています。
地元の学校では卒業証書などに使われているそうです。
今回は地学の話よりも大河内紙などの伝統工芸の話に時間が取られました。
熊本県・芦北町・銅山集落全景・・・集落の宣伝です
ふるさとの「大河内紙」は、製法も出来上がりも原始的に近く、江戸末期、安政年 間には製作されていた記録が現在でも残っています。
殆ど改良も加えられないまま代々伝えられ、地区の冬場の産業として栄え、丈夫 で防虫効果があり、障子紙として製造販売され、強くて破れにくく、―度はっ たら数年は持ち、とても好評で重宝されていました。
また、米等の穀物、乾物の保存袋《ドダイ装》として販売され、冬場の産業 として成り立っていました。
 米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。
米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。
和紙保存会では、芦北町の名紙である和紙「大河内紙」の製作体験を目的に、素 朴で温かみある、手漉き和紙発祥の地、芦北町銅山(かなやま)集落へ、この機会にお越しいただき まして、田舎の素朴さ、歴史ある本格手づくり工芸、人情味ある地区民とのふれあい、 などに親しんでいただきたいと考えております。
都会を脱し、時が止まった"田舎"を体感し、心身のリフレッシュを図ってみませんか!
また、お茶摘み、たけのこ堀り、和紙原料の"カジ"切り等の"季節の旬"を体験・ 味わえるコ―スも準備しております。
 マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)
マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)
松永みよ子さんの実家は吉尾にありすぐ傍にある小さな小川からいろいろな石が流れてくるらしい。
廣田さんの話では坂本から芦北にかけての地層はすさまじく色々な地層が入り乱れている地形だと話されます。
松永さんの実家の傍の小川の上流あたりにマンガンの採掘坑があったのかも知れません。
今回は事務局の川路先生が体調不良のため道案内はメンバーの松永みよ子さんがおこなわれました。
地質や岩石については廣田さんが説明をされました。
案内では 主な見学地:芦北の銅山痕とありましたので銅の鉱山跡を巡るものだと思っていましたが当日の予定では坂本町市ノ俣(マンガン)、芦北郡芦北町箙瀬(えびらせ・マンガン)、葦北郡芦北町吉尾(銅)、八代市坂本町百済来(くたらぎ・マンガン)とずいぶん広範囲に回ることになっていました。最初に市ノ俣に行きましたが鉱山跡が見つからずに箙瀬に向かい鉱山は見つけましたが廃坑になっており中には入れませんでした。
廣田さんに頂いたレシピでは
●市ノ俣鉱山 鉱種名 マンガン 鉱山所在地 八代郡上松求麻市ノ俣 休山 昭和24頃は一時稼行 20t位採掘当時箙瀬(葦北郡吉尾村)折立 (球磨郡五木村)も同程度産出
●吉尾鉱山 鉱種名 銅 鉱山所在地 芦北郡吉尾村大岩 休山 昭24一時試掘したがそのまま休山
●大河地銅山
寛永14年(1637)3月、葦北大河内銅山を試掘し、芦北銅の試吹きを差し上げ,開発を継続することに決定し、同15年8月には、銅の生産1ヶ月に1500斤から1600斤と報告され、更に翌12年10月には、銅山奉行鳥巣羽右衛門から、葦北銅山8月1か月間の銅吹き2500斤と報告されている。宝暦12年(1762)6月には、田浦助兵衛が大河内銅山を自勘で掘方を願い出、採掘を再開している。文政10年(1827)には大河内の銅吹きが櫨方産物方の担当となり、翌11年には、葦北銅山の櫨方産物方の担当が中止され、11月から蝋締役が受継いでいる。
安政元年(1854)には、湯浦平生の江口純三郎が大河内銅山の掘方を引き受けている。以上の記録から、一時中断されているが、試掘から二百数十年の歴史がある。芦北郡誌には、吉尾銅山として、次のように書かれている。吉尾銅山は元、木の根銅山と称して大岩木の根 平にある。この銅山の発見されたことについては、一つの記録もないので、詳かに知ることは出来ないが、凡そ三百年ばかり以前の発見であることが想像される。伝えるところによると、旧熊本藩主の経営であったが、幕府からの中止の命により、一旦廃鉱になったということである。明治7年阿蘇商社の経営によって再興した。これにより先英国人が再度来訪して調査した、その後数回開掘精煉し、近く は久原鉱業株式会社の経営の下に開掘し、其鉱石を佐賀関精煉所へ輸送したこともある。
銅鉱は黄銅鉱で平均含量9%をしめすという。(農商務省地質調査所分析)
となっています。
 芦北町銅山(かなやま)集落での説明
芦北町銅山(かなやま)集落での説明 立ち入り禁止
立ち入り禁止 銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい
銅を含む鉱石普通の石よりもかなり重たい 地元の方にも鉱山の話を聞きました
地元の方にも鉱山の話を聞きました
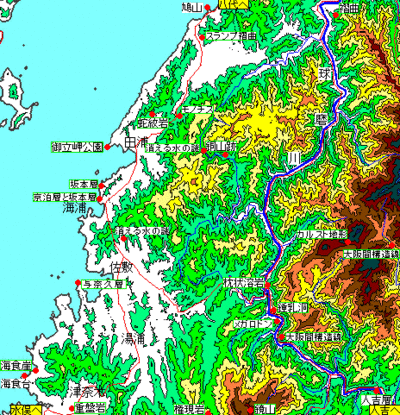 芦北地方
芦北地方山がちな地形
「リアス式海岸」・・・海岸線は沈降海岸の様相。
t太郎」・・・「太郎」とは峠を意味する古い言葉で古来陸の難所であった。国道3号線では水俣までに赤松太郎・佐敷太郎・津奈木太郎の3つの大きなトンネルをくぐることになる。
「地質」・・・この地域では,北部と南部で地質が大きく異なっている。
北部では古生代から中生代にかけての地層が西南日本外帯共通の構造である,北東-南西の方向性をもって分布している。一方,南部は肥薩火山区に属する火山からの噴出物が地表を広くおおっており,独特の火山地形を作っています。この北部と南部の地質の違いは,地形にもはっきりと現れている。
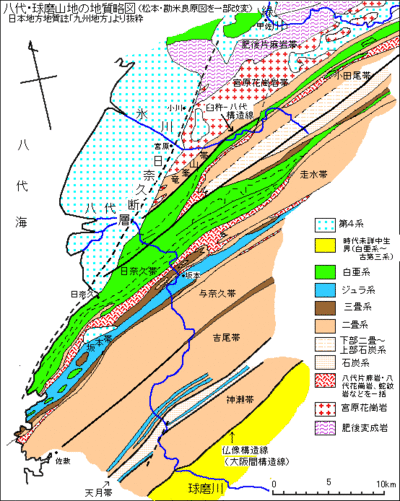

葦北海岸方面の地史
地層は人吉・球磨地方と同じ秩父累帯が分布していますが,その様子は北から南に向かって順に黒瀬川構造帯(シルル紀~白亜紀)・三宝山帯(下部三畳紀~上部ジュラ紀)となる。
[八代・球磨山地の地質略図][八代・球磨山地の地質帯の区分図]
黒瀬川構造帯では北から南に向かって宮地帯、日奈久帯、坂本帯に区分され、それらに分布する中生界は南ほど古くなる。
( 御立岬の日奈久層 )( 坂本層 )
三宝山帯では北から南に向かって与奈久層・吉尾層・神瀬層の順に新しい地層となり,仏像構造線(大坂間構造線)を境にして四万十累帯になります。
( 与奈久層と吉尾層 )
■伝統の名紙、『大河内紙』(おかわちがみ)とは・・・・
熊本県芦北町の北部、標高150mに
位置する銅山(かなやま)地区は、周囲を山林に覆われた素朴で静かな山村集落です。
集落を流れる吉尾川は、夏に蛍が乱舞し、河鹿が鳴く清流として有名です。
この銅山(かなやま)集落には、昭和初期まで和紙「大河内紙」の生産が営まれていました。


 和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。
和紙の原料になる楮(こうぞ)の葉です。
芦北町の銅山集落はいまでも和紙を生産しています。
地元の学校では卒業証書などに使われているそうです。
今回は地学の話よりも大河内紙などの伝統工芸の話に時間が取られました。
熊本県・芦北町・銅山集落全景・・・集落の宣伝です
ふるさとの「大河内紙」は、製法も出来上がりも原始的に近く、江戸末期、安政年 間には製作されていた記録が現在でも残っています。
殆ど改良も加えられないまま代々伝えられ、地区の冬場の産業として栄え、丈夫 で防虫効果があり、障子紙として製造販売され、強くて破れにくく、―度はっ たら数年は持ち、とても好評で重宝されていました。
また、米等の穀物、乾物の保存袋《ドダイ装》として販売され、冬場の産業 として成り立っていました。
 米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。
米俵の中に和紙が使われていたことは初めて知りました。 和紙保存会では、芦北町の名紙である和紙「大河内紙」の製作体験を目的に、素 朴で温かみある、手漉き和紙発祥の地、芦北町銅山(かなやま)集落へ、この機会にお越しいただき まして、田舎の素朴さ、歴史ある本格手づくり工芸、人情味ある地区民とのふれあい、 などに親しんでいただきたいと考えております。
都会を脱し、時が止まった"田舎"を体感し、心身のリフレッシュを図ってみませんか!
また、お茶摘み、たけのこ堀り、和紙原料の"カジ"切り等の"季節の旬"を体験・ 味わえるコ―スも準備しております。
 マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)
マンガン鉱(松永みよ子さんのコレクション)松永みよ子さんの実家は吉尾にありすぐ傍にある小さな小川からいろいろな石が流れてくるらしい。
廣田さんの話では坂本から芦北にかけての地層はすさまじく色々な地層が入り乱れている地形だと話されます。
松永さんの実家の傍の小川の上流あたりにマンガンの採掘坑があったのかも知れません。



