朝の散歩で八高周辺を歩いてみると、子供たちが運動服に着替えて運動場に集まっています。一瞬運動会かなと思ってよく眺めてみると父兄の姿がどこにも見当たりません。しかし、水筒やリュックなどはまとめて置いてあります。そう言えば福岡に居る高校生の孫も、今日が運動会なので見に来ないかと誘いがありました。今日は家内の目の手術があり行けなかったことを思い出しました。世間は運動会のシーズンです。
八高の近所の人に聞いてみましたが運動会らしいがいつもと様子が違うと話されていました。
正門には何も貼紙はなかったな・・?





中学生も高校生も全校生が集まっているようなので予行演習かも知れません。
八高の近所の人に聞いてみましたが運動会らしいがいつもと様子が違うと話されていました。
正門には何も貼紙はなかったな・・?





中学生も高校生も全校生が集まっているようなので予行演習かも知れません。
写真を見て何を感じますか?

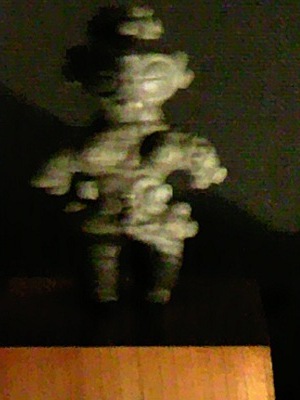








































三内丸山遺跡には青森へ到着した当日と最終日の2回に分けて見学しました。到着した日、遺跡を一通り見て廻り、縄文時遊館にも立ち寄って、遺跡から出土したもので一番気を引いたものが土偶でした。弥生時代にはほとんど見かけないものです。そんなきっかけもあって、今回立ち寄った資料館では土偶の写真を主に撮ることにしました。土偶は板のように平たく十字型をしたものがほとんどで円筒土器文化特有のもので「板状土偶」とよばれています。胸とおへその表現がある事から女性を表していると考えられています。土偶は壊れた状態で発見されることが多くわざと壊されたようにも考えられ祭祀に使われた可能性が高いと考えられています。三内丸山遺跡では縄文時代前期末ごろから薄い板状の十字形をした土偶が作られるようになり両手を横に広げたような形をしており足のないものが多いのですが中期の終わり頃には立つものも見られます。
子孫の繁栄や自然の豊饒(ほうじょう)を祈願する際の道具あるいは地母神を表したなどの 説があります。
土偶が作られる以前は数は少ないものの軟質の石材を利用した石製の人形が作られました。菱形状に人体を表し、顔の表現や手足のないものが大半です。中期に入り土偶が増加すると岩偶は減少します。用途は土偶と同じと考えられています。
東奥日報社発行 特別史跡三内丸山遺跡という本に青森県教育庁文化財保護課総括主幹の小笠原雅行さんがまとめられた縄文コラム「土偶」の記事があります。大変わかり易く書かれているので抜き取ってみました。
三内丸山遺跡では、これまで国内最多の2000点以上の土偶が出土しています。土偶はその字のごとく人形(ひとがた)を表しています。縄文時代に登場し、弥生時代になると極端に減少することから、縄文文化を特徴づける遺物の一つと言えます。
遺跡を調査すると、鍋や容器としての土器、狩猟や食料加工などの石器は好く出土しますが、土偶が出土することは多くはあ りません。土偶が増える縄文時代中期の遺跡は約600ヶ所確認されていますが、土偶が出土したのはその10%程度です。また、10点以上となるとわずか10遺跡程です。
三内丸山遺跡を除くと、県内で円筒土器文化期の土偶は300 点強見つかっていますが、その四分の一が青森市三内周辺に集中しています。三内丸山遺跡の土偶の点数がいかに突出しているかとともに近隣も合わせて土偶の集中域となっていることがわかります。
では、膨大な数の土偶はすべて三内丸山遺跡でつくられ、使われたのでしょうか。土偶の土の分析を行ったところ、分析対象のうち15%程度の土偶で土の成分が異なるという結果となりました。つまり、土偶の中には他の地域から持ち込まれたものが含まれている可能性があります。それがどこからなのか、逆に三内丸山遺跡から持ち出されたものはないのかなど、今後の課題と言えます。
大きさは最大32.5センチ、最小3.7センチと多様で、大中小のつくり分けがなされているようです。脚部の破片では、最大の土偶を凌ぐ大きさのものがあります。形状に極端な違いがなく、横幅に相関があると仮定すれば、高さが40センチを超えるとみられるものもあるようです。
土偶は希少なものであることから、生活必需品ではなく、精神文化に関わる道具と考えられています。後の合掌土偶や遮光器土偶など、非常に精巧につくられ、赤く塗られるものへと発展していくことを考えても、単なる玩具ではない強い精神性が感じられます。
精神文化は、定住により発達・進展したものと考えられています。集団の維持・安定、傷病の回復、自然への畏怖や感謝など、願望や思いを成就するために、日常的にあるいは季節などの節目ごとに様々な儀式・儀礼が行われたものと考えられます。
三内丸山遺跡では集落規模の増大や充実に伴い、精神文化も複雑化し、その一端を示すのが土偶です。一集落内や周辺地域にとどまらず、円筒土器文化圏内の中での心の拠りどころとなった、遺跡の性格の一面を示すものといえるのではないでしょうか。

知恵や道具を使うのは人間特有のものではありません。旧石器時代から縄文時代にかけて地球の気候は氷河期が終わり温暖化が進み自然の環境が変わったことから縄文の人達の生活の在り方もどんどん変わって行きました。それから1万5千年かけて今の私たちがいます。
どこがどれほど変わったのでしょうか?・・
便利さだけを追い求めて来たようにも思うのですが。

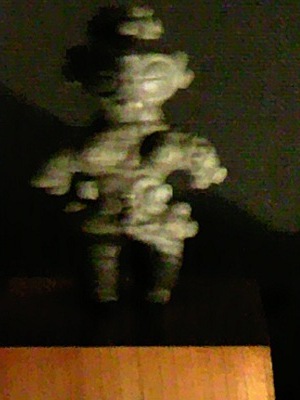








































三内丸山遺跡には青森へ到着した当日と最終日の2回に分けて見学しました。到着した日、遺跡を一通り見て廻り、縄文時遊館にも立ち寄って、遺跡から出土したもので一番気を引いたものが土偶でした。弥生時代にはほとんど見かけないものです。そんなきっかけもあって、今回立ち寄った資料館では土偶の写真を主に撮ることにしました。土偶は板のように平たく十字型をしたものがほとんどで円筒土器文化特有のもので「板状土偶」とよばれています。胸とおへその表現がある事から女性を表していると考えられています。土偶は壊れた状態で発見されることが多くわざと壊されたようにも考えられ祭祀に使われた可能性が高いと考えられています。三内丸山遺跡では縄文時代前期末ごろから薄い板状の十字形をした土偶が作られるようになり両手を横に広げたような形をしており足のないものが多いのですが中期の終わり頃には立つものも見られます。
子孫の繁栄や自然の豊饒(ほうじょう)を祈願する際の道具あるいは地母神を表したなどの 説があります。
土偶が作られる以前は数は少ないものの軟質の石材を利用した石製の人形が作られました。菱形状に人体を表し、顔の表現や手足のないものが大半です。中期に入り土偶が増加すると岩偶は減少します。用途は土偶と同じと考えられています。
東奥日報社発行 特別史跡三内丸山遺跡という本に青森県教育庁文化財保護課総括主幹の小笠原雅行さんがまとめられた縄文コラム「土偶」の記事があります。大変わかり易く書かれているので抜き取ってみました。
三内丸山遺跡では、これまで国内最多の2000点以上の土偶が出土しています。土偶はその字のごとく人形(ひとがた)を表しています。縄文時代に登場し、弥生時代になると極端に減少することから、縄文文化を特徴づける遺物の一つと言えます。
遺跡を調査すると、鍋や容器としての土器、狩猟や食料加工などの石器は好く出土しますが、土偶が出土することは多くはあ りません。土偶が増える縄文時代中期の遺跡は約600ヶ所確認されていますが、土偶が出土したのはその10%程度です。また、10点以上となるとわずか10遺跡程です。
三内丸山遺跡を除くと、県内で円筒土器文化期の土偶は300 点強見つかっていますが、その四分の一が青森市三内周辺に集中しています。三内丸山遺跡の土偶の点数がいかに突出しているかとともに近隣も合わせて土偶の集中域となっていることがわかります。
では、膨大な数の土偶はすべて三内丸山遺跡でつくられ、使われたのでしょうか。土偶の土の分析を行ったところ、分析対象のうち15%程度の土偶で土の成分が異なるという結果となりました。つまり、土偶の中には他の地域から持ち込まれたものが含まれている可能性があります。それがどこからなのか、逆に三内丸山遺跡から持ち出されたものはないのかなど、今後の課題と言えます。
大きさは最大32.5センチ、最小3.7センチと多様で、大中小のつくり分けがなされているようです。脚部の破片では、最大の土偶を凌ぐ大きさのものがあります。形状に極端な違いがなく、横幅に相関があると仮定すれば、高さが40センチを超えるとみられるものもあるようです。
土偶は希少なものであることから、生活必需品ではなく、精神文化に関わる道具と考えられています。後の合掌土偶や遮光器土偶など、非常に精巧につくられ、赤く塗られるものへと発展していくことを考えても、単なる玩具ではない強い精神性が感じられます。
精神文化は、定住により発達・進展したものと考えられています。集団の維持・安定、傷病の回復、自然への畏怖や感謝など、願望や思いを成就するために、日常的にあるいは季節などの節目ごとに様々な儀式・儀礼が行われたものと考えられます。
三内丸山遺跡では集落規模の増大や充実に伴い、精神文化も複雑化し、その一端を示すのが土偶です。一集落内や周辺地域にとどまらず、円筒土器文化圏内の中での心の拠りどころとなった、遺跡の性格の一面を示すものといえるのではないでしょうか。

知恵や道具を使うのは人間特有のものではありません。旧石器時代から縄文時代にかけて地球の気候は氷河期が終わり温暖化が進み自然の環境が変わったことから縄文の人達の生活の在り方もどんどん変わって行きました。それから1万5千年かけて今の私たちがいます。
どこがどれほど変わったのでしょうか?・・
便利さだけを追い求めて来たようにも思うのですが。

今年は気候の移り変わりがいつもとは違う様な気がします。八代地方だけの現象かもしれませんが雨も少なかったし、暑さだけはとても厳しくエアコンに頼る日が長く続いたかと思えば、朝晩が涼しく感じる時期もいつもよりは早く感じたように思います。歳をとったせいでしょうか?
白露は、「はくろ」と読むもので、季節を表す言葉の一つです。
露、という漢字が入っているように、本格的な秋が訪れ朝になると草花に朝露が付き始める時期を指します。
では、白露にはそもそもどのような意味があるのでしょうか。また、白露は具体的にいつ頃のことを言うのでしょうか。
白露は毎年9月8日頃、もしくは9月8日から次の節気である「秋分」の前日までの期間を指します。
2017年は9月7日となっており、年によって1~2日程度のズレが生じます。
日中はまだまだ暑い盛りですが、朝晩は少しずつ冷たい空気を感じるようにもなり、草花に露が付き始める時期が白露です。
白露は、二十四節気の15番目にあたる秋の季語です。
暑さが処する(収まる・落ち着くという意味)「処暑」が過ぎ、昼と夜の長さが同じになる「秋分」の間で、空には夏の代名詞である入道雲の出番が減って、代わりに秋らしいうろこ雲が見られるようになります。
日が暮れるのも早く感じるようになり、ススキが黄金色に輝くのもこの季節。
それまでは朝からうだるような暑さを感じていたのに、白露の時期になると朝晩は少しひんやりと感じられることもあります。
白露は「陰気ようやく重なり、露凝って白し」から名付けられました。
暑さも少しずつ収まり始め、草花には朝露がつくようになるという意味があり、暑さの種類が変わったように感じられる季節です。


ワールドカントリークラブ(9/1)
ゴルフをするのには先月と比べれば涼しさは感じますがまだまだ空には秋の雲は見当たりません。


永碇から沖町にかけての田んぼは道路の片方はもうすでに稲刈りが済んでいて反対側はもう少し後のようです。

近所の空き家のススキはまだ穂も出ていません。
人間が体感で感じるものと自然界の様子は少し違うようです。



前日の夕焼けそして田んぼから八代市内の夜景。
散歩の終わりに月を探すと満月ですが7時なのにこの暗さ。夜の訪れがずいぶん早くなりました。
暦に春分とか夏至とか立秋とか白露などの名前が書かれているものを見かけますが何を意味しているのか分かっている様で詳しく理解していない人が大半だと思われます。
私もそのうちの一人です、以前に勉強をした様な気もするのですが何しろ忘れっぽいたちで暮らしの歳時記を覗いてみて改めて再確認したような次第です。
二十四節気(季節の指標)は太陽の動きをもとにしています。太陽が移動する天球上の道を黄道といい、黄道を24等分したものが二十四節気です。
黄道を夏至と冬至の「二至」で2等分
↓
さらに春分と秋分の「二分」で4等分
↓
それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬の「四立」を入れて「八節」とする
↓
一節は45日。これを15日ずつに3等分し「二十四節気」とする
↓
さらに5日ずつに3等分し、時候を表したものが「七十二候」
二十四節気は、毎年同じ時期に同じ節気がめぐってきます。そして、節気の間隔が一定で半月ごとの季節変化に対応できるので、天候に左右される農業の目安として大変便利なものでした。季節を知るよりどころでもあったため、天候や生き物の様子を表す名前がつけられ、今でも年中行事や時候の挨拶など色々なシーンで使われています。
各節気の期間は約15日ですが、毎年同じ日付とは限らないため、その年のカレンダーなどで確認してください。たとえば、カレンダーに「2月4日・立春」「2月19日・雨水」と記載してあったら、2月4日から2月18日までが立春です。


二至、二分、四立をいれて八節とし一節45日を三等分した15日ずつが二十四節気
私もそのうちの一人です、以前に勉強をした様な気もするのですが何しろ忘れっぽいたちで暮らしの歳時記を覗いてみて改めて再確認したような次第です。
二十四節気(季節の指標)は太陽の動きをもとにしています。太陽が移動する天球上の道を黄道といい、黄道を24等分したものが二十四節気です。
黄道を夏至と冬至の「二至」で2等分
↓
さらに春分と秋分の「二分」で4等分
↓
それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬の「四立」を入れて「八節」とする
↓
一節は45日。これを15日ずつに3等分し「二十四節気」とする
↓
さらに5日ずつに3等分し、時候を表したものが「七十二候」
二十四節気は、毎年同じ時期に同じ節気がめぐってきます。そして、節気の間隔が一定で半月ごとの季節変化に対応できるので、天候に左右される農業の目安として大変便利なものでした。季節を知るよりどころでもあったため、天候や生き物の様子を表す名前がつけられ、今でも年中行事や時候の挨拶など色々なシーンで使われています。
各節気の期間は約15日ですが、毎年同じ日付とは限らないため、その年のカレンダーなどで確認してください。たとえば、カレンダーに「2月4日・立春」「2月19日・雨水」と記載してあったら、2月4日から2月18日までが立春です。


二至、二分、四立をいれて八節とし一節45日を三等分した15日ずつが二十四節気
青森には先月22日~26日まで行ってきました。青森空港でレンタカーを借りて行動することにしました。初日と4日目は青森で宿泊先をとり中2日の宿泊先は秋田県鹿角市に旅館をとりました。鹿角市には特別史跡の大湯環状列石があります。遺跡に行きますとたまたま今年は猪が頻繁に出没する為遺跡の内部には入場禁止で入ることができませんでした。遺跡の入り口に大湯ストーンサークル館があり猪が入る心配もないのでここは空いていましたので立ち寄ってみました。
写真も遺跡の中には入れないのでサークル館に展示されている土器類とサークル館の周りだけは写真に収めることができました。



 日時計状組石
日時計状組石
 復元された竪穴式住居
復元された竪穴式住居
 大湯環状列石案内図
大湯環状列石案内図
 鹿角市教育委員会提供 航空写真
鹿角市教育委員会提供 航空写真
大湯環状列石は、野中堂、万座に所在する2つの環状列石を主体とする大規模な縄文時代後期(約4000年前)野遺跡です。環状列石の周辺についてはこれまでの調査により、建物跡、貯蔵穴などが規則的に分布する事がわかっています。史跡内からはさまざまなまつりや祈りに関わる遺構と遺物が発見されており、縄文時代の精神文化や社会構造を総合的に理解できる史跡として、重要視されています。
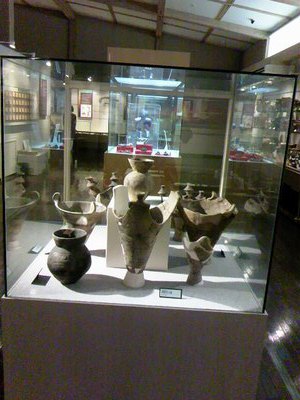 縄文人は自然のものを上手に活用して色々な道具を作りました。大湯環状列石から出土した土器などを展示してあります。
縄文人は自然のものを上手に活用して色々な道具を作りました。大湯環状列石から出土した土器などを展示してあります。


【大湯環状列石】
秋田県北東部、鹿角市の米代川上流に位置し、その支流である大湯川左岸、標高180m程の台地上に構築された、縄文時代後期前葉から中葉(紀元前2,000年~紀元前1,500年頃)の環状列石を中心とした遺跡です。
環状列石の形態は、定住とともに発達した集落形態である環状集落を背景としたものと考えられます。遺跡の中心として万座(まんざ)と野中堂(のなかどう)の二つの環状列石があり、それぞれの環状列石を取り囲むように、掘立柱建物跡、土坑・貯蔵穴、遺物廃棄域が同心円状に配置されています。これらの遺構とともに、日常使用する土器や石器、土偶や土版、鐸形土製品、石棒、石刀等といった土製品や石製品が出土しています。
記念物としての性格を顕著に表すものとして、土偶・動物形土製品、石棒等といった道具(マツリと祈りの道具)が環状列石周辺から多く出土しており、定住化に伴って発展した当時の社会構造や精神面の成熟を示す物証となっています。
二つの環状列石の各々の中心と日時計状組石は一直線に並び、夏至の日没方向を指しており、四季を区分する「二至二分」や太陽の運行を意識していたことをうかがい知ることができます。構築場所を選定し、天体(太陽の運行)を意識し、豊かな労働力と精神性によって構築された縄文時代の代表的な環状列石であり、当時の精神文化を知る上で重要なものです。 (鹿角市教育委員会)
●大湯ストーンサークル館の手引きより
平均30kg、最大200kgもの石をこの地に運び、さまざまな形に造られた縄文からの「メッセージ』その石の数は代表的な二つの環状列石だけでも約7200個にのぼります。4000年余りの時空を超えても私たちに人としての本質を語りかけています。環状列石の傍らに立ち、耳を澄ませ、その語りかけを聞いてみませんか!
緑色の聖なる石
何の目的のため、環状列石は作られたのか謎に迫ります。
使われている医師は、遺跡から約6㎞離れた安久谷川から運んでいます。しかも青緑の石にこだわって!環状列石とは、十数個の川原石を円形や楕円形に並べた「組石(配石)遺構」が二重のサークルに並べられたものです。

環状列石と呼ばれるものは各地にもあり日本では縄文時代後期のものが北海道から東北地方北部にかけて見つかっており、大湯環状列石(秋田県鹿角市)、伊勢堂岱遺跡(秋田県北秋田市)、大森勝山遺跡(青森県弘前市)、鷲ノ木遺跡(北海道森町)、小牧野遺跡(青森県青森市)などが有名です。
環状列石には墓地説と祭祀場説があります、大湯環状列石からは詩組の下から土坑墓と思われる穴が見つかってるが小牧野遺跡にはそれがなく、土偶などの土製品や三角形石製品といった祭祀に関係する遺物が出土しています。
公式テキストBOOK The縄文より
写真も遺跡の中には入れないのでサークル館に展示されている土器類とサークル館の周りだけは写真に収めることができました。



 日時計状組石
日時計状組石 復元された竪穴式住居
復元された竪穴式住居 大湯環状列石案内図
大湯環状列石案内図 鹿角市教育委員会提供 航空写真
鹿角市教育委員会提供 航空写真 大湯環状列石は、野中堂、万座に所在する2つの環状列石を主体とする大規模な縄文時代後期(約4000年前)野遺跡です。環状列石の周辺についてはこれまでの調査により、建物跡、貯蔵穴などが規則的に分布する事がわかっています。史跡内からはさまざまなまつりや祈りに関わる遺構と遺物が発見されており、縄文時代の精神文化や社会構造を総合的に理解できる史跡として、重要視されています。
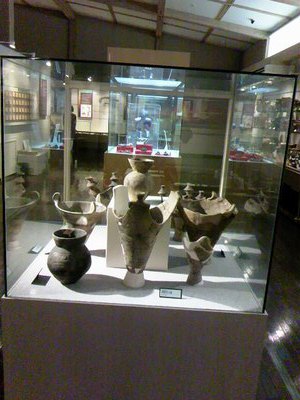 縄文人は自然のものを上手に活用して色々な道具を作りました。大湯環状列石から出土した土器などを展示してあります。
縄文人は自然のものを上手に活用して色々な道具を作りました。大湯環状列石から出土した土器などを展示してあります。

【大湯環状列石】
秋田県北東部、鹿角市の米代川上流に位置し、その支流である大湯川左岸、標高180m程の台地上に構築された、縄文時代後期前葉から中葉(紀元前2,000年~紀元前1,500年頃)の環状列石を中心とした遺跡です。
環状列石の形態は、定住とともに発達した集落形態である環状集落を背景としたものと考えられます。遺跡の中心として万座(まんざ)と野中堂(のなかどう)の二つの環状列石があり、それぞれの環状列石を取り囲むように、掘立柱建物跡、土坑・貯蔵穴、遺物廃棄域が同心円状に配置されています。これらの遺構とともに、日常使用する土器や石器、土偶や土版、鐸形土製品、石棒、石刀等といった土製品や石製品が出土しています。
記念物としての性格を顕著に表すものとして、土偶・動物形土製品、石棒等といった道具(マツリと祈りの道具)が環状列石周辺から多く出土しており、定住化に伴って発展した当時の社会構造や精神面の成熟を示す物証となっています。
二つの環状列石の各々の中心と日時計状組石は一直線に並び、夏至の日没方向を指しており、四季を区分する「二至二分」や太陽の運行を意識していたことをうかがい知ることができます。構築場所を選定し、天体(太陽の運行)を意識し、豊かな労働力と精神性によって構築された縄文時代の代表的な環状列石であり、当時の精神文化を知る上で重要なものです。 (鹿角市教育委員会)
●大湯ストーンサークル館の手引きより
平均30kg、最大200kgもの石をこの地に運び、さまざまな形に造られた縄文からの「メッセージ』その石の数は代表的な二つの環状列石だけでも約7200個にのぼります。4000年余りの時空を超えても私たちに人としての本質を語りかけています。環状列石の傍らに立ち、耳を澄ませ、その語りかけを聞いてみませんか!
緑色の聖なる石
何の目的のため、環状列石は作られたのか謎に迫ります。
使われている医師は、遺跡から約6㎞離れた安久谷川から運んでいます。しかも青緑の石にこだわって!環状列石とは、十数個の川原石を円形や楕円形に並べた「組石(配石)遺構」が二重のサークルに並べられたものです。

環状列石と呼ばれるものは各地にもあり日本では縄文時代後期のものが北海道から東北地方北部にかけて見つかっており、大湯環状列石(秋田県鹿角市)、伊勢堂岱遺跡(秋田県北秋田市)、大森勝山遺跡(青森県弘前市)、鷲ノ木遺跡(北海道森町)、小牧野遺跡(青森県青森市)などが有名です。
環状列石には墓地説と祭祀場説があります、大湯環状列石からは詩組の下から土坑墓と思われる穴が見つかってるが小牧野遺跡にはそれがなく、土偶などの土製品や三角形石製品といった祭祀に関係する遺物が出土しています。
公式テキストBOOK The縄文より
9月18日まで八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館に展示されている国宝の「合掌土偶」を一目見たくて八戸市へ行ってきました。この土偶は是川遺跡の風張1遺跡(かざはり1いせき)から出土しました。
八戸市の資料によると第15号竪穴住居跡出土土器「合掌土偶」が製作された時期は、土偶の形態からみて、縄文時代後期後半(約3,500年前頃)のものであるとしています。
 高さ 19.8㎝
高さ 19.8㎝
 両ももの付け根やひざの割れたところはアスファルトで修復しています。
両ももの付け根やひざの割れたところはアスファルトで修復しています。
 体の所々に赤い顔料が残っていますがもともとは赤色に塗られていたと考えられます
体の所々に赤い顔料が残っていますがもともとは赤色に塗られていたと考えられます
 全身に細かな模様が付けられています
全身に細かな模様が付けられています



 国宝指定書
国宝指定書
 「合掌土偶の出土状況」
「合掌土偶の出土状況」
第15号竪穴住居跡の出入り口から向かって奥の北壁際から出土している。右側面を下にし、正面を住居中央に向け、背面は住居壁面に寄りかかるように確認された。また、出土時に欠けていた左足部分は、2.5m離れた西側の床面から出土した。土偶は、一般的に捨て場や遺構外からの出土例が非常に多いが、住居の片隅に置かれた様な状態で出土した例は非常に少ない。
 「合掌土偶を出土した第15号竪穴住居」合掌土偶は、平成元年7月、長芋作付けによる緊急発掘調査で出土したものである。
「合掌土偶を出土した第15号竪穴住居」合掌土偶は、平成元年7月、長芋作付けによる緊急発掘調査で出土したものである。
 「風張1遺跡位置図」
「風張1遺跡位置図」
土偶が出土した風張1遺跡は八戸市庁から南方へ4.3 km、新井田川の右岸に位置し、縄文時代晩期で有名な是川遺跡の対岸に存在する。
八戸市の是川地区にある風張遺跡の竪穴住居跡から出土した縄文時代後期(約3,500年前)の土偶。まるで祈るかのように正面で両手を合わせ、両肘を立てて座るその姿から「合掌土偶」と呼ばれるようになった。信仰や出産などと関連付けて語られることが多く、縄文の精神世界を伝える貴重なものである。平成21年7月、国宝に指定された。
【是川石器時代遺跡】
是川石器時代遺跡は、中居・一王寺。堀田の三つの遺跡からなり、新井田川左岸の段丘上に立地します。前期から晩期の集落遺跡群で、日本考古学史に残る数々の発見がありました。一王寺遺跡では、細長いバケツ型の土器が大量にみつかり、「円筒土器」の名がつけられ、東北地方北部の前・中期の標識名になりました。堀田遺跡は土器とともに宋銭が出土し、縄文文化の週末年代をめぐる論争の舞台となりました。中居遺跡では、漆器をはじめ様々な植物質遺物が出土したことで、全国的に知られています。本遺跡は、長期的な集落の変遷や漆芸技術の系譜を考える上で重要な遺跡です。

今迄に全国で2万点以上出土している土偶で国宝に指定されている物は次の「縄文のビーナス」「縄文の女神」「中空土偶」「仮面の女神」「合掌土偶」の5点だけです。
風張1遺跡から出土した土偶は座った状態で両腕を膝の上に置き、正面で手を合わせ、指を組んだポーズを取っていることから合掌土偶と称されています。
『史跡 是川石器時代遺跡』
八戸市を北流する、新井田川左岸の標高10~44mの台地上に立地する遺跡です。堀田(ほった)遺跡(縄文時代中期)、一王寺(いちおうじ)遺跡(縄文時代前~中期)、中居(なかい)遺跡(縄文時代晩期)の総称で、中でも中居遺跡は亀ヶ岡文化を代表する遺跡の一つです。
集落の規模は、縄文時代中期や後期と比較すると小規模ですが、居住域、墓域、加工場、捨て場、祭祀場など多様な遺構が見つかっています。
中居遺跡の低湿地には沢があり、そこから捨て場が検出されました。捨て場には、トチやクルミといった木の実の殻をはじめ、獣骨や魚骨、貝類など多様な食料残滓(ざんし)が含まれています。特にトチの殻が大量に出土しており、最大80cmの厚さで堆積していました。捨て場からは、通常では腐って残らない、漆器やヤスなど植物質の道具が出土したほか、沢地ではトチのアク抜きをするための水さらし場も見つかっています。
また、花粉・種子・樹木などの分析から、集落やその周辺は、縄文人により有用植物を中心に管理され、人工林から里山を経て狩場である自然林へと繋がるような、同心円状の人為的な生態系を作り出して自然と共生していたと考えられます。
垣ノ島遺跡で登場した縄文の漆工芸技術は、道具を装飾するだけではなく、強化する目的で使われていました。是川石器時代遺跡においても、人工林や里山で、漆液を採取するためにウルシの木の管理を行い、漆液の採取時期を考慮しながら木地となる樹木を伐採・加工するなど、漆製品の高度で計画的な生産活動を読み取ることができます (八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館)
八戸市の資料によると第15号竪穴住居跡出土土器「合掌土偶」が製作された時期は、土偶の形態からみて、縄文時代後期後半(約3,500年前頃)のものであるとしています。
 高さ 19.8㎝
高さ 19.8㎝ 両ももの付け根やひざの割れたところはアスファルトで修復しています。
両ももの付け根やひざの割れたところはアスファルトで修復しています。 体の所々に赤い顔料が残っていますがもともとは赤色に塗られていたと考えられます
体の所々に赤い顔料が残っていますがもともとは赤色に塗られていたと考えられます 全身に細かな模様が付けられています
全身に細かな模様が付けられています


 国宝指定書
国宝指定書 「合掌土偶の出土状況」
「合掌土偶の出土状況」第15号竪穴住居跡の出入り口から向かって奥の北壁際から出土している。右側面を下にし、正面を住居中央に向け、背面は住居壁面に寄りかかるように確認された。また、出土時に欠けていた左足部分は、2.5m離れた西側の床面から出土した。土偶は、一般的に捨て場や遺構外からの出土例が非常に多いが、住居の片隅に置かれた様な状態で出土した例は非常に少ない。
 「合掌土偶を出土した第15号竪穴住居」合掌土偶は、平成元年7月、長芋作付けによる緊急発掘調査で出土したものである。
「合掌土偶を出土した第15号竪穴住居」合掌土偶は、平成元年7月、長芋作付けによる緊急発掘調査で出土したものである。 「風張1遺跡位置図」
「風張1遺跡位置図」土偶が出土した風張1遺跡は八戸市庁から南方へ4.3 km、新井田川の右岸に位置し、縄文時代晩期で有名な是川遺跡の対岸に存在する。
八戸市の是川地区にある風張遺跡の竪穴住居跡から出土した縄文時代後期(約3,500年前)の土偶。まるで祈るかのように正面で両手を合わせ、両肘を立てて座るその姿から「合掌土偶」と呼ばれるようになった。信仰や出産などと関連付けて語られることが多く、縄文の精神世界を伝える貴重なものである。平成21年7月、国宝に指定された。
【是川石器時代遺跡】
是川石器時代遺跡は、中居・一王寺。堀田の三つの遺跡からなり、新井田川左岸の段丘上に立地します。前期から晩期の集落遺跡群で、日本考古学史に残る数々の発見がありました。一王寺遺跡では、細長いバケツ型の土器が大量にみつかり、「円筒土器」の名がつけられ、東北地方北部の前・中期の標識名になりました。堀田遺跡は土器とともに宋銭が出土し、縄文文化の週末年代をめぐる論争の舞台となりました。中居遺跡では、漆器をはじめ様々な植物質遺物が出土したことで、全国的に知られています。本遺跡は、長期的な集落の変遷や漆芸技術の系譜を考える上で重要な遺跡です。

今迄に全国で2万点以上出土している土偶で国宝に指定されている物は次の「縄文のビーナス」「縄文の女神」「中空土偶」「仮面の女神」「合掌土偶」の5点だけです。
風張1遺跡から出土した土偶は座った状態で両腕を膝の上に置き、正面で手を合わせ、指を組んだポーズを取っていることから合掌土偶と称されています。
『史跡 是川石器時代遺跡』
八戸市を北流する、新井田川左岸の標高10~44mの台地上に立地する遺跡です。堀田(ほった)遺跡(縄文時代中期)、一王寺(いちおうじ)遺跡(縄文時代前~中期)、中居(なかい)遺跡(縄文時代晩期)の総称で、中でも中居遺跡は亀ヶ岡文化を代表する遺跡の一つです。
集落の規模は、縄文時代中期や後期と比較すると小規模ですが、居住域、墓域、加工場、捨て場、祭祀場など多様な遺構が見つかっています。
中居遺跡の低湿地には沢があり、そこから捨て場が検出されました。捨て場には、トチやクルミといった木の実の殻をはじめ、獣骨や魚骨、貝類など多様な食料残滓(ざんし)が含まれています。特にトチの殻が大量に出土しており、最大80cmの厚さで堆積していました。捨て場からは、通常では腐って残らない、漆器やヤスなど植物質の道具が出土したほか、沢地ではトチのアク抜きをするための水さらし場も見つかっています。
また、花粉・種子・樹木などの分析から、集落やその周辺は、縄文人により有用植物を中心に管理され、人工林から里山を経て狩場である自然林へと繋がるような、同心円状の人為的な生態系を作り出して自然と共生していたと考えられます。
垣ノ島遺跡で登場した縄文の漆工芸技術は、道具を装飾するだけではなく、強化する目的で使われていました。是川石器時代遺跡においても、人工林や里山で、漆液を採取するためにウルシの木の管理を行い、漆液の採取時期を考慮しながら木地となる樹木を伐採・加工するなど、漆製品の高度で計画的な生産活動を読み取ることができます (八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館)
亀ヶ岡石器時代遺跡は江戸時代から、造形的に優れた土器が出土することが知られ、北海道から北日本を中心とする土器を中心とした物質文化、「亀ヶ岡文化」の名称の由来となっています。弘前藩の記事が記載された「永禄日記(館野越本)」や、滝沢馬琴らの鑑賞会の記録「耽奇漫録」などにも、出土品の記録が残されています。また出土数土器の素晴らしさは外国人も魅了し、出島のオランダ商館を通じ、ヨーロッパ諸国にも流出しています。
遺跡は標高7~18m程度の舌状大地(亀山地区)とそれを囲む南北の低湿地(北:近江野沢地区、南:沢根地区)にまたがって立地しています。
土偶、赤塗などの彩色土器、漆器などの遺跡を代表する遺物は南北の低湿地から出土しています。
また、台地部分の亀山地区の南縁部からは、縄文晩期の土坑墓群が確認されたほか、近年の発掘調査で台地北西端部から同時期の竪穴建物跡が初めて発見されました。
これらのことから、従来から言われていたように台地の亀山地区に住居などの居住域が位置し、台地の南縁部に墓域が形成され、その外側に位置し台地を取り囲む低湿地に土器などの「捨て場」が形成されているという、縄文晩期の空間構成が推定できるようになり、「亀ヶ岡文化」を育んだ人々のムラの姿が明らかになりつつあります。
縄文文化 The Jomon Culturee
縄文文化は、紀元前約1万3千年に始まり、世界的にも稀な生物多様性に恵まれた生態系に適応し、自然との共生のもと、約1万年間にわたる持続可能な社会を形成した日本列島特有の先史文化です。本格的な農耕と牧畜を選択することなく、狩猟・採集・漁猟を生業の基盤としながら定住を達成し、協調的な社会を作り上げ、それを長期間継続できた縄文文化は、世界の他地域における新石器時代の文化とは全く異なり、先史文化としては世界史上極めて稀有なものです。
縄文時代と世界史の比較年表
【年代】【時代区分】【主な出来事】【●世界の出来事】【縄文遺跡群】
旧石器時代 細石器文化が日本列島に広がる ●北京原人が活躍する
●ラスコー洞窟の絵画が描かれる
遺跡は標高7~18m程度の舌状大地(亀山地区)とそれを囲む南北の低湿地(北:近江野沢地区、南:沢根地区)にまたがって立地しています。
土偶、赤塗などの彩色土器、漆器などの遺跡を代表する遺物は南北の低湿地から出土しています。
また、台地部分の亀山地区の南縁部からは、縄文晩期の土坑墓群が確認されたほか、近年の発掘調査で台地北西端部から同時期の竪穴建物跡が初めて発見されました。
これらのことから、従来から言われていたように台地の亀山地区に住居などの居住域が位置し、台地の南縁部に墓域が形成され、その外側に位置し台地を取り囲む低湿地に土器などの「捨て場」が形成されているという、縄文晩期の空間構成が推定できるようになり、「亀ヶ岡文化」を育んだ人々のムラの姿が明らかになりつつあります。
縄文文化 The Jomon Culturee
縄文文化は、紀元前約1万3千年に始まり、世界的にも稀な生物多様性に恵まれた生態系に適応し、自然との共生のもと、約1万年間にわたる持続可能な社会を形成した日本列島特有の先史文化です。本格的な農耕と牧畜を選択することなく、狩猟・採集・漁猟を生業の基盤としながら定住を達成し、協調的な社会を作り上げ、それを長期間継続できた縄文文化は、世界の他地域における新石器時代の文化とは全く異なり、先史文化としては世界史上極めて稀有なものです。
縄文時代と世界史の比較年表
【年代】【時代区分】【主な出来事】【●世界の出来事】【縄文遺跡群】
旧石器時代 細石器文化が日本列島に広がる ●北京原人が活躍する
●ラスコー洞窟の絵画が描かれる
----------------------------------------------------------------------------------
紀元前約13000年 草創期 土器や石鏃の使用が始まり、定住化が進み、
ムラが出現する 大平山元遺跡
----------------------------------------------------------------------------------
紀元前約9000年 早期 気候の温暖化が進み、海水面が上昇する(縄文海進)
●長江下流域で稲作が始まる
長七谷地貝塚、垣ノ島遺跡(~後期)
-----------------------------------------------------------------------------------
紀元前約5000年 前期 円筒土器文化の成立 ●中国文明の始まり
●メソポタミア文明の始まり
北黄金貝塚、三内丸山遺跡(~中期)、田小屋野貝塚(~中期)、二ッ森貝塚(~中期)、入江・高砂貝塚(~晩期)、是川石器時代遺跡(~晩期)
----------------------------------------------------------------------------------------
紀元前約3000年 中期 東日本に大規模な集落が発達する
●クフ王のピラミッド建設 ●インダス文明の始まり
大船遺跡 御所野遺跡
紀元前約9000年 早期 気候の温暖化が進み、海水面が上昇する(縄文海進)
●長江下流域で稲作が始まる
長七谷地貝塚、垣ノ島遺跡(~後期)
-----------------------------------------------------------------------------------
紀元前約5000年 前期 円筒土器文化の成立 ●中国文明の始まり
●メソポタミア文明の始まり
北黄金貝塚、三内丸山遺跡(~中期)、田小屋野貝塚(~中期)、二ッ森貝塚(~中期)、入江・高砂貝塚(~晩期)、是川石器時代遺跡(~晩期)
----------------------------------------------------------------------------------------
紀元前約3000年 中期 東日本に大規模な集落が発達する
●クフ王のピラミッド建設 ●インダス文明の始まり
大船遺跡 御所野遺跡
紀元前約2000年 後期 環状列石が出現する
●ハンムラビ法典ができる●殷王朝の成立●ツタンカーメン王即位 鷲ノ木遺跡、小牧野遺跡、伊勢堂岱遺跡、大湯環状列石、キウス周堤墓群
----------------------------------------------------------------------------------------
紀元前約1000年 晩期 亀ヶ岡文化が栄える ●春秋時代
北部九州に稲作が伝来する
亀ヶ岡石器時代遺跡、大森勝山遺跡
----------------------------------------------------------------------------------------
紀元前約300年 弥生時代 吉野ケ里遺跡が栄える ●秦の中国統一●コロッセウム建設
 遮光器土偶は石碑が建っている場所から出土しました。
遮光器土偶は石碑が建っている場所から出土しました。

 このあたり一帯が亀ヶ岡遺跡です
このあたり一帯が亀ヶ岡遺跡です

つがる市教育委員会の資料をもとに亀ヶ岡石器時代遺跡の事を勉強させてもらいました。特に亀ヶ岡考古資料室では色々な出土資料の展示品をみせていただきました。その他、木造駅周辺の観光案内も詳しく教えていただきその日の観光には大変役に立ちました。
亀ヶ岡遺跡は岩木川左岸に立地する縄文時代晩期の遺跡です。江戸時代から優れた土器が多数出土することで知られ「亀ヶ岡文化」の名前の由来になりました。亀山、沢根及び近江野沢の三地区からなり、土坑墓群、漆塗り製品、ヒスイ製品の玉類や大型の遮光器土偶などが発見されました。





通信関係の料金設定や他社乗り換え時の違約金制度について納得できない点があります。
通信関係の料金はある一定の期間、月々の請求額はほぼ同じ料金で請求が来るので余り気にすることがないのですが、或る時突然請求金額がいつもより多くなっていることに気付くことがあります。
この事はもともと契約の時に1年、2年、3年、5年、などの契約期間があり契約期間満了でその時点から金額が上がったるようになっています。
契約も自動更新で何の通知もなく更新するようなシステムになっています。
契約時に一通り説明を受けますが誰もがその事をいつまでも覚えていることはまずありえません。
値段が上がって初めて契約の事を思い出すのが世の中の人すべてだとおもいます。
通信料金は上がるは,もし他社に乗り換えでもすれば違約金が発生します、このような契約の在り方に疑問を感じます。
人の記憶力を逆手に取るような商法で許しがたいものがあります。
皆さんはどう思いますか?

事前に値上がりは告知(契約時)してはしているものの1年以上前のことはほとんどの人は覚えていません。
法律的には有りなんでしょうが・・。




