写真を見て何を感じますか?

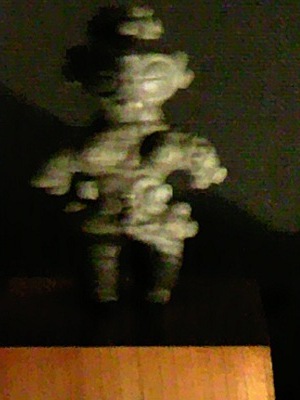








































三内丸山遺跡には青森へ到着した当日と最終日の2回に分けて見学しました。到着した日、遺跡を一通り見て廻り、縄文時遊館にも立ち寄って、遺跡から出土したもので一番気を引いたものが土偶でした。弥生時代にはほとんど見かけないものです。そんなきっかけもあって、今回立ち寄った資料館では土偶の写真を主に撮ることにしました。土偶は板のように平たく十字型をしたものがほとんどで円筒土器文化特有のもので「板状土偶」とよばれています。胸とおへその表現がある事から女性を表していると考えられています。土偶は壊れた状態で発見されることが多くわざと壊されたようにも考えられ祭祀に使われた可能性が高いと考えられています。三内丸山遺跡では縄文時代前期末ごろから薄い板状の十字形をした土偶が作られるようになり両手を横に広げたような形をしており足のないものが多いのですが中期の終わり頃には立つものも見られます。
子孫の繁栄や自然の豊饒(ほうじょう)を祈願する際の道具あるいは地母神を表したなどの 説があります。
土偶が作られる以前は数は少ないものの軟質の石材を利用した石製の人形が作られました。菱形状に人体を表し、顔の表現や手足のないものが大半です。中期に入り土偶が増加すると岩偶は減少します。用途は土偶と同じと考えられています。
東奥日報社発行 特別史跡三内丸山遺跡という本に青森県教育庁文化財保護課総括主幹の小笠原雅行さんがまとめられた縄文コラム「土偶」の記事があります。大変わかり易く書かれているので抜き取ってみました。
三内丸山遺跡では、これまで国内最多の2000点以上の土偶が出土しています。土偶はその字のごとく人形(ひとがた)を表しています。縄文時代に登場し、弥生時代になると極端に減少することから、縄文文化を特徴づける遺物の一つと言えます。
遺跡を調査すると、鍋や容器としての土器、狩猟や食料加工などの石器は好く出土しますが、土偶が出土することは多くはあ りません。土偶が増える縄文時代中期の遺跡は約600ヶ所確認されていますが、土偶が出土したのはその10%程度です。また、10点以上となるとわずか10遺跡程です。
三内丸山遺跡を除くと、県内で円筒土器文化期の土偶は300 点強見つかっていますが、その四分の一が青森市三内周辺に集中しています。三内丸山遺跡の土偶の点数がいかに突出しているかとともに近隣も合わせて土偶の集中域となっていることがわかります。
では、膨大な数の土偶はすべて三内丸山遺跡でつくられ、使われたのでしょうか。土偶の土の分析を行ったところ、分析対象のうち15%程度の土偶で土の成分が異なるという結果となりました。つまり、土偶の中には他の地域から持ち込まれたものが含まれている可能性があります。それがどこからなのか、逆に三内丸山遺跡から持ち出されたものはないのかなど、今後の課題と言えます。
大きさは最大32.5センチ、最小3.7センチと多様で、大中小のつくり分けがなされているようです。脚部の破片では、最大の土偶を凌ぐ大きさのものがあります。形状に極端な違いがなく、横幅に相関があると仮定すれば、高さが40センチを超えるとみられるものもあるようです。
土偶は希少なものであることから、生活必需品ではなく、精神文化に関わる道具と考えられています。後の合掌土偶や遮光器土偶など、非常に精巧につくられ、赤く塗られるものへと発展していくことを考えても、単なる玩具ではない強い精神性が感じられます。
精神文化は、定住により発達・進展したものと考えられています。集団の維持・安定、傷病の回復、自然への畏怖や感謝など、願望や思いを成就するために、日常的にあるいは季節などの節目ごとに様々な儀式・儀礼が行われたものと考えられます。
三内丸山遺跡では集落規模の増大や充実に伴い、精神文化も複雑化し、その一端を示すのが土偶です。一集落内や周辺地域にとどまらず、円筒土器文化圏内の中での心の拠りどころとなった、遺跡の性格の一面を示すものといえるのではないでしょうか。

知恵や道具を使うのは人間特有のものではありません。旧石器時代から縄文時代にかけて地球の気候は氷河期が終わり温暖化が進み自然の環境が変わったことから縄文の人達の生活の在り方もどんどん変わって行きました。それから1万5千年かけて今の私たちがいます。
どこがどれほど変わったのでしょうか?・・
便利さだけを追い求めて来たようにも思うのですが。

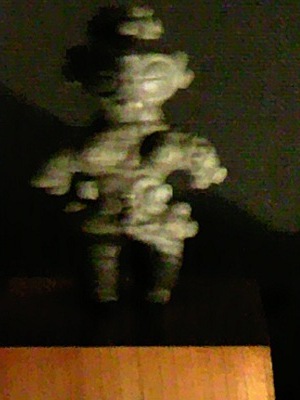








































三内丸山遺跡には青森へ到着した当日と最終日の2回に分けて見学しました。到着した日、遺跡を一通り見て廻り、縄文時遊館にも立ち寄って、遺跡から出土したもので一番気を引いたものが土偶でした。弥生時代にはほとんど見かけないものです。そんなきっかけもあって、今回立ち寄った資料館では土偶の写真を主に撮ることにしました。土偶は板のように平たく十字型をしたものがほとんどで円筒土器文化特有のもので「板状土偶」とよばれています。胸とおへその表現がある事から女性を表していると考えられています。土偶は壊れた状態で発見されることが多くわざと壊されたようにも考えられ祭祀に使われた可能性が高いと考えられています。三内丸山遺跡では縄文時代前期末ごろから薄い板状の十字形をした土偶が作られるようになり両手を横に広げたような形をしており足のないものが多いのですが中期の終わり頃には立つものも見られます。
子孫の繁栄や自然の豊饒(ほうじょう)を祈願する際の道具あるいは地母神を表したなどの 説があります。
土偶が作られる以前は数は少ないものの軟質の石材を利用した石製の人形が作られました。菱形状に人体を表し、顔の表現や手足のないものが大半です。中期に入り土偶が増加すると岩偶は減少します。用途は土偶と同じと考えられています。
東奥日報社発行 特別史跡三内丸山遺跡という本に青森県教育庁文化財保護課総括主幹の小笠原雅行さんがまとめられた縄文コラム「土偶」の記事があります。大変わかり易く書かれているので抜き取ってみました。
三内丸山遺跡では、これまで国内最多の2000点以上の土偶が出土しています。土偶はその字のごとく人形(ひとがた)を表しています。縄文時代に登場し、弥生時代になると極端に減少することから、縄文文化を特徴づける遺物の一つと言えます。
遺跡を調査すると、鍋や容器としての土器、狩猟や食料加工などの石器は好く出土しますが、土偶が出土することは多くはあ りません。土偶が増える縄文時代中期の遺跡は約600ヶ所確認されていますが、土偶が出土したのはその10%程度です。また、10点以上となるとわずか10遺跡程です。
三内丸山遺跡を除くと、県内で円筒土器文化期の土偶は300 点強見つかっていますが、その四分の一が青森市三内周辺に集中しています。三内丸山遺跡の土偶の点数がいかに突出しているかとともに近隣も合わせて土偶の集中域となっていることがわかります。
では、膨大な数の土偶はすべて三内丸山遺跡でつくられ、使われたのでしょうか。土偶の土の分析を行ったところ、分析対象のうち15%程度の土偶で土の成分が異なるという結果となりました。つまり、土偶の中には他の地域から持ち込まれたものが含まれている可能性があります。それがどこからなのか、逆に三内丸山遺跡から持ち出されたものはないのかなど、今後の課題と言えます。
大きさは最大32.5センチ、最小3.7センチと多様で、大中小のつくり分けがなされているようです。脚部の破片では、最大の土偶を凌ぐ大きさのものがあります。形状に極端な違いがなく、横幅に相関があると仮定すれば、高さが40センチを超えるとみられるものもあるようです。
土偶は希少なものであることから、生活必需品ではなく、精神文化に関わる道具と考えられています。後の合掌土偶や遮光器土偶など、非常に精巧につくられ、赤く塗られるものへと発展していくことを考えても、単なる玩具ではない強い精神性が感じられます。
精神文化は、定住により発達・進展したものと考えられています。集団の維持・安定、傷病の回復、自然への畏怖や感謝など、願望や思いを成就するために、日常的にあるいは季節などの節目ごとに様々な儀式・儀礼が行われたものと考えられます。
三内丸山遺跡では集落規模の増大や充実に伴い、精神文化も複雑化し、その一端を示すのが土偶です。一集落内や周辺地域にとどまらず、円筒土器文化圏内の中での心の拠りどころとなった、遺跡の性格の一面を示すものといえるのではないでしょうか。

知恵や道具を使うのは人間特有のものではありません。旧石器時代から縄文時代にかけて地球の気候は氷河期が終わり温暖化が進み自然の環境が変わったことから縄文の人達の生活の在り方もどんどん変わって行きました。それから1万5千年かけて今の私たちがいます。
どこがどれほど変わったのでしょうか?・・
便利さだけを追い求めて来たようにも思うのですが。



