山岡耕春著・南海トラフ地震 岩波新書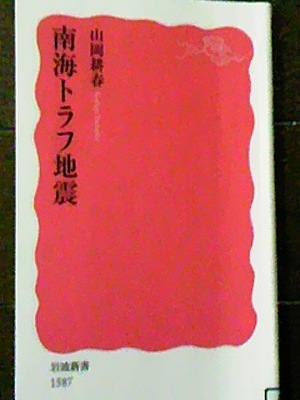

南海トラフは、東海地方から西日本太平洋側の海底の地形に付けられた名称です。そこで起きる地震を南海トラフ地震と言います。南海トラフの南側にあるフィリピン海プレート(海側のプレート)は、日本列島があるユーラシアプレート(陸側のプレート)の方に毎年数センチずつ移動し、その下にもぐり込んでいます。海側のプレートが動くと、陸側のプレートの先端が一緒に引きずり込まれて、ひずみがたまっていきます。そのひずみが限界に達した時、元に戻ろうと陸側のプレートが一気に跳ね上がり、地震が発生します。またその際、プレートが真上にある海水を一気に持ち上げるので、大きな津波が発生します。その地震は日本列島の宿命ともいえる地震でマグニチュード8~9クラス、今後30年以内の発生確率が70%という巨大地震で未曾有の大災害をもたらす可能性があると言われています。
著書には地震のことは勿論、地震の基礎知識や地震が引き起こす津波や土砂災害、火山噴火との関係など多岐にわたり過去の歴史からもひも解きながら詳しく書いておられます。被害予測と震災対策についても政府が出している被害想定を読み解きながら防災体制はどうなっているのかを詳しく調べて説明されておられます。そして最後に災害対策の限界を話されそれでも日本列島に生きるにはという締めくくりで結ばれています。読み応えのある本の1冊です。お薦めします。
最終章の1節を紹介します。
日本列島に生きる
ここで述べた地震災害も、津波災害も、火山災害も、土砂災害も、日本列島が形成されていく中で起きる自然の現象である。技術の進歩により、小さくて頻度の高い現象から徐々に災害防止がなされてきた。自然のままならば毎年土砂災害や洪水に見舞われる地域であっても、一生に一度も災害を受けないで済むようになってきた。そのため、私たち自然を征服してしまったかのような錯覚に陥っている。
しかし、大きな規模の現象ほど頻度は低い。幾世代を渡って安全であったとしても、自分の代に大災害を受けることもありうる。そのような場合、親の代からの言い伝えは役に立たない。言い伝えが伝わらない過去に起きた現象を古文書や地質学的手法から読み取り、それを自然のしくみの研究に照らし合わせて将来発生しうる現象を予測し、それぞれの地域の住民に知らせていくという作業が必要である。
提供された知見をどのように使い、判断するかは住民に任される。たとえば、普段の生活や仕事には便利ではあってっも、1〇〇年に一回の津波に襲われる可能性のある場所に住んでいる場合、より安全な場所に引っ越すか、便利さを選択して被害の可能性を人生設計の中に入れて命を守る対策を取るかは、判断の問題である。
いずれにせよ、専門家や国・自治体はできる限り正確な情報と知見を住民に伝えることが大事である。また、受け取る側も、その情報を正しく理解して活用する力を深めることが大事である。高校における地学の地位の低下が指摘されて久しい。地学は、私たちの身の回りの自然の営みを学ぶ学問である。日本列島では、地震も火山噴火も土石流も洪水もごく普通の自然の営みである。それをきちんと理解することが命を守ることに通じる。地学は命を守るための科目であることも忘れてはいけない。
私たちは、プレートの沈み込みに起因する地殻変動やマグマ活動による陸地の成長と、水の作用による土砂の運搬によってできた日本列島の地形を利用して住んでいる。そのような日本列島の自然の営みによる災害をハードで防ぐことは、とりもなおさず、自然の摂理を妨げることと同じである。洪水を防止するダムや堤防は、同時に土砂の運搬・堆積作用を防げていることを理解しなければいけない。日本列島のほとんどの平野は地殻変動で沈降しつつある場所に河川が運んできた土砂がたまってできた場所である。おそらく将来、私たちは、自然現象が担ってきた平野の堆積作用を肩代わりしなければならなくなるだろう。
内閣府が想定した南海トラフで発生する最大クラスの地震は、地震本部によると、過去1600年間には発生したことがないという。しかし、2000年前の地震によると見られる津波堆積物が発見されるなど、それ以前に最大クラスに匹敵する地震が発生していないという保証はないし、次の地震が最大クラスになることも否定できない。日本列島は過去100万年にわたってほぼ同じ変動を継続してきた。人類にとって2000年は大昔に見えても、日本列島にとってはつい最近のことである。
将来発生する現象は過去に知られている現象の範囲内とは限らず、最も大きな規模の現象かもしれない。私たちは、日本列島の自然が引き起こす、ごく稀ではあるが、大規模な災害と災害との間の、平和な時間に生かされてきたのかも知れない。このことを理解して、日本列島で生きていきたい。

山岡耕春(やまおか こうしゅん、1958年 - )は、日本の地震学・火山学者。名古屋大学大学院環境学研究科教授。専門は固体地球惑星物理学。地震や地震予知の専門家として著名。
1958年静岡県生まれ。岐阜県立大垣東高等学校、名古屋大学理学部を経て、1986年に名古屋大学大学院理学研究科博士課程(地球科学専攻)修了。
その後、東京大学地震研究所助手(伊豆大島火山観測所)などを経て、現在、名古屋大学大学院環境学研究科教授(地震火山・防災研究センター)。また、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会の委員などを務めている。
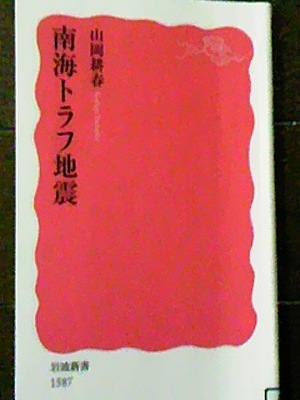

南海トラフは、東海地方から西日本太平洋側の海底の地形に付けられた名称です。そこで起きる地震を南海トラフ地震と言います。南海トラフの南側にあるフィリピン海プレート(海側のプレート)は、日本列島があるユーラシアプレート(陸側のプレート)の方に毎年数センチずつ移動し、その下にもぐり込んでいます。海側のプレートが動くと、陸側のプレートの先端が一緒に引きずり込まれて、ひずみがたまっていきます。そのひずみが限界に達した時、元に戻ろうと陸側のプレートが一気に跳ね上がり、地震が発生します。またその際、プレートが真上にある海水を一気に持ち上げるので、大きな津波が発生します。その地震は日本列島の宿命ともいえる地震でマグニチュード8~9クラス、今後30年以内の発生確率が70%という巨大地震で未曾有の大災害をもたらす可能性があると言われています。
著書には地震のことは勿論、地震の基礎知識や地震が引き起こす津波や土砂災害、火山噴火との関係など多岐にわたり過去の歴史からもひも解きながら詳しく書いておられます。被害予測と震災対策についても政府が出している被害想定を読み解きながら防災体制はどうなっているのかを詳しく調べて説明されておられます。そして最後に災害対策の限界を話されそれでも日本列島に生きるにはという締めくくりで結ばれています。読み応えのある本の1冊です。お薦めします。
最終章の1節を紹介します。
日本列島に生きる
ここで述べた地震災害も、津波災害も、火山災害も、土砂災害も、日本列島が形成されていく中で起きる自然の現象である。技術の進歩により、小さくて頻度の高い現象から徐々に災害防止がなされてきた。自然のままならば毎年土砂災害や洪水に見舞われる地域であっても、一生に一度も災害を受けないで済むようになってきた。そのため、私たち自然を征服してしまったかのような錯覚に陥っている。
しかし、大きな規模の現象ほど頻度は低い。幾世代を渡って安全であったとしても、自分の代に大災害を受けることもありうる。そのような場合、親の代からの言い伝えは役に立たない。言い伝えが伝わらない過去に起きた現象を古文書や地質学的手法から読み取り、それを自然のしくみの研究に照らし合わせて将来発生しうる現象を予測し、それぞれの地域の住民に知らせていくという作業が必要である。
提供された知見をどのように使い、判断するかは住民に任される。たとえば、普段の生活や仕事には便利ではあってっも、1〇〇年に一回の津波に襲われる可能性のある場所に住んでいる場合、より安全な場所に引っ越すか、便利さを選択して被害の可能性を人生設計の中に入れて命を守る対策を取るかは、判断の問題である。
いずれにせよ、専門家や国・自治体はできる限り正確な情報と知見を住民に伝えることが大事である。また、受け取る側も、その情報を正しく理解して活用する力を深めることが大事である。高校における地学の地位の低下が指摘されて久しい。地学は、私たちの身の回りの自然の営みを学ぶ学問である。日本列島では、地震も火山噴火も土石流も洪水もごく普通の自然の営みである。それをきちんと理解することが命を守ることに通じる。地学は命を守るための科目であることも忘れてはいけない。
私たちは、プレートの沈み込みに起因する地殻変動やマグマ活動による陸地の成長と、水の作用による土砂の運搬によってできた日本列島の地形を利用して住んでいる。そのような日本列島の自然の営みによる災害をハードで防ぐことは、とりもなおさず、自然の摂理を妨げることと同じである。洪水を防止するダムや堤防は、同時に土砂の運搬・堆積作用を防げていることを理解しなければいけない。日本列島のほとんどの平野は地殻変動で沈降しつつある場所に河川が運んできた土砂がたまってできた場所である。おそらく将来、私たちは、自然現象が担ってきた平野の堆積作用を肩代わりしなければならなくなるだろう。
内閣府が想定した南海トラフで発生する最大クラスの地震は、地震本部によると、過去1600年間には発生したことがないという。しかし、2000年前の地震によると見られる津波堆積物が発見されるなど、それ以前に最大クラスに匹敵する地震が発生していないという保証はないし、次の地震が最大クラスになることも否定できない。日本列島は過去100万年にわたってほぼ同じ変動を継続してきた。人類にとって2000年は大昔に見えても、日本列島にとってはつい最近のことである。
将来発生する現象は過去に知られている現象の範囲内とは限らず、最も大きな規模の現象かもしれない。私たちは、日本列島の自然が引き起こす、ごく稀ではあるが、大規模な災害と災害との間の、平和な時間に生かされてきたのかも知れない。このことを理解して、日本列島で生きていきたい。

山岡耕春(やまおか こうしゅん、1958年 - )は、日本の地震学・火山学者。名古屋大学大学院環境学研究科教授。専門は固体地球惑星物理学。地震や地震予知の専門家として著名。
1958年静岡県生まれ。岐阜県立大垣東高等学校、名古屋大学理学部を経て、1986年に名古屋大学大学院理学研究科博士課程(地球科学専攻)修了。
その後、東京大学地震研究所助手(伊豆大島火山観測所)などを経て、現在、名古屋大学大学院環境学研究科教授(地震火山・防災研究センター)。また、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会の委員などを務めている。



