2022年05月17日
松尾芭蕉に触れる

梅雨ではないのですが梅雨に似たこの時期、同じように思い起こされる松尾芭蕉という人物、今日は読売新聞編集手帳でも取り上げられています。
松尾芭蕉が「奥の細道」の旅に出発したのは、元禄2年3月27日と記録されている。西暦に改めれば1689年5月16日、333年前のきのうのことである◆現在の気候がどの程度変わったかは脇にどけて、観測衛星が写す列島のようすと比べたくなる。今は梅雨前線が太平洋の南海上にある。もし芭蕉が旅立つときも同じなら、前線が俳聖の背中を追いかけていくことになる◆大石田(山形県)に7月14日に到着し、そこで<五月雨を集めて涼し最上川>と詠んだ。東北南部の平均的な梅雨は6月中旬~7月下旬とされている。北上してきた前線に追いつかれたのだろうか◆芭蕉はその後、実際に最上川の川下りを体験している。雨の多い時期なのでかなりの激流だろう。 推敲すいこう を経てのちに「涼し」を「早し」に改めたのは、恐怖の川下りの体験が影響したとも考えられている。「ああ怖かった」とつぶやく俳聖を想像すると、教科書にも載る名句にひと味ちがった親しみを覚える◆週間予報に晴れマークが増えてきた。気温も高くなる。熱中症への警戒に気が抜けないとはいえ、梅雨が訪れるまでの貴重な太陽だろう。
読売新聞編集手帳 2022/05/17 編集手帳
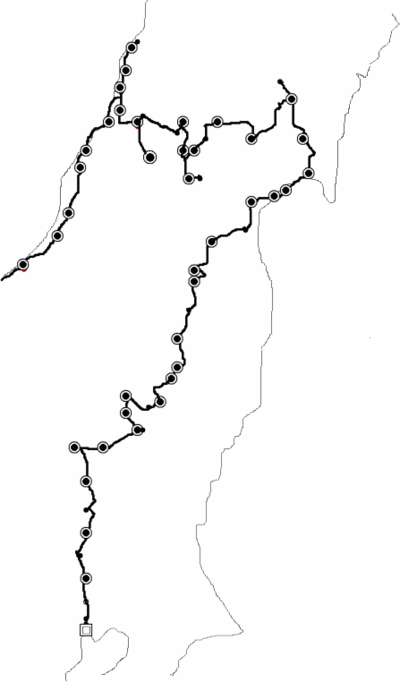
芭蕉・奥の細道全行程表
元禄2年(1689)3月27日(陰暦。現在の暦では5月16日)、46歳の松尾芭蕉は、弟子の曾良を伴として江戸の深川を出発し、陸奥、出羽、北陸の各地をまわる旅に出ました。そして8月21日、美濃の大垣に到着。この156日間、476里余に及ぶ長旅の中で、特に印象に残った出来事をまとめたのが、紀行文「おくのほそ道」です。その記述を踏まえ、同行した曾良がつけていた旅日記をもとに芭蕉たちの歩いた全行程を図にしたのが、この「奥の細道全行程図」で(芭蕉はこの後、伊勢神宮の御遷宮を拝むため大垣湊を船出した)

Posted by マー君 at 10:34│Comments(0)
│記事









