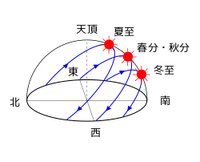2020年09月17日
旧八朔
9月17日は暦に「旧八朔」とあります。
●旧八朔とは
朔日はついたちという意味があるので、八朔とは八月朔日すなわち8月1日のことです。つまり、旧八朔とは旧暦の8月1日を指しますが、新暦では8月25日から9月23日までのいずれかになります。日中は厳しい残暑が残るものの、夜には秋の虫たちが鳴く頃といえるでしょう。
そして、ちょうど稲が実りを迎える季節でもあります。かつて国民の大半が農民だった時代には、初めて実った稲穂である初穂を恩人に贈るといった風習がありました。そのため、旧八朔には「田の実の節句」という別名もあり「田の実」と「頼み」をかけて、公家や武家も恩人に感謝して贈り物をする習慣があったのです。
●旧八朔の風習
八朔は8月1日から転じて、その頃に毎年吹く強い風を意味することもあります。農家によっては二百十日、二百二十日とともに三大厄日でもあり、収穫前の稲が駄目になってしまうリスクのある注意が必要な日でもあったのです。
何事もなく収穫をすませることができたとしても、小作人にとっては徹夜作業が続くつらい日々の始まりでもあります。そのため、大きな農家では使用人にぼたもちをふるまい、来るべき労働の毎日に備える日でもあったのです。
また、江戸時代の吉原で花魁道中が行われたのもこの日でした。京都の祇園でも芸妓や舞妓が盛装して、出入りの茶屋や芸事のお師匠さ
んに挨拶回りをする日とされていました。農家はもちろん、色街に至るまでさまざまな人たちにとって特別な日だったことがわかります。
●各地の八朔祭り
熊本県上益城群山都町(かみましきぐんやまとちょう)にある浜町では、現在でも八朔祭りが行われています。旧暦8月1日に近い9月の第1土曜日・日曜日に、高さ4mほど、長さ8mほどの大造り物が数十基も引き廻されるというダイナミックな祭りで、国内外からやって来る観光客も少なくありません。国の重要文化財である通潤橋からの放水、花火大会などもある日本を代表する秋祭りのひとつといっていいでしょう。

一方、福井県美浜町新庄区では日本の奇祭のひとつとして有名な八朔祭りが開催されています。天狗に扮した人が担いだ男性のシンボルをかたどった60cmほどの御神体で、女性の見物客をつつくというものです。つつかれた女性は子宝に恵まれるといういわれもあり、こちらも全国津々浦々からたくさんの観光客がやってきます。
山梨県都留市四日市場の生出神社では、葛飾北斎が手がけたという伝承がある幕を使った八朔祭りがあります。少なくとも江戸後期の天保年間には実施されていた記録もあるなど、歴史ある祭りのひとつであることは間違いありません。
●旧八朔とは
朔日はついたちという意味があるので、八朔とは八月朔日すなわち8月1日のことです。つまり、旧八朔とは旧暦の8月1日を指しますが、新暦では8月25日から9月23日までのいずれかになります。日中は厳しい残暑が残るものの、夜には秋の虫たちが鳴く頃といえるでしょう。
そして、ちょうど稲が実りを迎える季節でもあります。かつて国民の大半が農民だった時代には、初めて実った稲穂である初穂を恩人に贈るといった風習がありました。そのため、旧八朔には「田の実の節句」という別名もあり「田の実」と「頼み」をかけて、公家や武家も恩人に感謝して贈り物をする習慣があったのです。
●旧八朔の風習
八朔は8月1日から転じて、その頃に毎年吹く強い風を意味することもあります。農家によっては二百十日、二百二十日とともに三大厄日でもあり、収穫前の稲が駄目になってしまうリスクのある注意が必要な日でもあったのです。
何事もなく収穫をすませることができたとしても、小作人にとっては徹夜作業が続くつらい日々の始まりでもあります。そのため、大きな農家では使用人にぼたもちをふるまい、来るべき労働の毎日に備える日でもあったのです。
また、江戸時代の吉原で花魁道中が行われたのもこの日でした。京都の祇園でも芸妓や舞妓が盛装して、出入りの茶屋や芸事のお師匠さ
んに挨拶回りをする日とされていました。農家はもちろん、色街に至るまでさまざまな人たちにとって特別な日だったことがわかります。
●各地の八朔祭り
熊本県上益城群山都町(かみましきぐんやまとちょう)にある浜町では、現在でも八朔祭りが行われています。旧暦8月1日に近い9月の第1土曜日・日曜日に、高さ4mほど、長さ8mほどの大造り物が数十基も引き廻されるというダイナミックな祭りで、国内外からやって来る観光客も少なくありません。国の重要文化財である通潤橋からの放水、花火大会などもある日本を代表する秋祭りのひとつといっていいでしょう。

一方、福井県美浜町新庄区では日本の奇祭のひとつとして有名な八朔祭りが開催されています。天狗に扮した人が担いだ男性のシンボルをかたどった60cmほどの御神体で、女性の見物客をつつくというものです。つつかれた女性は子宝に恵まれるといういわれもあり、こちらも全国津々浦々からたくさんの観光客がやってきます。
山梨県都留市四日市場の生出神社では、葛飾北斎が手がけたという伝承がある幕を使った八朔祭りがあります。少なくとも江戸後期の天保年間には実施されていた記録もあるなど、歴史ある祭りのひとつであることは間違いありません。
Posted by マー君 at 08:30│Comments(0)
│暦