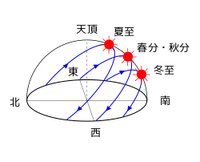2018年01月15日
小正月・左義長・正月事じまい
知らないことがまだまだある事に気づかされる今日この頃。
「左義長」という言葉はご存知でしょうか?
暮らしの歳時記というブログに説明があります。
・・小正月に正月飾りや書き初めを燃やす行事で、その煙に乗って年神様が天上に帰ってゆくとされています。「左義長」は、三毬杖(さぎちょう)という青竹で正月飾りを焼いたことに由来しますが、「どんど焼き」「とんど」とも呼ばれ、その火で焼いたお餅などを食べると無病息災で過ごせるといわれています。
このように年神様を見送って正月行事も無事終了となるので、1月15日を「正月事じまい」といい、15日までを「松の内」とする地方もあります。
どんど焼きは勿論、また、秋田のなど、「なまはげ」や「かまくら」など地方色豊かな行事は理解できても「左義長」は分からないという人はほとんどだと思います。
日本語って奥が広いですね。
ちなみに今日は小正月です。
大正月には門松を飾りますが、小正月には餅花(もちばな)をなどを飾ります。これは、豊作の予祝の大切の行事でした。そのため「花正月」ともいいます。
この日の朝には、小豆粥を炊いて家族の健康を祈るならわしがあり、無病息災と五穀豊穣を願い粥をいただく風習が残っています。鏡開きのお餅を入れた小豆粥をいただきます。

餅花(もちばな)
・餅や団子を小さく丸めて柳などの木の枝につけたもの。
繭玉とも呼ばれています。
「左義長」という言葉はご存知でしょうか?
暮らしの歳時記というブログに説明があります。
・・小正月に正月飾りや書き初めを燃やす行事で、その煙に乗って年神様が天上に帰ってゆくとされています。「左義長」は、三毬杖(さぎちょう)という青竹で正月飾りを焼いたことに由来しますが、「どんど焼き」「とんど」とも呼ばれ、その火で焼いたお餅などを食べると無病息災で過ごせるといわれています。
このように年神様を見送って正月行事も無事終了となるので、1月15日を「正月事じまい」といい、15日までを「松の内」とする地方もあります。
どんど焼きは勿論、また、秋田のなど、「なまはげ」や「かまくら」など地方色豊かな行事は理解できても「左義長」は分からないという人はほとんどだと思います。
日本語って奥が広いですね。
ちなみに今日は小正月です。
大正月には門松を飾りますが、小正月には餅花(もちばな)をなどを飾ります。これは、豊作の予祝の大切の行事でした。そのため「花正月」ともいいます。
この日の朝には、小豆粥を炊いて家族の健康を祈るならわしがあり、無病息災と五穀豊穣を願い粥をいただく風習が残っています。鏡開きのお餅を入れた小豆粥をいただきます。

餅花(もちばな)
・餅や団子を小さく丸めて柳などの木の枝につけたもの。
繭玉とも呼ばれています。