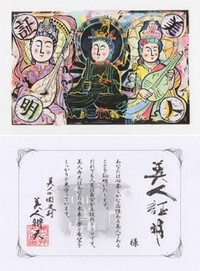2017年02月28日
今日は何の日?
今日の【春秋】を読んで、友達のブログ「今日は何の日?」という小欄を思い浮かべました。【春秋】担当者も毎日の記事のネタには色々な書物やニュースに目を通すのが、毎日のお仕事のように思いますが、今日の文章は「ふしぎなポケット」という童謡の話から、「ビスケットの日」の語源に結びつけ、締めくくりに待機児童の問題に繋げていく非常に上手な筆の運びです。いつも読ませてもらって感心しています。ありがとう。・・・
 今日は何の日?
今日は何の日?
 2月28日はビスケットの日
2月28日はビスケットの日

ポケットのなかには ビスケットがひとつ/ポケットをたたくと ビスケットはふたつ・・・。まど・みちおさん作詞の「ふしぎなポケット」。ぽけっとをたたくたびにビスケットが増えていく►きょうは「ビスケットの日」。全国ビスケット協会によると、長崎に留学していた水戸藩の蘭医、柴田方庵は、保存が利く食料としてビスケットに着目。製法を調べ、藩に書き送ったのが安政2年(1855)年2月28日だった。方庵の日記は、日本でビスケットが作られていたことを示すさいこのきろくという►また、ビスケットの語源はラテン語で「2度焼かれた物」、「2(に)どや(8)かれた」の語呂合わせも兼ね、2月28日を記念日にしたそうだ►ポケットをたたくと増えるのが保育所だったら---。そう願いたくなる保護者も多かろう。許可保育所に4月入所を希望しながら、〝落選〟した母親らが国会で集会を開き、「保育所を増やして」と国会議員に訴えた►昨年、「保育園落ちた日本死ね」という
匿名のブログから注目が集まった待機児童問題。国や自治体も保育所増設や保育士確保に力を入れているが、現状はまだ厳しいようだ。►また落ちた、子供の預け先がない、仕事を続けられない・・・ネット上には、何度も焼かれるような思いをする親たちの悲鳴が。不思議なポケットはないけれど、親子で笑ってビスケットを楽しめる社会へ少しでも近づけたい。
西日本新聞 【春秋】 2017・2・28
●まど・みちお
まど・みちお(本名:石田 道雄〈いしだ みちお〉、1909年〈明治42年〉11月16日 - 2014年〈平成26年〉2月28日)は、日本の詩人。25歳のときに北原白秋にその才能を認められ、33歳のときには太平洋戦争に召集された。詩作りは20代から始め、以来生涯にわたって詩を作り続けた。創作意欲の源は、政治・行政・教育・経済・戦争などに対する不満である。「ぞうさん」や「やぎさんゆうびん」などの、そのおおらかでユーモラスな作品は童謡としても親しまれている。表現の前に存在があるという意味で「存在の詩人」とも称される。
●柴田方庵 しばた-ほうあん
1800-1856 江戸時代後期の蘭方医。
寛政12年生まれ。江戸で朝川善庵に儒学をまなぶ。長崎で竹内玄同,青木周弼(しゅうすけ)らシーボルトの門人とまじわり,西洋医学をおさめる。種痘法をまなび,長崎,大坂などで実施。帰郷して常陸(ひたち)水戸藩医となるが,のち長崎で開業。嘉永(かえい)4年(1851)験温器をつくる。安政3年10月8日死去。57歳。名は海。字(あざな)は谷王。
 今日は何の日?
今日は何の日? 2月28日はビスケットの日
2月28日はビスケットの日
ポケットのなかには ビスケットがひとつ/ポケットをたたくと ビスケットはふたつ・・・。まど・みちおさん作詞の「ふしぎなポケット」。ぽけっとをたたくたびにビスケットが増えていく►きょうは「ビスケットの日」。全国ビスケット協会によると、長崎に留学していた水戸藩の蘭医、柴田方庵は、保存が利く食料としてビスケットに着目。製法を調べ、藩に書き送ったのが安政2年(1855)年2月28日だった。方庵の日記は、日本でビスケットが作られていたことを示すさいこのきろくという►また、ビスケットの語源はラテン語で「2度焼かれた物」、「2(に)どや(8)かれた」の語呂合わせも兼ね、2月28日を記念日にしたそうだ►ポケットをたたくと増えるのが保育所だったら---。そう願いたくなる保護者も多かろう。許可保育所に4月入所を希望しながら、〝落選〟した母親らが国会で集会を開き、「保育所を増やして」と国会議員に訴えた►昨年、「保育園落ちた日本死ね」という
匿名のブログから注目が集まった待機児童問題。国や自治体も保育所増設や保育士確保に力を入れているが、現状はまだ厳しいようだ。►また落ちた、子供の預け先がない、仕事を続けられない・・・ネット上には、何度も焼かれるような思いをする親たちの悲鳴が。不思議なポケットはないけれど、親子で笑ってビスケットを楽しめる社会へ少しでも近づけたい。
西日本新聞 【春秋】 2017・2・28
●まど・みちお
まど・みちお(本名:石田 道雄〈いしだ みちお〉、1909年〈明治42年〉11月16日 - 2014年〈平成26年〉2月28日)は、日本の詩人。25歳のときに北原白秋にその才能を認められ、33歳のときには太平洋戦争に召集された。詩作りは20代から始め、以来生涯にわたって詩を作り続けた。創作意欲の源は、政治・行政・教育・経済・戦争などに対する不満である。「ぞうさん」や「やぎさんゆうびん」などの、そのおおらかでユーモラスな作品は童謡としても親しまれている。表現の前に存在があるという意味で「存在の詩人」とも称される。
●柴田方庵 しばた-ほうあん
1800-1856 江戸時代後期の蘭方医。
寛政12年生まれ。江戸で朝川善庵に儒学をまなぶ。長崎で竹内玄同,青木周弼(しゅうすけ)らシーボルトの門人とまじわり,西洋医学をおさめる。種痘法をまなび,長崎,大坂などで実施。帰郷して常陸(ひたち)水戸藩医となるが,のち長崎で開業。嘉永(かえい)4年(1851)験温器をつくる。安政3年10月8日死去。57歳。名は海。字(あざな)は谷王。
Posted by マー君 at 11:34│Comments(0)
│つぶやき